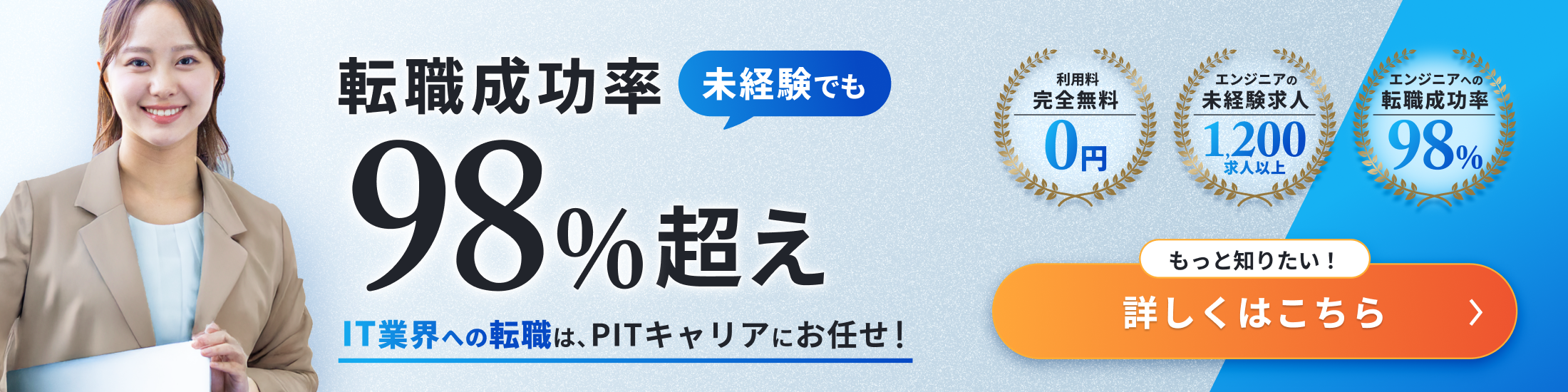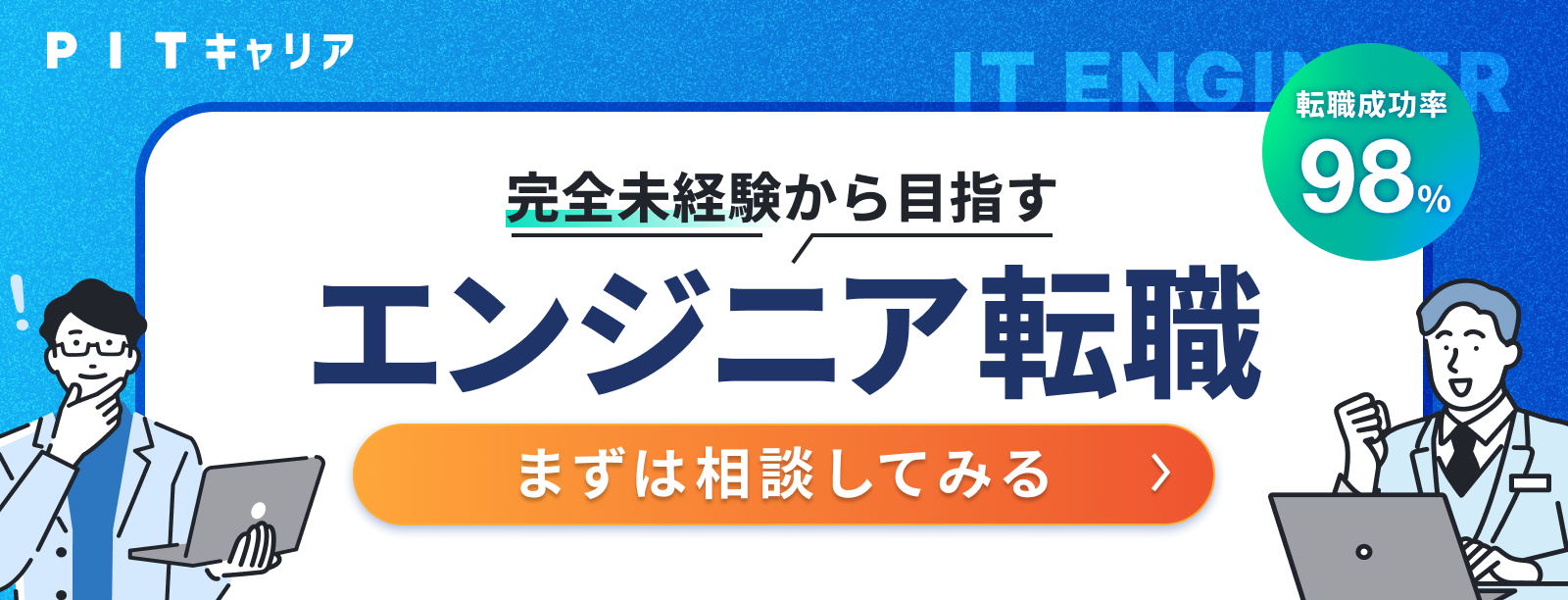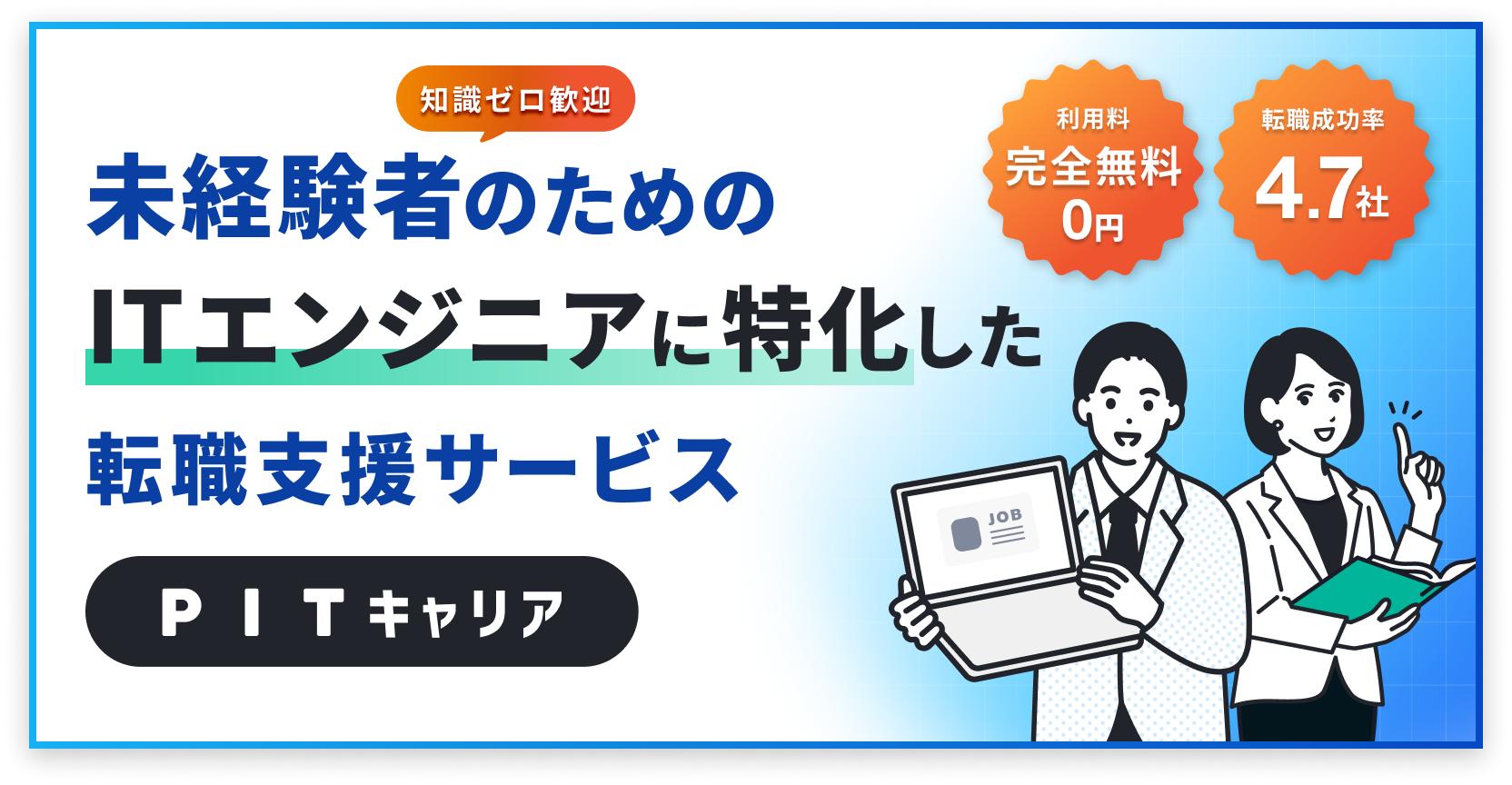カテゴリー
ITコンサルタントのキャリアパスと将来性を徹底解説!
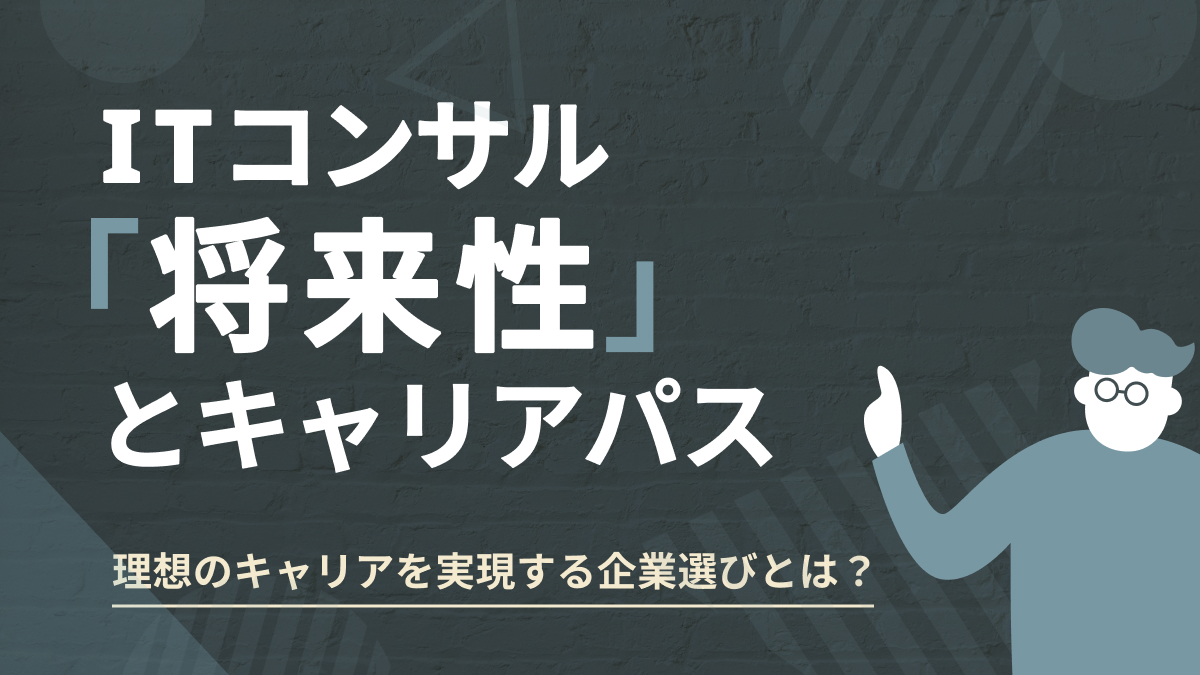
皆さん、こんにちは!
活学キャリアです。

ITコンサルタントはどんなキャリアを歩んでいくのかな?



ITコンサルタントの将来性ってどうなんだろう?
ITコンサルタントは、企業のIT戦略やシステム導入、業務改善を支援するプロフェッショナルです。
専門性が高く、市場ニーズも拡大していることから、「キャリアアップの可能性が大きい職種」として注目されています。
しかし、具体的にどんなキャリアパスを描けるのか、未経験者がどう成長していけるのかは、意外と知られていません。
この記事では、ITコンサルタントのキャリアパスと将来性について、初心者にも分かりやすく解説します。
大手企業・SIer・ベンチャーなどの違いや、実際の転職者のキャリア事例も交えながら、自分らしいキャリアの作り方をイメージできる内容にしています。
- ITコンサルタントの具体的なキャリアパスがわかる
- ITコンサルタントのキャリアパスの組み立て方が分かる
- 理想のキャリアパスを実現する為の企業選びの考え方が分かる
ITコンサルタントのキャリアパスとは?まずは全体像を理解しよう
ITコンサルタントのキャリアパスは、一気にマネージャーや戦略案件に飛び込むわけではありません。
ほとんどの人が、まずは基礎を固めて少しずつステップアップしていきます。



最初はどんな仕事から始まるの・・・?



どのくらいの期間で次の役割に進めるの・・・?
と不安に思う方も多いでしょう。
ここでは、未経験からでもイメージしやすいように、ITコンサルタントが歩む基本ステップを順を追って紹介します。
- まずは、「データ収集」、「市場調査」、「資料作成」などに携わる
- 1~3年ほど経験を積むと課題の分析や改善策の提案など、より上流の工程に携われる
- さらに年次が進むと複数のプロジェクトやチームを統括する立場になる
まずはここから|ITコンサルの基本ステップ
ITコンサルタントとしてのキャリアは、多くの場合「ジュニアポジション」から始まります。
ここでは“アナリスト”や“アソシエイト”という肩書で呼ばれることが多く、主な業務はデータ収集・市場調査・資料作成・議事録の作成などです。
たとえば、クライアントが新しいシステムを導入するプロジェクトであれば、導入の目的や背景、既存業務の課題を調べ、その結果をPowerPointやExcelで分かりやすくまとめる、といった作業を担当します。
1〜3年ほど経験を積むと「シニアアソシエイト」「コンサルタント」と呼ばれるポジションに昇格し、課題の分析や改善策の提案など、より上流の工程に関わります。
この段階になると、クライアントとの打ち合わせに同席し、自ら発言する機会も増えます。
さらに経験を積むと「マネージャー」「シニアマネージャー」へと進み、複数のプロジェクトやチームを統括する立場になります。
ジュニアは“舞台の裏で大道具や小道具を準備するスタッフ”、シニアは“舞台の流れや演出を整える舞台監督補佐”、マネージャーは“全体の脚本と演出を決め、舞台を成功に導く総監督”なんてイメージを持っていただいたら良いと思います。
ジュニア・シニア・マネージャー職…役職ごとの期待される役割
ITコンサル業界では、役職ごとに求められる能力と責任範囲が大きく異なります。
ジュニア職では、まず「正確に」「期限通りに」業務をこなすことが最重要です。
例えば、データ入力一つでもミスが許されず、細かい確認作業が欠かせません。
この話を聞くと



ITコンサルタントの仕事なのに、なんでデータ入力の仕事をするの?
と思われる方もいらっしゃると思います。
実は、ITコンサルのジュニア職でもデータ入力や検証作業は普通にあります。
ただし「エクセルに顧客名を打ち込む」みたいな単純事務というよりは、プロジェクトで使う重要データや検証用の数値を扱うケースが多いです。
例えば
- システム移行プロジェクト
旧システムから新システムにデータを移す際、移行用の表に顧客IDや契約情報を登録する
→ 1桁でも間違えると顧客データが紐付かず大きなトラブルになる - 検証(テスト)作業
新しく作ったシステムに、想定通りの数字が表示されるか確認するためにテストデータを入力
→ 間違った値を入力すると、バグの原因が見つからない - 分析用データの作成
クライアントへの報告資料用に、大量の数値を集計し、フォーマットに合わせて入力
→ 1つの数値がズレるとグラフや結論が変わってしまう
といった業務などが有ります。
この様に、「地味に見えるけど、結果に直結する作業」なので、ミス防止のための二重チェックや承認フローがしっかりあるんです。
ITコンサルタントとして働いていくということは、先輩やマネージャーの指示を正しく理解するだけでなく、こういった背後関係も理解しながら、適切にアウトプットする力が求められます。
シニア職になると、単に与えられたタスクをこなすだけでなく、「クライアントが気づいていない課題を発見する力」が必要になります。
例えば、顧客管理システムを導入する案件で、クライアントが営業成績の集計に困っていることに気づいたら、その改善方法も合わせて提案するといった姿勢です。
マネージャー職以上では、プロジェクトの成功に責任を持つ立場になります。
複数の案件を同時に管理し、予算や人員の配分、進捗管理、リスクマネジメントまで幅広く対応します。
また、新規案件を受注するための営業活動や、経営層との折衝も重要な業務です。
大手企業の場合、このあたりから売上目標や採用活動への関与も求められるため、ビジネス全体を俯瞰できる視野が不可欠です。
転職を活かしたステップアップも可能?
ITコンサル業界はIT業界の中でも、特に転職市場が活発で、「キャリアを転職を通して加速させる」なんてことも珍しくありません。
例えば、大手SIerで5年間システム開発に携わった人が、コンサル会社に転職して要件定義やIT戦略立案に挑戦するケースがあります。
この場合、前職の技術知識を武器に、短期間でシニアポジションへ昇格できることもあります。
逆に、コンサル会社で数年経験を積んだ後、事業会社の情報システム部門やIT企画部門に移る人も多いです。
理由は、長期的に一つの会社のIT戦略を腰を据えて推進できることや、残業時間・出張頻度を抑えやすい働き方ができるからです。
さらに最近は、ベンチャー企業やスタートアップに移るケースも増えています。
新しいサービスの立ち上げやプロダクト開発に直接関われるため、「より事業に近い立場で働きたい」という人に人気です。
このように、ITコンサルタントのキャリアパスは社内昇格だけでなく、転職を組み合わせて多様な形で広がっていくのが特徴です。
キャリアの進み方は人それぞれ!パターン別のキャリアルート解説
ITコンサルタントのキャリアは一本道ではなく、関わる領域や会社の規模、そして本人の志向性によって大きく形が変わります。
ここでは、代表的な3つの領域の違いと、会社タイプ別の特徴、さらに異業種・未経験からの戦略や多様な働き方の選択肢まで詳しく解説します。
これらを知っておくことで、自分に合った道筋が見えやすくなります。
- 戦略・業務・IT領域で異なる
- 大手会社・SIer・ベンチャーそれぞれの特徴がある
- 女性・子育て世代・Uターン転職などの選択肢がある
戦略・業務・IT領域の違いでキャリアはどう変わる?
ITコンサルタントは大きく「戦略領域」「業務領域」「IT領域」に分かれます。
- 戦略領域:企業の経営課題や中長期戦略を立案する仕事。経営層とのやり取りが多く、ITだけでなく市場動向や競合分析にも関わります。例としては、製造業のDX戦略立案や、金融機関の新サービス展開のロードマップ策定など。
- 業務領域:現場の業務プロセス改善やシステム導入時の要件定義などを担当。たとえば、受発注管理の効率化や、店舗オペレーションの自動化など、現場に近い改革を行います。
- IT領域:システム設計や開発、テスト、運用改善など技術寄りの領域。クラウド移行やAI導入など、最新技術を実装に落とし込む部分で活躍します。
同じ「ITコンサルタント」という肩書きでも、この3つの領域のどこに軸足を置くかで、求められるスキルやキャリアパスは全く異なります。
例えば、戦略領域で経験を積むと経営企画部門への転職がしやすくなり、IT領域で専門性を高めるとアーキテクトや技術顧問の道が開けます。
【比較表】大手会社・SIer・ベンチャーの昇進・働き方の違い
| 項目 | 大手会社系 | SIer系 | ベンチャー系 |
| 昇進スピード | 年功序列傾向が強く、安定 | 中堅以上は成果主義 | 完全成果主義で昇進早い |
| 案件規模 | 数十億円単位の規模も | 中規模〜大規模 | 小〜中規模、多種多様 |
| 教育体制 | 研修・OJTが充実 | 現場OJT中心 | 実戦で学ぶ |
| 働き方 | 比較的安定、残業少なめ傾向 | 忙しい時期は残業多め | 波が大きいが自由度高い |
| キャリアの広がり | 海外案件や経営層直結案件あり | 技術寄りの深掘りが可能 | 起業・CxO経験に繋がりやすい |
この比較表はあくまで傾向ですが、各タイプの会社ごとにキャリアの進み方や得られる経験が大きく異なります。
まず大手会社系は、
外資・日系問わずブランド力が高く、教育制度や研修プログラムが整っています。
昇進はやや年功序列的な色合いがあり、スピード感よりも安定感を重視する人に向いています。
特に、海外案件や経営層直結のプロジェクトに携われる機会が多く、将来的に経営企画やグローバル事業に進みたい人には良い環境です。
SIer系は、システムインテグレーションや開発を強みとする企業で、案件規模は大手企業に比べるとやや小さいものの、技術的な深掘りが可能です。
成果主義の要素が強まるポジションもあり、早くから責任ある仕事を任されるチャンスもあります。
特に、開発・保守から改善提案まで一貫して関われるため、「技術に軸足を置きながらコンサル能力を磨きたい」人に合っています。
ベンチャー系は、昇進・昇給スピードが圧倒的に早く、入社1〜2年でリーダーやマネージャーになる例も珍しくありません。
その一方で、案件規模や予算は比較的小さいため、求められるのはスピードと幅広いスキルです。
制度や教育体制は整っていないことが多く、実戦を通して学ぶスタイルになります。
起業や経営層を目指す人には非常に相性が良い環境です。
さて、ここまでITコンサルタント会社の特徴を、会社の規模別に大まかな傾向をお伝えしてきましたが、あくまでもこれは全体的な傾向のお話であって、会社によって特色は違います。
中には、ベンチャーとSIerの特色を掛け合わせたような企業が存在するのも事実です。
ですが、それを外から判断するのはとても難しいことです。
そんな時は、ぜひ無料カウンセリングにお越しください。
私たちは、これまでの卒業生の実体験と、各企業の人事との繋がりなどから、企業ごとの特徴や性質を事細かに把握しています。
そのため、あなたに合った会社だけをご紹介することが出来ます。
そのためにも、転職や入社を検討する際は、給与や待遇だけでなく、将来どんなキャリアを描きたいのかをまずは明確にしつつ基準に選ぶことが重要です。
異業種・未経験からスタートする人が取るべきキャリア戦略
異業種からITコンサルタントを目指す人にとって、一番の課題は「自分の経験をどう活かすか」です。
たとえば営業職で培った顧客対応力、販売職で磨いた課題発見力など、過去のキャリアはそのまま強みになります。
ただし「未経験だから弱い」と思われないように、それを「ITコンサルタントとしてどう活かすのか」に変換して語ることが必要です。
特に大切なのは、「なぜITコンサルタントなのか」という動機と、「自分の強みがどうつながるか」を一貫性を持って説明できることです。
この部分は志望動機の核にも直結しますが、ここでは詳細には触れません。
志望動機の具体的な書き方については、こちらの記事で紹介していますので、併せて参考にしてください。
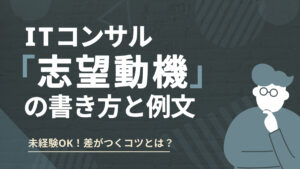
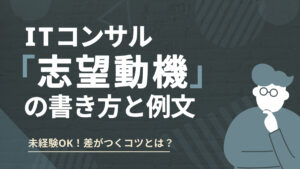
つまり、キャリア戦略を考えるうえでは「経験の棚卸し」と「未来像の言語化」の2つが欠かせません。
過去の強みを具体化し、今後どう成長して活躍するかを描くことで、人事に「未経験でも戦力になる」という印象を与えられるのです。
多様な働き方が可能に|女性・子育て世代・Uターン転職などの選択肢
近年は、ITコンサルタントの働き方も多様化しています。
フルリモートや週3〜4日の勤務、副業との掛け合わせなど、かつての「長時間労働」のイメージを覆す事例も増えています。
特に女性や子育て世代では、
- 時短勤務でPM補佐や要件定義のみ担当
- 地方在住で首都圏案件にリモート参画
- 育児と両立しながらデータ分析など専門業務に特化
といった働き方も可能になっています。
また、Uターン転職で地元企業のDX推進を支援する道もあり、「地元×IT」でのやりがいを感じながら働く人も増えています。
ただし注意したいのは、「柔軟な働き方ができる」と表向きに掲げていても、実際には裁量が限られていたり、ポジションが限定的だったりする企業も少なくないということです。
求人票や説明会だけでは見抜けない部分なので、企業の風土や働き方のリアルを把握しておくことが重要です。
そこで役立つのが、転職エージェントの存在です。
私たち活学キャリアでは、実際にその企業で働いている人の声や、過去に転職した方の事例をもとに「本当に柔軟な働き方ができるのか」を見極めたうえでご提案しています。
もし「子育てと両立できる会社を知りたい」「Uターン転職の実例を聞きたい」といった不安がある方は、ぜひ無料カウンセリングでご相談ください。
現場で働くITコンサルのキャリア実例|リアルな声から見える道筋
ITコンサルタントという仕事は、キャリアの歩み方が一つに決まっているわけではありません。
営業やSIer、社内SEなど、さまざまなバックグラウンドを持つ人がコンサルタントとして活躍しています。
ここでは、実際にどんな道筋をたどったのかをいくつかの事例から見ていきましょう。
あなた自身のキャリアの参考になるヒントが見つかるはずです。
- 営業からITコンサルタントへキャリアチェンジする人は少なく
- SIer出身者は「技術的な裏付けを持ったコンサルタント」としてキャリアを築きやすい
- 社内SE出身者は「全社を俯瞰する力」を強みにしやすい
営業職から未経験でITコンサルへ
営業からITコンサルタントへキャリアチェンジする人は少なくありません。
なぜなら営業で培った「ヒアリング力」「提案力」「交渉力」は、ITコンサルタントに必要とされる資質と非常に近いからです。



お客様の要望をそのまま鵜呑みにせず、「本当に解決すべき課題は何か?」を引き出す力は、営業出身者が特に強みとする部分です。
実際に営業職からITコンサルタントになった方の多くは、次のようなステップでキャリアを広げています。
- 入社直後:プロジェクトマネージャーの補佐として、議事録作成やタスク管理を担当。営業経験で培った“段取り力”を活かしてスムーズにキャッチアップ。
- 2〜3年目:要件定義フェーズでお客様と直接対話し、システム要件を整理する役割へ。営業時代のヒアリング力がそのまま生き、信頼を得やすい。
- 4〜5年目:業務改善やDX推進など、より上流の案件にアサイン。お客様の経営課題を捉え、解決策を提示できるコンサルタントへとステップアップ。
このように、営業からスタートしても「人と向き合う力」を土台にすれば、ITの知識を後から身につけながら段階的にキャリアを広げることが可能です。
むしろ営業経験があることで、単なる“技術提案”ではなく“課題解決型の提案”ができる点は、他職種出身者にはない強みになります。
「未経験だから難しいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実際には営業出身者がITコンサルタントとして成功している事例は数多くあります。
大切なのは、最初から完璧なスキルを備えていることよりも、自分の強みをどうITの現場で活かすかを理解し、着実にステップアップしていくことです。
SIerからITコンサルへ転職し業務改善を担当
SIerからITコンサルへ転職したAさんの場合、最初は「システムを作る側」から「業務を改善する側」へのシフトに苦労しました。
しかし、開発経験があることで「現場のシステムがなぜ使いづらいのか」を具体的に説明でき、クライアントから信頼を得やすかったのが強みでした。
徐々に要件定義や業務フロー整理に関わるようになり、数年でプロジェクトリーダーを任される立場に成長しています。
- 1年目:要件定義の補助、既存システムの課題整理に参加。開発経験を活かし、技術面からクライアントの悩みを補足。
- 2〜3年目:業務改善プロジェクトの一部を担当。営業部門の業務フローを可視化し、二重入力やムダを洗い出す役割を担う。
- 5年目:小規模案件のプロジェクトリーダーに昇格。クライアントの部長クラスに対し、業務改善の根本的な提案を行う立場へ。
SIer出身者は「技術的な裏付けを持ったコンサルタント」としてキャリアを築きやすく、数年でリーダー職に進む例も少なくありません。



このように「作る」から「変える」へ視点を切り替えることが、ITコンサルタント転身成功のポイントといえます。
社内SEからIT戦略領域へキャリアチェンジ
社内SEからITコンサルに転職したBさんは、当初「自社の便利屋」から「他社の課題解決パートナー」への転身に不安がありました。
しかし、社内SEで全社的なシステムに触れてきた経験が評価され、早い段階で「全体最適」や「経営視点の提案」に携わるようになります。
5年目には経営層と直接議論し、IT戦略ロードマップを描くような上流工程を担うようになりました。
- 1年目:現場ヒアリングや課題整理を担当。利用者目線で不便さを拾い上げ、提案資料に反映。
- 2年目:部門横断のシステム統合を支援。複数ツールを整理し、統一基盤に移行するプロジェクトに参加。
- 4〜5年目:経営層との打ち合わせに参加し、DX推進計画や人材育成を含む「IT戦略ロードマップ」策定に関与。



社内SE出身者は「全社を俯瞰する力」を強みにしやすく、戦略的なITコンサルタント領域にスムーズに進めるケースがあります。
内部の便利屋から、企業の未来を描くブレーンへとキャリアが広がるのが特徴です。
ITコンサルタントの将来性は?今後も市場価値が上がり続ける理由
経済産業省の調査では、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると試算されています。
また、リソシアの分析では2040年に最大73.3万人の人材不足が見込まれており、長期的に需給ギャップが続くことが明らかです。
- DX・AI・クラウドと進化する技術のお陰でニーズが高い
- それに対してコンサルタント業界全体として、人手不足になっている
- 事業会社や社内コンサルへのキャリア展開も視野に入れると、さらに活躍の幅が広がる
DX・AI・クラウド…進化する技術とニーズの高まり
近年、企業が直面している最大のテーマのひとつが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
業務プロセスをデジタル化するだけでなく、データやAI、クラウドの技術を用いて新しい事業モデルを構築し、競争力を高めることが求められています。
ただし、これらの技術は単純に導入すれば成果が出るものではありません。
現場の業務フローや従業員のスキル、経営層の意思決定プロセスなど、さまざまな要素を踏まえて最適な形に落とし込む必要があります。
ここで活躍するのがITコンサルタントです。
ITコンサルタントは、経営層の戦略と現場のオペレーションをつなぐ「橋渡し役」として、最新技術をどうビジネスに活かすかを設計・推進していきます。
例えば、
- AIを導入して業務効率を改善するプロジェクトを企画する
- クラウドシステムを選定し、既存システムから移行するロードマップを描く
- データ分析基盤を整備して、経営層が意思決定に活用できる仕組みをつくる
といった取り組みは、単にITの知識だけではなく、経営の視点や業務プロセスの理解が不可欠です。
こうした複合的なスキルを持つ人材は希少であり、今後も需要は高まる一方です。
情報処理推進機構(IPA)では「DXを推進するための人材不足が深刻化している」と指摘しており、特に最新技術をビジネスに落とし込める人材の不足が顕著です。
事実、ITコンサルタントの報酬水準は一般的な職種よりも高めに設定されやすく、経験を積めば「平均以上」の待遇を得られる可能性が十分にあります。
dodaの調査によると、ITコンサルタントの平均年収は約598万円(20代:472万円/30代:660万円/40代:880万円)となっています。国税庁の統計を基にした分析でも平均年収は684.9万円と、日本全体の平均443万円を大きく上回っています。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
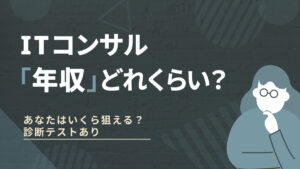
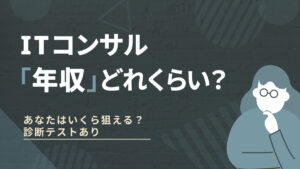
コンサル業界全体の人材不足と採用ニーズ
将来性を語るうえで欠かせないのが「人材不足」という背景です。
ITコンサルタントに限らず、コンサルティング業界全体で人材が足りていない状況が続いています。
背景には、次のような要因があります。
- DX推進を国や自治体も後押ししており、プロジェクトの数自体が急増している
- 少子高齢化による労働人口減少で、企業が効率化や自動化を急いでいる
- 技術が高度化・複雑化し、専門的な知見を持つ人材が育ちにくい
つまり「需要は増えるのに供給が追いつかない」状況が長期的に続いているのです。
このため、コンサルティングファームだけでなく、事業会社やSIer、スタートアップ企業まで、幅広い組織が「ITを理解し、ビジネスの言葉で語れる人材」を求めています。
Linux Foundation Japanが2025年に発表した調査では、日本企業の70%以上がクラウドやAI分野で人材不足を感じていると回答しました。
また、企業の94%が「既存人材のアップスキリング」を最優先課題と位置付けています。
新卒・未経験からの採用も積極的に行われていますし、他職種からのキャリアチェンジ事例も増えています。
また、採用後の教育体制が整備されている企業も多く、現場で経験を積みながらスキルアップできる環境が広がっているのも特徴です。
こうした背景は、ITコンサルタントを目指す人にとって大きな追い風といえるでしょう。
事業会社や社内コンサルへのキャリア展開も視野に入る
ITコンサルタントとしての経験は、将来的なキャリアの選択肢を大きく広げます。
第一線で活躍し続ける人もいれば、数年経験を積んだあとに事業会社へ移り、IT戦略部門や社内コンサルティング部門で働くケースも少なくありません。
企業にとっても、外部のコンサルティングファームで培った知見を社内で活かしてくれる人材は非常に貴重だからです。
さらに、経営戦略や新規事業の立ち上げに携わるチャンスも増えます。
- 社内のDX推進担当として、全社のシステム刷新をリードする
- マーケティングや営業部門と連携し、データドリブンな意思決定を支援する
- 新しいサービス開発に参画し、テクノロジーを活かしたビジネスモデルを構築する
こうしたキャリア展開は、コンサルタント時代に培った「課題解決力」「論理的思考力」「コミュニケーション力」があってこそ実現できるものです。
また、経験を積めば独立してフリーランスのITコンサルタントとして活動することも可能です。
企業からプロジェクト単位で依頼を受け、自分の専門領域を武器に働き方の自由度を高めていくケースも増えています。



このように、ITコンサルタントの経験は「今後も市場価値が上がり続ける」理由そのものといえるでしょう。
しかし、ITコンサルタントの業務領域は大変広いため、仕事内容も考え方は違えど、業界や領域は沢山あり、それぞれに特徴があります。
そのため、ITコンサルタントを目指すならば、まずはITコンサルタントの仕事内容を正しく理解しておきましょう。
ITコンサルタントの仕事内容に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
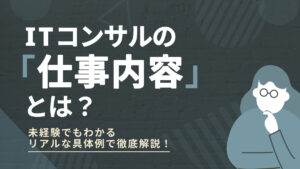
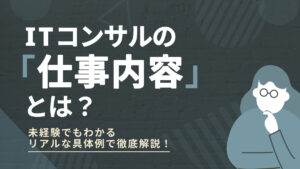
また、ITコンサルタントの将来性や業界選びなどで悩んでいる方は、ぜひ無料カウンセリングにお越しください。
IT業界専門のキャリアコンサルタントが、どこよりも詳しくITコンサルタント業界の実態について赤裸々にお話いたします。
自分だけのキャリアパスを描くために考えるべき3つの視点
ITコンサルタントのキャリアは一本道ではありません。
役職の階段をまっすぐ上る人もいれば、専門領域を深掘りしてエキスパートになる人、事業会社のDX部門へ舵を切る人、地方勤務やリモート勤務を軸に働き方を最適化する人もいます。
だからこそ大事なのは、「いま取れる選択肢」を増やすことよりも、「自分が本当に望むゴール」に向けて選択肢を絞っていくこと。



じゃあその視点をどうやって養っていったらいいの?
そんな疑問にお応えすべく、ここでは3つの視点を紹介します。
この内容を基に、ご自身の考えを掘り下げれば、ブレないキャリアの設計図を描けるようになります。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
- 自分が「何を大切にしたいか」から逆算する
- 身につけたいスキル・知見はどこで得られるかを見極める
- 将来的にどの働き方を望んでいるかを言語化する
自分が「何を大切にしたいか」から逆算する
キャリアパスを決めていくうえで、一番大切なことはスキルでも市場環境でもなく、あなたの価値観です。
ITコンサルタントは“正解がひとつではない”課題に向き合う仕事といえます。
だからこそ、日々の意思決定の軸=価値観が安定していないと、案件選び・会社選び・ロール選びのたびに迷い、消耗します。
まずは次の問いから始めてみましょう。
- 仕事で達成感を覚える瞬間は?(例:チームで何か一つのことを成し遂げた、経営の意思決定できた、数字が動いた)
- 譲れない条件は?(学習時間の確保、リモート比率、土日稼働の可否、転勤の頻度など)
- 「避けたいこと」は?(常時深夜対応、属人的な丸投げ、意図が見えない仕様変更 など)
- 誰に価値を届けたい?(現場ユーザー/経営層/社会課題の当事者 など)
このようにして、自分の本音をベースに価値観が見えたら、逆算して“設計”します。
価値観 → 叶えやすい役割 → 活躍しやすい環境 → 適した会社タイプ(大手系/SIer系コンサル/ベンチャー系 など
例えば「現場の人が楽になる瞬間が嬉しい」「プロダクトに長く伴走したい」なら、短期の提言よりも定着支援や運用設計が多い環境がフィットします。
逆に「新規事業や全社変革に関わりたい」なら、上流で意思決定に近い立場が取りやすい会社や案件を選ぶべきです。
ここまで自分の思考が整理できたら、それをベースにどんな企業を選んでいくか、方向性を決めていくと良いでしょう。
個人的なオススメのやり方は、まず「3年後に自分がどうなっていたいか?」を決めてから逆算していく方法です。
ここでは、未経験からITコンサルタントを目指す方で、よくあるパターンを例にご紹介していきます。
- 業務改善プロジェクトをリードする
- 週3日のリモート勤務で柔軟に働く
この例の場合だと、3年後には「リーダーシップ」と「働き方の自由度」の両方を実現している必要があります。
そこで、次に考えることとして、3年後のこの姿を実現する為に、まずは1年後の自分がどうなっている必要があるのかを考えます。
この例の場合ですと、未経験でいきなりリーダーを任されることは現実的ではありません。
だからこそ、1年後には“土台づくり”として「小規模案件で自走できるスキル」と「柔軟な働き方に慣れる経験」を積んでおく必要があるのです。
- 要件定義を自走できる
- Power BIなどのBIツールでレポート提案ができる
- 改善施策の定着設計に携わっている
- 週1〜2日のリモート勤務が許容される環境に慣れている
こうして見てみると、「3年後に必要な要素を小さく分解した姿」が1年後の状態になっているのがわかります。
リーダーシップに直結するのが“要件定義の自走”であり、BIツールや定着支援は“改善リードの武器”になります。
また、週3リモートで働く未来に向けて、1年目から週1〜2日のリモートに慣れておくと、キャリアの一貫性が保てるのです。
ここまで整理できたら、最後に、「この1年後の姿を実現できる会社」とはどんな会社なのかを考えます。
この例の場合、ポイントは3つあります。
- 小〜中規模の案件に関わる機会があること
→ 大規模案件では未経験の段階で裁量を持ちにくいので、まずは小さめの案件で経験を積める環境が理想です。 - データ活用や業務改善をテーマにしていること
→ BIツールや改善施策に触れられるかどうかは会社によって差が出ます。配属先の案件テーマを事前に確認できるかどうかが重要です。 - 柔軟な働き方が浸透していること
→ 1年目からフルリモートは難しくても、週1〜2日リモート勤務が可能な会社は増えています。また、これらの制度が実際に運用されているかをチェックしましょう。
このように、会社を選ぶときは「ネームバリュー」や「年収」だけで選んではいけません。
自分が3年後に立っていたい場所に“つながる1年後の経験”を積ませてくれる環境かどうか?
この視点で会社を見極めることが、ブレないキャリアパス設計の第一歩になるのです。
ところが、募集要項や会社紹介(社風)の内容と、実態が伴わないケースは珍しくありません。
これらを見抜くには、過去案件の稼働実績・ロール定義・決裁の速さ・権限移譲の範囲など「風土」を確かめるのが近道です。
これらの内容に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてチェックしていただき、“地雷回避”の術を養っておきましょう。
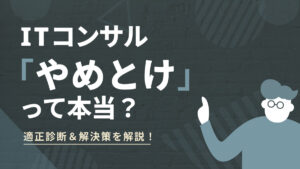
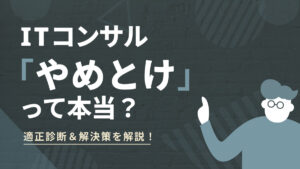
身につけたいスキル・知見はどこで得られるか
ここまで整理ができたら、次は「何を」「どこで」学ぶかを考えます。
おすすめは、スキルを4層で捉えることです。
①課題解決の基礎(課題の切り分け・論点整理・シンプルな資料化)
②業務ドメイン(会計/営業/人事など、どれか一つでも理解できる分野)
③テクノロジー(ExcelやBIツールの基本操作、クラウド基礎知識)
④推進力(会議で意見を整理する力、タスク管理、関係者との調整)
未経験の方は「全部やろう」と思うと挫折しがちです。
まずは①課題解決と④推進力の基礎を、社内の小さな仕事から体感していくのが現実的といえます。
たとえば:
- 現場で得る:上司の会議に同席し、議事録をまとめてみる。気づいた課題を一つ提案する。
- 社内プロジェクトで得る:研修や改善タスクに参加して、「メモ取り」や「簡単なタスク進行」から入る。
- 型で得る:先輩の資料をストックして、自分なりに真似してみる。
- 資格で得る:ITパスポートやAWS基礎など、学習の土台を固める。
学びを成果に変えるためには、0→1の小さな成功体験を早く積むことが大切です。
こうして小さなステップを積み上げていくと、「3年後の姿」で描いたキャリアパスに近づけます。
たとえば「週3日リモートで業務変革とデータ活用をリードする」なら、
→ 1年目は会議や要件定義に同席しつつ、自分でも小さな可視化を試す
→ 2年目以降はプロジェクトの一部を任され、調整役を経験する
といった流れです。



ここで意識したいのが「どんな会社なら、このスキルが身につきやすいか」という視点。
前の章では会社選びの重要性を整理しましたが、ここで紹介した内容を基にもう一歩踏み込むと、以下の観点で絞り込むことができます。
- 基礎スキルを鍛えられるか:資料や議事録の“型”が共有されているか
- 顧客との接点があるか:早い段階で会議やヒアリングに参加できるか
- 挑戦機会があるか:小さな提案でも試させてもらえる文化があるか
つまりキャリアパスを描く上で、「こんなことをやってみたい」→「その実現のためにこんな経験を積みたい」→「その経験ができる会社かどうか」といった流れで企業を絞っていく。
これが未経験から逆算してキャリアを築く、一番現実的なアプローチです。
将来的にどの働き方を望んでいるかを言語化する
「3年後にはどんな働き方をしていたいか?」を一度言葉にしてみましょう。
たとえば「リモート中心で柔軟に働きたい」「専門領域を持って長期で顧客を支援したい」など、自分なりのイメージで構いません。
そのうえで、面接の場では 遠慮せずに希望をぶつけてみること が大切です。
- 「このポジションはどのくらいリモートワークできますか?」
- 「未経験者が顧客との会議に参加できるタイミングは?」
こうした質問を投げると、会社の実態が垣間見えてきます。
ただし注意点として、表面上は良いことをうたっていても、実態が伴っていない会社も少なくありません。
だからこそ、情報収集は自分だけで抱え込まずに専門家を頼るのがおすすめです。
活学キャリアなら、
- ITコンサル未経験の人向けに特化した求人の紹介
- 各社の「実際の働き方」や「未経験者のキャッチアップ体制」についての内部情報
をもとに、一人ひとりに合ったキャリア選びをサポートしています。
ここまで整理してきた、「ご自身の理想や叶えたい未来」と「実際に選ぶ会社」を正しくマッチングさせるために、ぜひ気軽に無料カウンセリングへ相談にいらしてください。
ITコンサルタントのキャリアパスに関するよくある疑問
ここでは、ITコンサルタントのキャリアパスを考えるうえで、よくある疑問や質問をまとめています。
ぜひ確認して、ご自身のキャリアパスを考えるときの参考にしてみてください。
- 何年目くらいでマネージャーになれる?
- 途中で別業界や職種にキャリアチェンジできる?
- 転職せず社内でキャリアを築く道もある?
- 未経験で入った場合の最初の数年の過ごし方は?
- 「会話の現場に身を置く」とは?
何年目くらいでマネージャーになれる?
一般的には5〜7年目あたりでマネージャー昇格を狙えるケースが多いです。
ただし「どの規模の会社にいるか」「どんなプロジェクトを経験したか」に左右されます。
未経験入社でも、早ければ30歳前後でマネージャーになる人もいますが、まずは 小規模でもチームをリードする経験を積むこと が近道です。
途中で別業界や職種にキャリアチェンジできる?
可能です。
実際に「ITコンサル→事業会社のDX部門」「ITコンサル→プロダクトマネージャー」「ITコンサル→フリーランス」といった動きは珍しくありません。
ポイントは「どんな業務ドメインや技術を経験したか」。
転職市場では“成果が見える武器”を持っているかが評価されます。
転職せず社内でキャリアを築く道もある?
もちろんあります。
大手では 専門領域を深めてシニアスペシャリストになる道 と、 ラインマネジメントで組織を率いる道 の両方が用意されています。
未経験者が最初から選ぶ必要はなく、まずは複数の案件に関わって「自分は人を動かすのが得意か、技術を深めるのが得意か」を見極めていけば大丈夫です。
未経験で入った場合の最初の数年の過ごし方は?
1〜2年目は 現場でのインプット期間。
議事録、資料作成、簡単な可視化やテストなど“小さい成功体験”を積むのが中心です。
最初のうちは事務作業が多くて面倒だなと思うこともあるかもしれません。
しかしその小さな積み重ねが、信頼へと繋がっていくものです。
上長からの信頼が増してくれば、やがて「部分的な要件定義」や「小規模PJのリード」などを任され、徐々にキャリアの選択肢が広がっていきます。
大事なのは “型を身につける”ことと、“会話の現場に身を置く”こと。
「型を身につける」とは?
ITコンサルの仕事には「よく使う型(テンプレートや進め方のパターン)」があります。
たとえば…
- 会議の議事録を書くときのフォーマット
- 要件定義を整理するチェックリスト
- 提案資料の基本構成(現状→課題→打ち手→効果)
こうした“型”を早めに吸収して、自分で再現できるようになると、未経験でも一気に戦力になれます。
「会話の現場に身を置く」とは?
資料作りだけでなく、お客様や上司が実際に議論している場に立ち会うことです。
- 要件ヒアリングの打ち合わせに同席する
- プロジェクト会議の議事録を取る
- 先輩の質問の仕方を横で聞いて学ぶ
こういう場に出るほど、「何を大事にしているのか」「どんな言葉で合意形成しているのか」が肌感覚で分かってきます。
この基盤が後のキャリアを左右します。
まとめ|「自分の描きたいキャリア」を主軸に選ぼう
ITコンサルタントは、案件の内容や会社の方針によってキャリアの形が大きく変わります。
だからこそ大切なのは、「自分がどんな働き方をしたいか」「3年後どんな姿になっていたいか」を主軸に置いて、企業や案件を選んでいくことです。
年収や役職のスピードだけを追いかけると、思っていた成長や働き方とズレてしまうこともあります。
逆に「自分はこんな価値を提供したい」「こういう生活スタイルを目指したい」といった軸があれば、どんな環境を選ぶかの判断基準がクリアになります。
そのうえで、
- スキルを伸ばせる場(型を学べる・会話の現場に立てる)
- 自分の強みを活かしやすい場(営業経験・エンジニア経験など)
- 将来の働き方につながる制度やカルチャー(リモート可、社内異動の柔軟さなど)
こうした条件を満たす会社を選べば、未経験からでも「理想のキャリアパス」を描きやすくなります。
不安があるなら、まずは一人で抱え込まずにプロに相談するのも手です。
活学キャリアでは、未経験の方がキャリアの軸を固めて企業選びをするサポートをしています。
あなたの「描きたいキャリア」を一緒に言語化して、第一歩を踏み出しましょう!
アドバイザーに相談してみる

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
無料相談してみる

 一人で悩まず、
一人で悩まず、
まずは話してみませんか?