カテゴリー
社内SEはやめとけって本当?後悔しやすい理由と回避のポイントを解説!
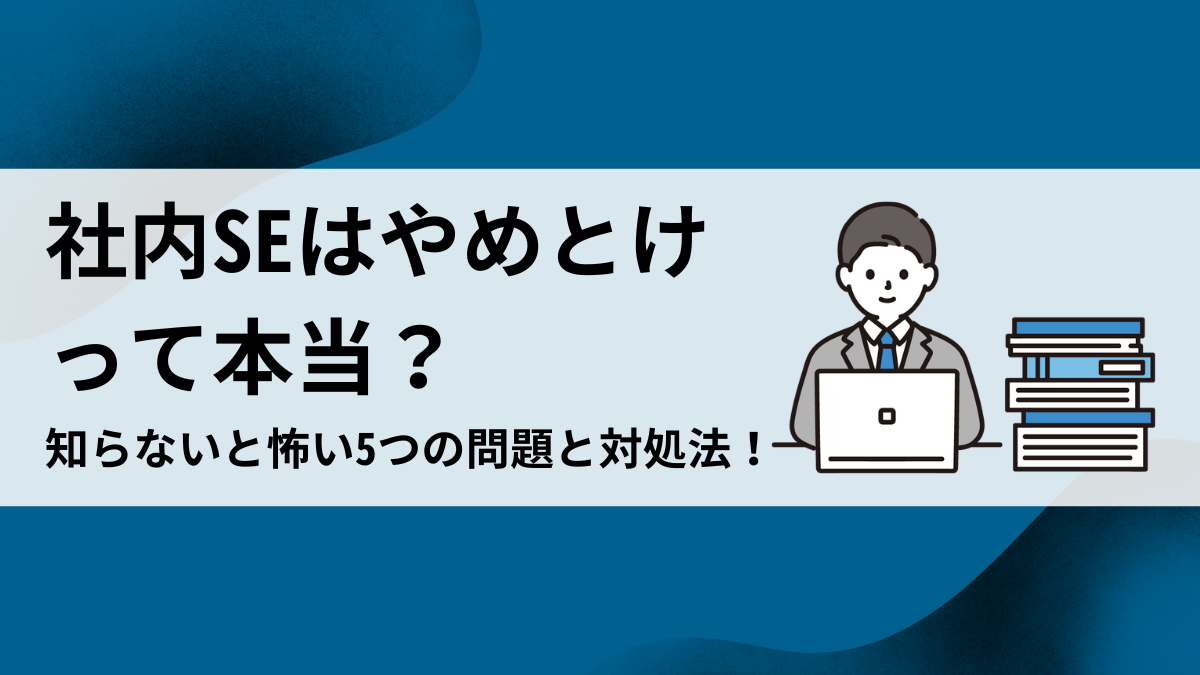
こんにちは、活学キャリアです!

「社内SEはやめといたほうがいいよ」
せっかく安定してそうな社内SEに興味を持っても、そんなネガティブな声を見かけると、不安になりますよね。
実は、社内SEという働き方には“向いている人”と“後悔しやすい人”がはっきり分かれる傾向があります。
この記事では後悔しやすいポイントと、回避するための判断基準を紹介します。
- 社内SEが「やめとけ」と言われる代表的な理由
- 実際に社内SEになって後悔した人のリアルな声
- 未経験で社内SEを選ぶ際の注意点
- 社内SEで後悔しないための具体的な対策
- 自分が社内SEに向いているかを見極める判断軸
社内SEはやめとけと言われる理由とは?
ここでは、実際に「やめとけばよかった」と感じてしまう人が多い5つの理由を紹介します。
読みながら、「自分に当てはまりそうかどうか?」をイメージしてみてください。
- 専門性が身につきにくくキャリアが限定される
- 雑務や非IT業務を押し付けられることもある
- 社内調整がメインでITスキルが伸びない
- 社員のクレーム処理など精神的負担が大きい
- 昇給・昇格が見えにくくモチベーションが続かない
専門性が身につきにくくキャリアが限定される
やめとけと言われる一番の要因が、“成長しにくさ”です。
社内SEの仕事は、社内のIT環境を整えたり、システムの保守・運用をしたりと、かなり幅広い業務に関わります。
ただしその反面、「ひとつの分野を深く極める」といった機会が少なく、キャリアの専門性を育てにくい一面もあるんです。
「もっとインフラを極めたい」「セキュリティのプロになりたい」と考えていた人にとっては、
中途半端に広く浅い経験だけが残ってしまうことも…。
将来的にスペシャリストを目指すなら、「社内SEでは物足りないかも」と感じてしまうケースがあります。
雑務や非IT業務を押し付けられることもある
「ITに詳しいからちょっとお願い!」
便利屋”扱いされやすい社内SEでは、気づいたらプリンタの設定やパソコンの初期化、名簿の印刷まで頼まれていた…なんて経験、社内SEではよくある話です。
本来の仕事に集中したくても、周囲から“便利屋”のように扱われてしまうと、やりがいを見失ってしまうことも。
実際、「こんな仕事がしたかったわけじゃない…」とモヤモヤを抱える人は少なくありません。
社内調整がメインでITスキルが伸びない
「もっと技術を磨いていきたい」
そんな思いで社内SEになったものの、実際にやってみると“調整業務ばかり”で驚く人も多いです。
部署同士の橋渡し、ベンダーとの折衝、業務改善の提案…
意外とコードを書く機会が少なく、「思っていたエンジニア像と違う」と感じることもあるかもしれません。
自分の手を動かしてスキルアップしていきたいタイプの方は、ギャップを感じやすいポイントです。
社員のクレーム処理など精神的負担が大きい
社内SEは“社外のお客様”ではなく、“社内の従業員”が相手。
つまり、トラブルやクレームを直接ぶつけられる機会も多くなります。
「なんで繋がらないの!?」
「いつ直るの!?」
感情的な声を受け止める場面もあり、人によってはメンタル的にしんどくなってしまうことも…。
「人のサポートをする仕事が好き」と思っていても、実際に現場に入ると想像以上にストレスを感じてしまうケースは珍しくありません。
昇給・昇格が見えにくくモチベーションが続かない
「がんばって改善提案もしたのに、まったく評価されない…」
社内SEは“会社の売上に直結しにくい職種”だからこそ、成果が目に見えづらく、評価や昇進につながりにくい傾向があります。
その結果、
「どれだけ頑張っても給料が上がらない」
「成長実感がない」
と感じてしまい、モチベーションが続かなくなる人も…。
やりがいが感じられないまま働き続けるのは、誰にとってもつらいですよね。
【体験談】社内SEになって「やめとけばよかった」と思うリアルな声
ここでは、実際に社内SEとして働いた方のリアルな声をもとに、どんなギャップや後悔があったのかを紹介します。
理想と現実のギャップに悩む人は、意外と少なくありません。
- 「エンジニアとして成長できない環境だった」
- 「思っていた仕事内容と全然違った」
- 「現場の温度差や孤独感がつらかった」
「エンジニアとして成長できない環境だった」
案件ベースでどんどん技術に触れていけると思っていたのですが、実際は社内のパソコンやネットワークの保守が中心でした。
開発経験もなく、気づけば“いつでも誰でもできる仕事”ばかりで、スキルが身につかないまま3年が過ぎていました。
このように、
「エンジニアとしての価値を高めたい」
「技術職としてレベルアップしたい」
と思っていた人にとって、社内SEは物足りなく感じることがあります。
特に、“手を動かして学ぶタイプ”の人にとっては、「このままでいいのかな…」と焦りを感じやすいポジションです。
「思っていた仕事内容と全然違った」
社内SE=内製開発や新システムの導入に関わる仕事だと思っていました。でも実際は、業務システムのベンダーとの連絡や、トラブル対応がほとんど。
期待していた“モノづくり”の楽しさがなくて、かなりギャップを感じました。
求人票だけではイメージしにくいのが、社内SEの難しいところ。
会社によっては「IT事務」に近い業務が中心だったり、開発業務はすべて外注していたりすることも珍しくありません。
思い描いていた“エンジニアらしい働き方”との違いに、戸惑う方も多いです。
「現場の温度差や孤独感がつらかった」
技術職の人間が自分だけで、周りは営業や事務の人ばかり。
開発の相談もできず、何かを提案しても「わからないから任せるよ」と言われるだけで、評価もフィードバックもないまま仕事が進んでいきました。
「本当にこれで良かったのかな…」と、ずっとモヤモヤしていました。
社内SEは「一人情シス」になりやすい職種でもあります。
周囲に同じ目線で話せる人がいないと、技術の話が通じない孤独感や、評価されない虚無感に悩むことも。
「誰かと一緒に成長したい」
「チームでやりたい」
という方には、環境によっては厳しく感じられるかもしれません。
未経験から社内SEを目指す際に後悔しないための注意点
社内SEは他のIT職と比べて「未経験でも挑戦しやすい」と言われることがあります。
しかし、その分リスクやギャップも大きく、結果として「やめとけばよかった…」と感じてしまうケースも。
ここでは、新卒や未経験の方が特に注意しておきたいポイントを3つに絞って解説します。
- 育成前提でない企業に配属されるリスク
- 幅広すぎる業務に対応しきれないこともある
- ITキャリアの第一歩としては遠回りになる場合も
育成前提でない企業に配属されるリスク
「研修があるから安心」と思って入社してみたら、実際は「教える余裕なんてない現場」だった――。
これは、未経験の社内SEにありがちな落とし穴です。
特に中小企業やベンチャー系の場合、「人手不足だからとりあえず入れて、あとは現場で覚えて」スタイルのところも珍しくありません。
先輩SEがいない、教育マニュアルが整っていない…となると、右も左もわからないまま、いきなりトラブル対応やシステム操作を任されてしまうことも。
「育ててもらえる前提」で入ると、ギャップに苦しむ可能性があります。
幅広すぎる業務に対応しきれないこともある
社内SEは「守備範囲が広い仕事」です。
ネットワークやセキュリティの管理、業務フローの改善、PCの設定やキッティングまで、担当する業務は多岐にわたります。
特に未経験の方は、何が自分の仕事で、何が他部署の仕事なのかの線引きもあいまいになりがち。
気づけば「全部自分でやるしかない」状況になっていた…なんて話もよく聞きます。
あれもこれもと振られてパンクしてしまう前に、「業務内容の幅広さ」と「サポート体制」のバランスは、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
ITキャリアの第一歩としては遠回りになる場合も
「せっかくIT業界に入るなら、キャリアアップを見据えたい」と考える方にとっては、社内SEが“遠回り”になることもあります。
なぜなら、社内SEの多くは“運用保守”が中心で、開発や設計といった「技術を積み上げていく仕事」が少ないからです。
もちろん、社内SEでも学べることはありますが、将来的にフルスタックエンジニアやクラウドエンジニアなどを目指す場合は、「他の職種の方がスキルが伸びやすい」と感じることも。
最初のキャリア選択だからこそ、
「どんな働き方をしたいか」
「どんなスキルを身につけたいか」
を明確にしておくことが大切です。
それでも社内SEが人気を集める理由
ここまで読むと、「やっぱり社内SEはやめといたほうがいいのかも…」と感じた方もいるかもしれません。
ですが実は、社内SEという働き方は多くの人にとって「ちょうどいいバランスの職種」として人気が高まっているんです。
なぜ「やめとけ」と言われながらも選ばれるのかを解説します。
- ワークライフバランスが取りやすい
- 客先常駐や納期ストレスがない
- プロジェクト全体に関わることができる
- 社員の声を直接聞いて仕事に活かせる
実際に社内SEは人気が高く、非常に競争率の高い職種です。求人倍率や転職成功率を高める方法はこちらを参照してください。
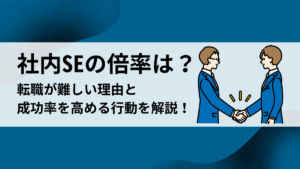
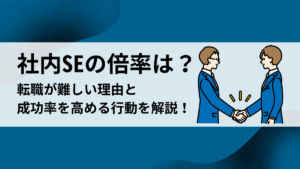
ワークライフバランスが取りやすい
まず、社内SEの大きな魅力は「働きやすさ」。
クライアント対応がないため、納期に追われるプレッシャーが少なく、突発的な残業や休日対応も比較的発生しにくい環境です。
そのため「家族との時間を大切にしたい」「自分のペースで働きたい」という方にとっては、かなり好条件。
実際に、「前職よりも心に余裕ができた」「子育てと両立できている」という声も多く聞かれます。
客先常駐や納期ストレスがない
SIerやSESと違い、社内SEは“社内だけ”が担当範囲です。
客先への常駐がないため、慣れない環境や人間関係に振り回される心配も少なくなります。
また、社内でのやり取りが中心になるため、過度な納期プレッシャーや理不尽な要求が飛んでくることもほぼありません。
「もっと落ち着いて働きたい」
「精神的なストレスを減らしたい」
という方にとっては、大きなメリットになるでしょう。
プロジェクト全体に関わることができる
社内SEは、ただ与えられた作業をこなすだけではなく、企画から運用まで一貫してプロジェクトに関われるケースが多いです。
たとえば、「この業務フロー、非効率だから自動化したらどうかな?」という提案から、実際にツールを導入し、社内に浸透させるところまで主導できることも。
「自分の提案が会社全体に影響を与える」そんな手応えを感じられるのは、社内SEならではのやりがいと言えます。
社員の声を直接聞いて仕事に活かせる
ユーザーである社員の声をダイレクトに聞けるのも、社内SEの特徴です。
たとえば、
「あのシステム、使いやすくなって助かったよ」
「業務がすごく効率化された!」
そんな感謝の声を直接もらえると、「やってよかったな」と素直に思えます。
クライアント相手の開発とは違い、ユーザーと距離が近いからこそ、フィードバックの実感が強く、それがモチベーションにつながります。
社内SEで後悔しないための5つの対策
ここまで読んで「やっぱり社内SE、向いてないかも…」と感じた方もいるかもしれません。ですが安心してください。
社内SEで後悔するかどうかは、入社前の準備や働き方次第で大きく変わります。
逆にいえば、ポイントを押さえておけば、「社内SEにしてよかった」と思えるキャリアを築くことも可能です。
ここでは、後悔しないために今からできる対策を5つに絞って紹介します。
- 配属先の業務範囲・役割を事前に把握する
- 自社開発比率やIT戦略の有無を確認する
- 将来的なキャリアステップを想定しておく
- ITスキルを補完できる副業・資格学習を活用する
- 転職エージェントに社内SEの実態を相談する
配属先の業務範囲・役割を事前に把握する
同じ“社内SE”でも、実は会社によってやっていることがまったく違います。
たとえば、ある企業ではインフラ整備が中心、別の企業では業務改善の提案がメインだったりもします。
なかにはIT事務のような業務だけを任されるケースも。
入社後のギャップを防ぐには、面接や企業HPで「具体的な業務内容」と「期待される役割」を確認しておくことが重要です。
自社開発比率やIT戦略の有無を確認する



「開発に関われると思っていたのに、すべて外注だった…」
そんな声も実際によく聞かれます。
もし「手を動かしてスキルを伸ばしたい」と思っているなら、内製化(自社開発)している割合や、IT戦略にどれだけ力を入れているかをチェックしておきましょう。
「情シスはコストセンター」という考え方が根強い会社では、なかなか新しいことに挑戦できない場合もあります。
※情シスはコストセンター・・・頑張っても評価されづらいポジションという意味
将来的なキャリアステップを想定しておく
社内SEとして経験を積んだ後、どんなキャリアを歩みたいのか――。
これを事前に考えておくことが、後悔しないための鍵です。
たとえば、「まずは社内SEで全体像を掴み、その後クラウドエンジニアを目指す」など、ゴールを見据えた選択をしておくと、今の環境の活かし方が変わってきます。
「何となく入ったけど将来が見えない」という状態にならないよう、キャリアプランは早めに描いておきましょう。
社内seのキャリアパスについてはこちらで詳しく解説しています。
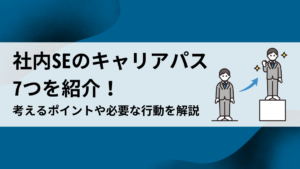
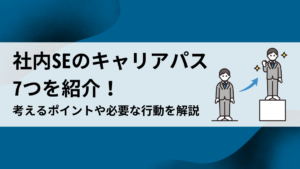
ITスキルを補完できる副業・資格学習を活用する
もし今の業務が“スキルになりにくい”と感じたとしても、学ぶ手段は会社の外にもあります。
たとえば、副業で小さな開発案件に関わってみたり、CCNAや基本情報技術者などの資格取得を目指すのも有効です。
最近では、スキルの証明ができるオンライン講座やポートフォリオ作成支援も充実しています。
「会社では得られない学びを、自分で取りに行く」という姿勢が、将来の選択肢を大きく広げてくれます。
転職エージェントに社内SEの実態を相談する
もし今「社内SEとして転職しようか迷っている」段階であれば、プロに相談するのが一番早くて確実です。
転職エージェントは、企業の内情や現場の雰囲気、育成体制の有無なども把握しています。
自分では見えない「働いてみないとわからない部分」も事前に知ることができるため、ミスマッチを防ぐうえでも非常に頼りになります。
「まだ転職するか迷っている段階でも大丈夫?」と不安な方も、まずは相談してみるだけでも気持ちがスッと軽くなるはずです。
活学キャリアなら、未経験からでもIT業界に挑戦できます。
・直感的に理解できるカリキュラム
・講師にすぐ質問できる環境
・ブラック企業の扱いはゼロ
「このままでいいのかな…」と感じた今が、動き出すタイミングです。
社内SEで失敗しやすいタイプとは?後悔しないための見極め方
社内SEに向いているかどうか――
これは、働いてみるまで分からない…と思われがちですが、実は「後悔しやすい人・しにくい人」には、ある程度の共通点があります。
もし「自分に合っていない働き方」だった場合、スキルもキャリアも思ったように伸びず、「やめとけばよかった…」と後悔することに。
ここでは、事前にチェックしておきたいポイントを3つずつ紹介します。
- こんなタイプは注意!社内SEに向かない傾向3つ
- 「安心して働ける!社内SEに合う人の特徴3選」
社内SEに向いている人、向いていない人についてはこちらでさらに詳しく解説しています。
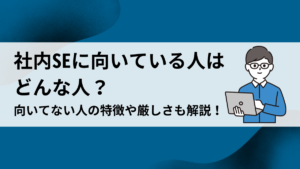
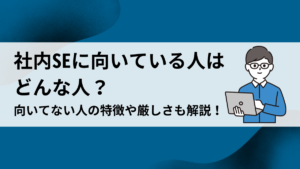
こんなタイプは注意!社内SEに向かない傾向3つ
① 自主的に動ける・改善提案が好きな人
社内SEは、「言われたことをやるだけ」ではなく、自分で考えて行動できる人が強いです。
たとえば、「この業務フロー、もっと効率化できそうだな」と気づき、提案・実行までできる人は大きなやりがいを感じやすく、周囲からも信頼されます。
② 技術だけでなく、調整やコミュニケーションが苦でない人
「社内の人と話すのは平気」
「調整も仕事のうち」
と思えるタイプの人は、社内SEにフィットしやすいです。
むしろ、コードを書くより人と話すほうが好きなタイプは、ストレスなく働ける職場になるかもしれません。
③ 安定性や働きやすさを重視する人
「無理な納期や深夜残業がない働き方がいい」
「長く続けられる仕事がしたい」
と考える人にとって、社内SEの環境は魅力的です。
ワークライフバランスを大切にしたい人には、社内seは今後の将来性も高くむしろピッタリの選択肢とも言えます。将来性についてはこちらをご覧ください。


「安心して働ける!社内SEに合う人の特徴3選」
① 成長スピードやスキルの“見える化”を重視する人
「どんどん技術力を上げたい」
「スキルを数字で証明したい」
と考えている方にとっては、社内SEの環境はやや物足りなく感じやすいです。
外部からの評価が可視化されにくく、「自分は本当に成長しているのか?」と不安になることも。
② 同僚との技術的な会話を求める人
同じレベルのエンジニア仲間と切磋琢磨したい」と思っている方は要注意です。
社内SEは一人情シスや少人数体制になりがちで、技術的な相談相手が社内にいないという状況になることも珍しくありません。
③ 自分の仕事が“会社の成果に直結する”実感が欲しい人
売上や数字に貢献することにやりがいを感じる人にとっては、社内SEの「縁の下の力持ち」ポジションは、少し歯がゆく感じるかもしれません。
がんばっても社内評価に反映されにくいと感じる場面が続くと、モチベーションが下がってしまう傾向があります。
社内SEになって後悔してしまった本音をこちらの記事でまとめています。
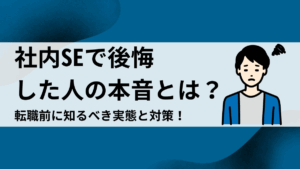
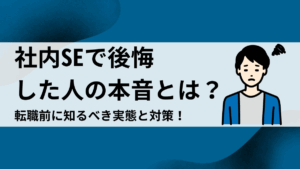
まとめ:「社内SEはやめとけ」はケース次第。後悔を防ぐ選び方とは?
ここまで、社内SEにまつわる“やめとけ”の理由や、後悔してしまう人の共通点について紹介してきました。
“やめとけ”と一括りにするのではなく、自分に合う環境を見極められるかが重要です。
「スキルが伸びにくい」
「評価されづらい」
「雑務に追われる」
など、実際に後悔する人がいるのも事実です。
でも一方で、
「ワークライフバランスが取りやすい」
「自分の提案で職場を良くできる」
「無理なく長く働ける」
といった魅力を感じて、社内SEを選ぶ人がいるのもまた事実です。
つまり――
向いている人にとっては、社内SEは“勝ち組キャリア”にもなり得る
ということ。
大切なのは、「誰かがやめとけと言っていたから」ではなく、
“自分にとってその選択が合っているかどうか”を見極めることです。
そして、もし今「このままでいいのかな」「自分に合った環境で働きたい」と感じているなら、それは立ち止まってキャリアを見直すチャンスかもしれません。
そんなときは、一人で悩まずにプロに相談してみるのも選択肢のひとつです。
実際に、未経験からIT業界を目指す人に選ばれているのが活学キャリア。
アニメーション教材で基礎から学べて、現場を知る講師にすぐ質問できる環境が整っています。
転職サポートも一人ひとりに合わせて行い、ブラック企業は一切紹介しない方針なのも安心ポイントです。
「このまま社内SEを続けていいのか迷っている」
「スキルを身につけて、もっと自信を持って働きたい」
そう感じているなら、あなたの悩みに寄り添いながら、未来の選択肢を一緒に考えてくれます。

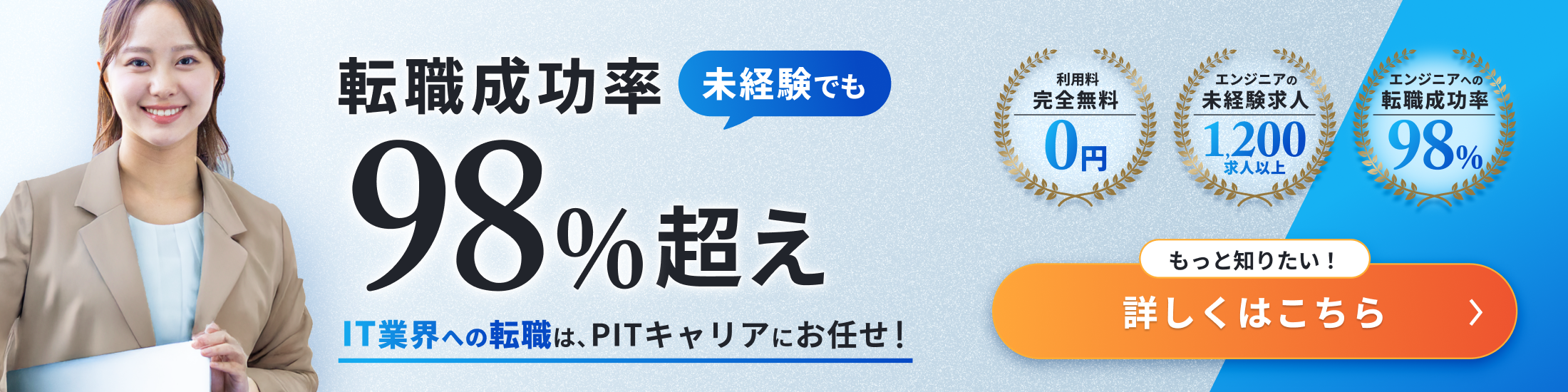
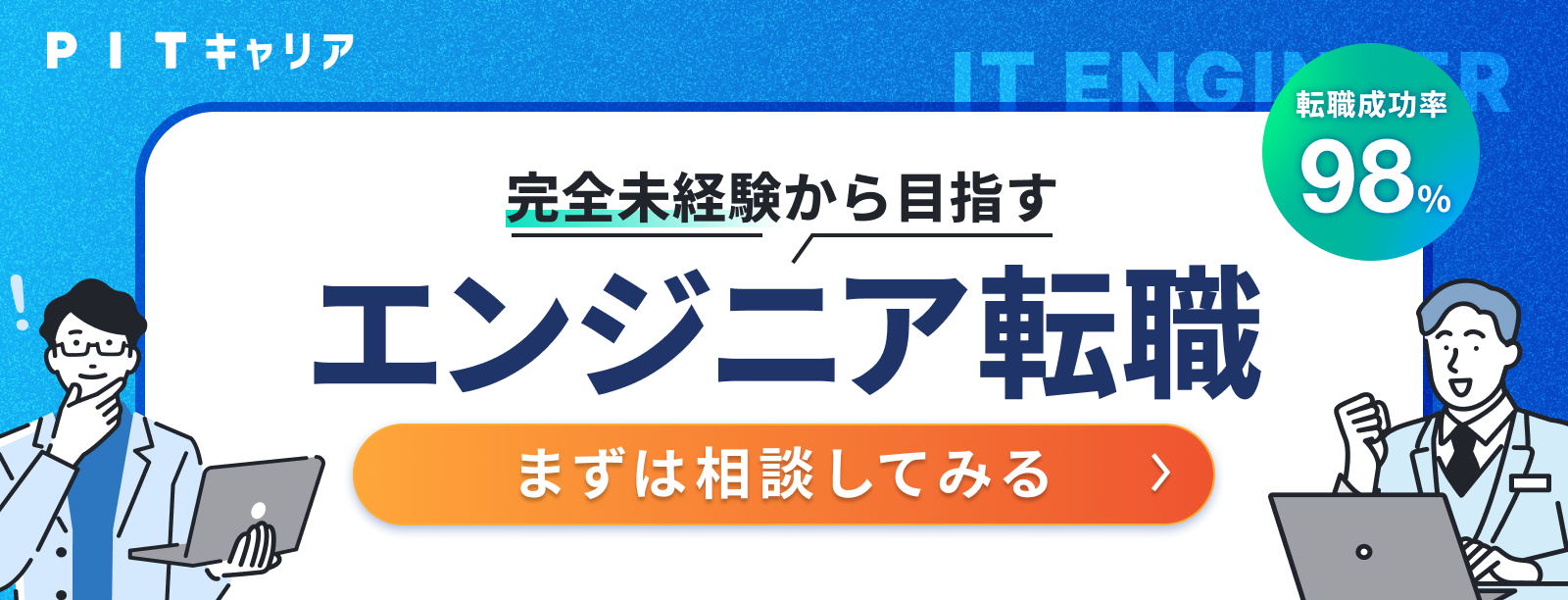
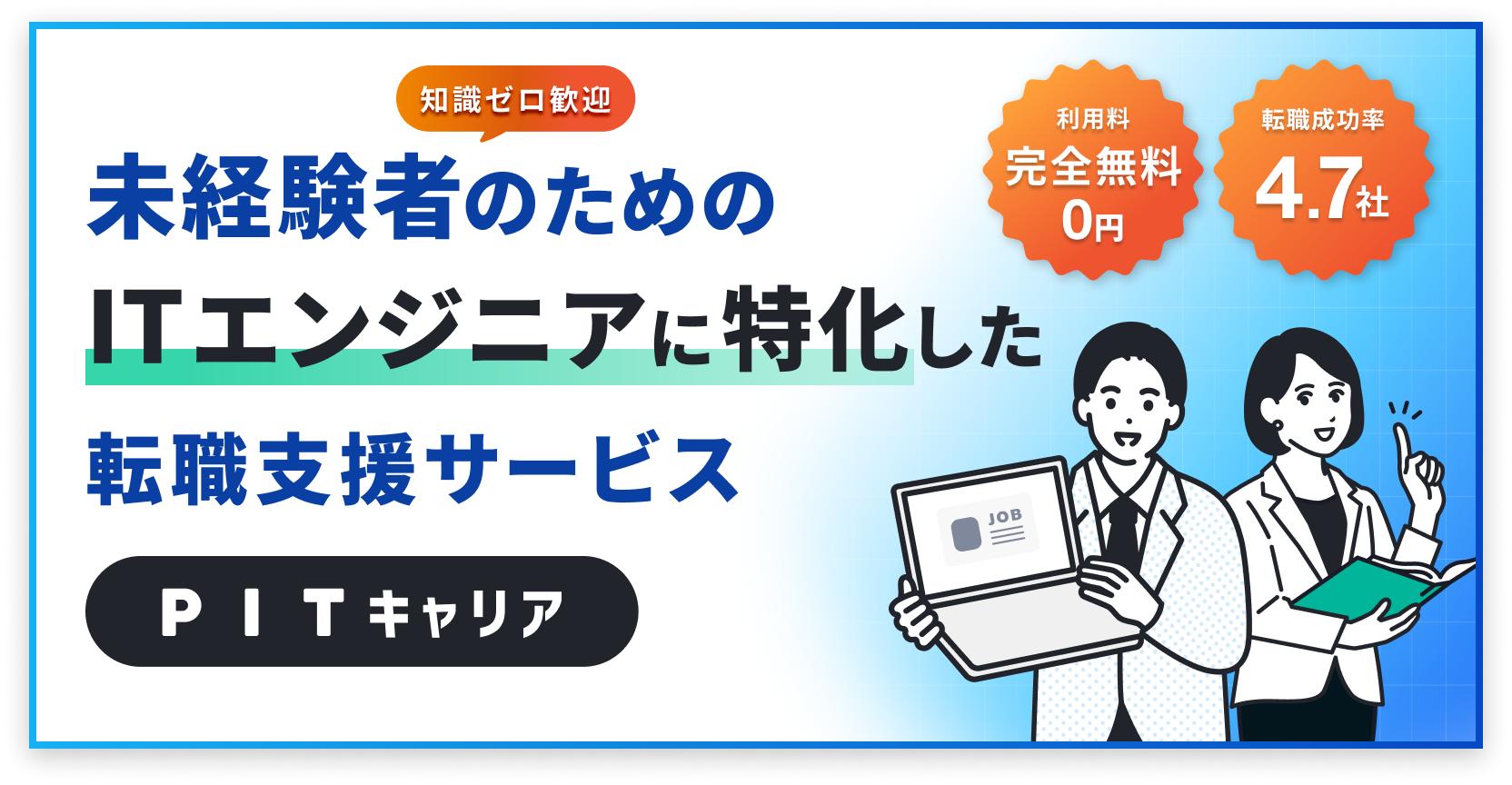
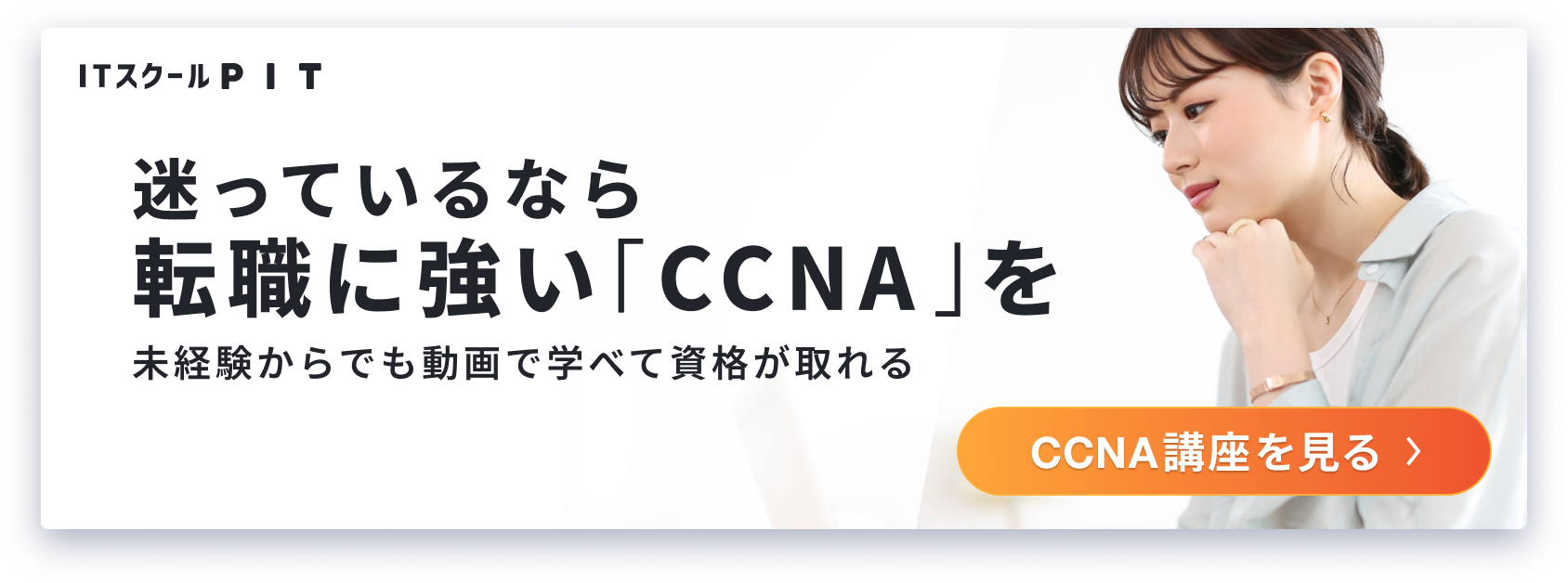




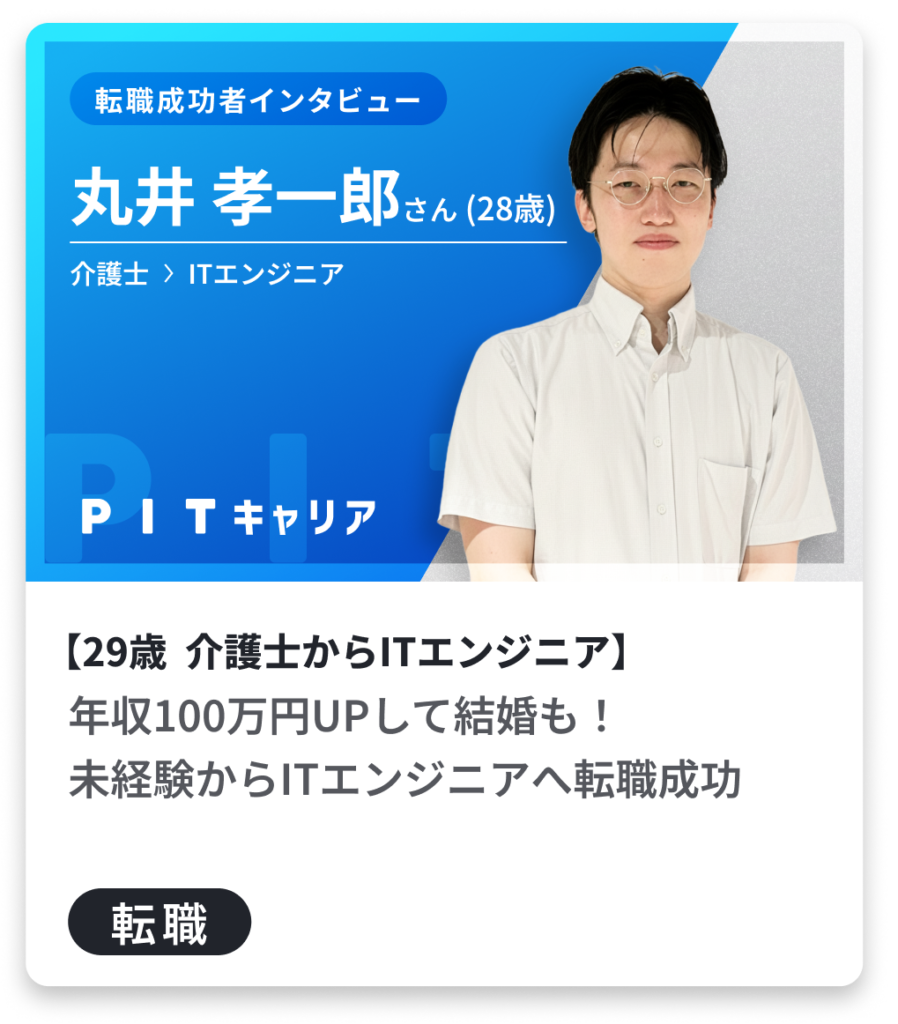
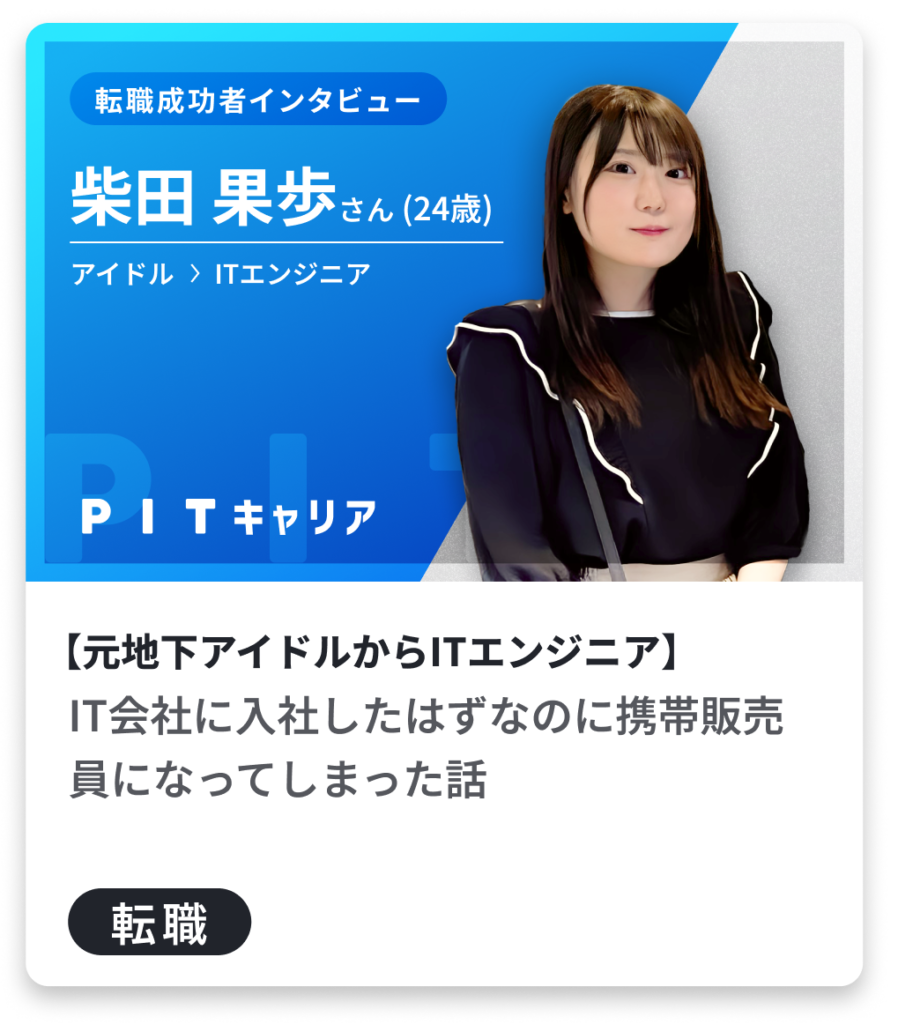
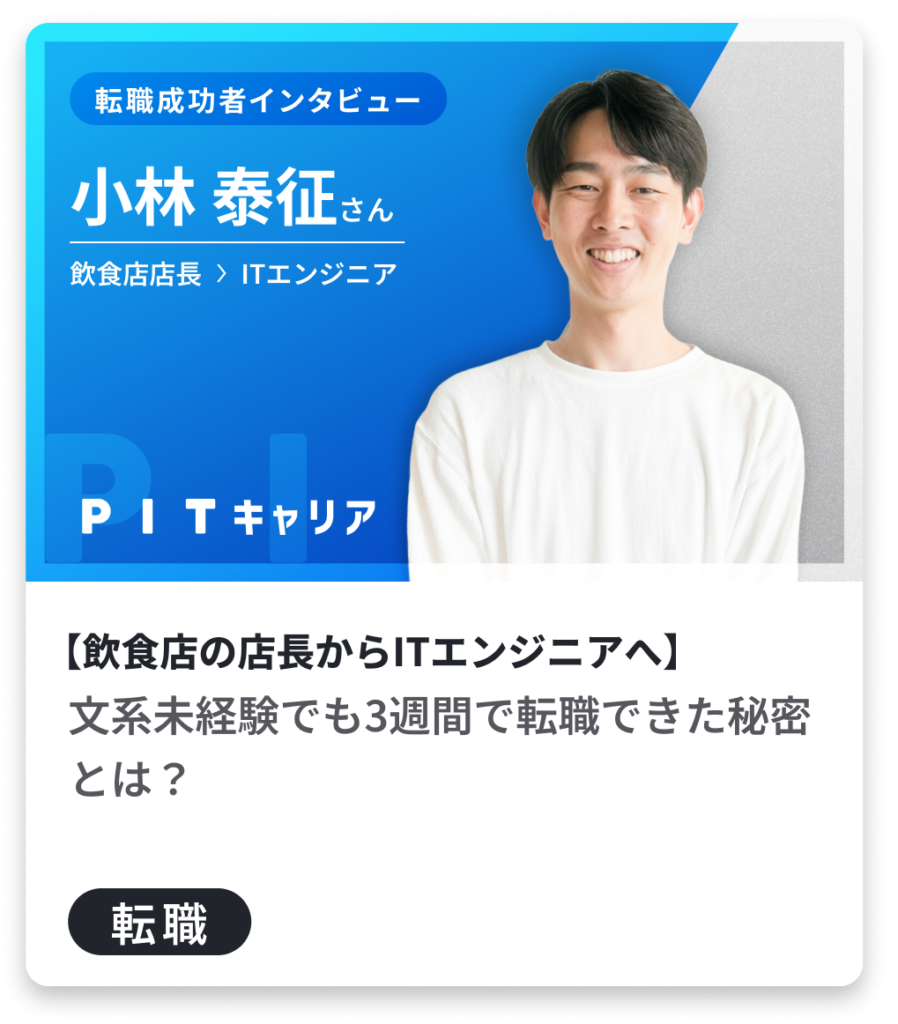

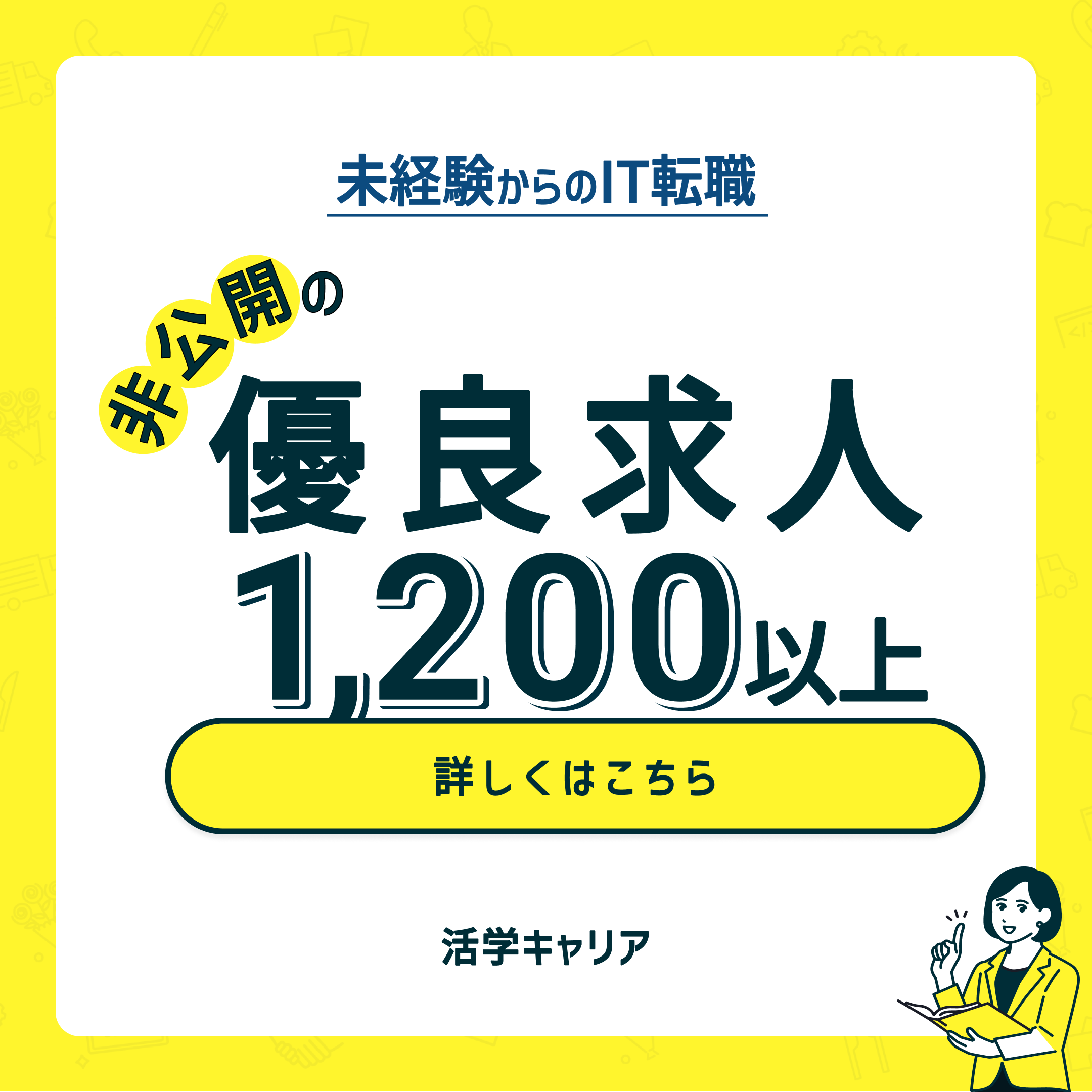

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
