カテゴリー
SESインフラエンジニアの全貌!仕事内容からキャリア戦略の秘訣まで徹底解説


「SESでインフラエンジニアって大丈夫なの?」



「インフラエンジニアってなに?」
と悩む方も多いのではないでしょうか。
現場の仕事内容やスキルの活かし方が分かりづらいですよね。
この記事では、SESインフラエンジニアの具体的な業務内容やキャリアアップのコツをわかりやすく解説していきます。


SESとインフラエンジニアについて基本概要を解説
SESとインフラエンジニア、SESインフラエンジニアについてそれぞれ、どういったものなのかを解説していきます。
SESとは
SES(システムエンジニアリングサービス)は、企業の依頼に応じてエンジニアがクライアント先に派遣され、システム開発やインフラ運用を行う形態です。
SESは、特定のプロジェクトや期間に従事するため、クライアント先での対応力や柔軟なスキルが求められます。
インフラエンジニアとは
インフラエンジニアは、ITシステムの基盤となるネットワークやサーバー、データベースなどの構築、運用、保守を担当します。
企業のIT基盤を支えるため、安定性と効率性が求められ、システム障害時には迅速に対応する力も重要です。
クラウド技術の普及に伴い、最近ではクラウド環境のインフラ整備に関わるケースも増えています。
SESインフラエンジニアとは
SESインフラエンジニアは、クライアント企業へ常駐し、ITインフラの構築や保守を担当します。
上流工程になると、システムやネットワークの設計や企画、要件定義など、プロジェクトの初期段階で行われる重要な基盤を作る役割を担います。
SESインフラエンジニアの仕事内容
SESインフラエンジニアは、クライアント先でシステムの基盤部分であるネットワークやサーバーの運用を行います。
具体的には、ネットワークの設計や構築、サーバーの管理、障害発生時のトラブルシューティングなどです。
また、最近ではクラウド環境の整備やセキュリティ対策にも対応することが増えており、技術の幅広さが求められます。
SESインフラエンジニアとして働くメリット
SESインフラエンジニアは、多様なプロジェクトや企業で働くことで、幅広いスキルや経験を積むことができます。
それぞれを詳しく解説していきます。
幅広い業界での経験を積むことができる
SESインフラエンジニアは、クライアント先ごとに異なる業界や業務形態で働く機会があります。
金融、製造、医療など多様な分野でのシステム構築や運用を経験することで、幅広い業界知識を得られると同時に、業界ごとのインフラニーズや課題に対応できるスキルが養われます。
チームマネジメントやプロジェクト管理のスキルが身につく
SESエンジニアは、プロジェクトの規模に応じてリーダーシップを発揮する場面も多く、チームメンバーの指導やプロジェクトの進捗管理など、マネジメントスキルを自然と身につけられます。
これにより、将来的にプロジェクトマネージャーやリーダーとしてのキャリアアップも視野に入れることができます。
多様な企業文化に触れ、柔軟な対応力が身につく
SESインフラエンジニアは、さまざまなクライアント企業の文化や業務フローに順応する必要があります。
そのため、異なる業務環境に迅速に適応する柔軟な対応力が自然と培われ、どのような環境でもスムーズに業務を進める能力が身につきます。
また、プロジェクトの種類によって多様なクライアント業界の理解も深まり、ITインフラ全般に対する知識が広がります。
SESインフラエンジニアのデメリット
SESインフラエンジニアには、スキル向上や幅広い経験ができるメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
案件の安定性や働き方、専門スキルの習得に関しては注意が必要です。
ここでは、代表的なデメリットについて詳しく解説します。
案件が決まるまで待機期間が発生する場合がある
SESインフラエンジニアは、プロジェクト単位で働くため、次の案件が決まるまで待機期間が発生することがあります。
この待機期間中は、業務に従事していない状態が続くため、収入が減少する可能性があります。
企業によっては待機期間中の給与が保証されない場合もあるため、安定性に欠けるという不安があるのです。
また、待機期間が長引くと、技術力やモチベーションの維持が難しくなることもあります。
常駐先によっては残業や休日出勤になることがある
SESインフラエンジニアは、クライアント先での業務が多いため、常駐先の状況に大きく左右されます。
特に、クライアントのプロジェクト進行状況によっては、残業や休日出勤が発生することが少なくありません。
SES企業によっては、こうした追加業務の調整が難しい場合があり、長時間労働が常態化してしまうことも。自分では労働環境をコントロールできない点が、ワークライフバランスを保つ上でのデメリットとなることがあります。
専門性が身につきにくい場合がある
SESインフラエンジニアは、多様なプロジェクトに関わる機会がある一方で、特定の技術や分野に集中してスキルを深める時間が限られることがあります。
短期間の案件が多いため、一つの分野に対して深い専門知識を習得しづらくなる場合があります。
また、クライアントの指示に従って業務を行うため、自主的に技術を学ぶ余裕がなくなることも。
結果として、特定分野での専門性が不足し、キャリアの方向性が見えにくくなることがあります。
SESインフラエンジニアとして成功するキャリア戦略
SESで得られる経験やスキルを活かし、次のステップに進むための準備をすることが、長期的なキャリアアップの鍵となります。
ここでは、具体的なキャリア戦略について解説します。
インフラ系の資格を取得する
SESインフラエンジニアとしてのスキルを証明し、キャリアアップを目指すためには、インフラ系の資格取得が効果的です。
特に、CCNA(Cisco Certified Network Associate)やAWS認定資格、LPIC(Linux Professional Institute Certification)など、ネットワークやクラウド関連の資格は、インフラエンジニアにとって有力なスキルの証明となります。
資格を持つことで、企業内の評価が高まり、プロジェクトリーダーや上流工程の業務にも携わるチャンスが増えます。
また、資格取得の過程で学んだ知識が実務に直結するため、技術力の底上げにもつながり、より高度な案件を担当することができるようになります。
企業によっては資格手当もあるので取得しておいて損はないでしょう。
スキルを身につけSESからフリーランスや社内SEに転職する
SESで培ったスキルを活かし、フリーランスや社内SEに転職するのも、キャリア戦略の一つです。
フリーランスになることで、自分のスキルや経験に基づいて報酬を設定でき、柔軟な働き方を実現できます。
フリーランスとして活躍するためには、インフラ設計やクラウド構築などの専門スキルだけでなく、自己管理やプロジェクトをスムーズに進めるコミュニケーション力も求められます。
一方で、社内SEとして転職する場合、クライアントワークではなく、自社内でのインフラ運用や管理に携わることが中心となります。
社内SEは安定した環境で働けるため、長期的なキャリア形成に向いている選択肢です。
転職エージェントを活用して、SESでの経験をどのように評価されるかを確認しつつ、自分に合った働き方を選びましょう。
活学キャリアは、ITに特化した転職エージェントで、累計1,000名以上が利用し満足度は90%以上と高水準です。
常駐先の企業に引き抜かれる
SESインフラエンジニアとして常駐先で高い評価を得ると、クライアント企業から直接雇用のオファーを受けるケースもあります。
これは「引き抜き」とも呼ばれ、クライアント先で優れた技術力や信頼を築いたエンジニアにとっては、キャリアアップの大きなチャンスです。
特に、長期的なプロジェクトで成果を上げることで、クライアント側が「自社に必要な人材」として評価することが引き抜きの理由となります。
引き抜きの場合、社内SEとして安定したポジションで働けるだけでなく、既に慣れた業務環境でスムーズに新しいキャリアをスタートできる利点があります。
ただし、引き抜きの際には、給与や待遇、キャリアパスについてしっかりと交渉し、自分の目標に合ったオファーかどうかを見極めることが大切です。
SESインフラエンジニアがキャリアアップで注意すべき点
SESインフラエンジニアとしてキャリアアップを目指す際、目先の技術だけに囚われたり、評価基準に依存しすぎることで長期的な成長が妨げられることがあります。
以下に、キャリアを進めるうえで注意すべき点を解説します。
特定の技術に依存しすぎない
SESインフラエンジニアとしてプロジェクトに取り組む中で、特定の技術に精通することは強みになりますが、依存しすぎるとキャリアの幅が狭まる危険性があります。
例えば、特定のネットワーク機器やクラウドプラットフォームに精通しても、その技術が古くなったり、クライアントのニーズが変わると、新しい技術をキャッチアップする必要に迫られます。
技術は常に進化しているため、幅広く最新の技術に触れながら、バランスよくスキルを向上させることが、長期的なキャリアアップにつながります。
クライアント先での評価に過度に依存しない
SESインフラエンジニアとして働く際、クライアント先での評価は重要ですが、過度に依存してしまうのは危険です。
クライアントの評価に応じてプロジェクトが延長される場合もありますが、それが必ずしも自身のキャリアにとって最適な選択とは限りません。
評価に頼りすぎると、自分のキャリアプランや成長の方向性が見えにくくなり、結果としてスキルの幅を広げる機会を逃してしまう可能性があります。
定期的に自分のキャリア目標を見直し、自分にとって価値のある案件に積極的に取り組む姿勢が大切です。
長時間労働に慣れすぎない
SESの働き方では、プロジェクトの進行状況やクライアントの要望によって、長時間労働が発生することが少なくありません。
しかし、長時間労働に慣れすぎてしまうと、ワークライフバランスが崩れ、心身の健康に悪影響を及ぼすこともあります。
さらに、長時間働いていることで「頑張っている」という評価に頼りすぎると、労働時間に対して成果が伴わない場合も出てきます。
キャリアアップを目指す際には、効率的な働き方を心がけ、自分の体調や生活環境を優先しながら、質の高いアウトプットを意識することが重要です。
これらの注意点を理解し、バランスの取れたキャリア形成を進めることで、SESインフラエンジニアとしての成功がより現実的なものになるでしょう。
SESインフラエンジニアが選ぶべき企業の特徴
SESインフラエンジニアとしてのキャリアアップや働きやすさを考えるうえで、どの企業に所属するかは非常に重要です。
技術力が向上できるか、働き方は問題ないか、以下のような特徴を持つ企業を選ぶことが大切です。
研修制度、OJTがしっかりしている
研修制度やOJT(On-the-Job Training)がしっかりと整備されている企業を選ぶことで、最新技術を学びながら実務での応用力も高めることができます。
例えば、クラウド技術(AWS、Azure)、セキュリティ、ネットワーク管理などに特化した研修プログラムが用意されている企業は、成長の機会が豊富です。
また、現場での実践的な指導が行われるOJTも、自身のスキルを短期間で伸ばすために有効です。
上流工程に携われるチャンスがある
SESインフラエンジニアとして、キャリアアップを目指すなら、上流工程に携われる機会がある企業を選ぶことが重要です。
上流工程では、ネットワークやシステムの要件定義や設計を行い、プロジェクトの方向性を決定する立場となります。
これにより、技術力だけでなく、顧客とのコミュニケーションスキルやプロジェクト管理能力も鍛えることができます。
特にSESでは、クライアント先での保守・運用に留まるケースが多いため、上流工程を経験できる企業は貴重です。
この経験が積めることで、プロジェクトリーダーやマネージャーへのキャリアパスが開け、社内SEやフリーランスへの転職時にも大きな武器となります。
上流工程に携われるチャンスがない場合、SESエンジニアとしてのキャリアが特定の技術領域や運用保守に偏りがちになり、キャリアアップに限界が生じてしまう可能性があります。
下流工程(運用や保守、トラブルシューティング)に従事するだけでは、技術力は向上しますが、プロジェクト全体を管理するスキルや、システム設計に必要な知識を得る機会が少なくなってしまいます。
有休消化率が高く働き方がホワイト
SES業界では、クライアント先の都合によって残業や休日出勤が発生しやすく、労働環境が厳しい企業も少なくありません。
しかし、労働環境がホワイトで、有給休暇の消化率が高い企業は、働きやすさの面で非常に大きなメリットがあります。
有給休暇がしっかり取れる企業は、従業員の健康管理や働き方に配慮しており、ワークライフバランスを保ちながらキャリアを積むことができます。
また、労働時間の管理が厳格で、残業が少ない企業では、仕事に対する生産性が重視されているため、効率よく働きたいエンジニアにとって理想的な職場です。
健康を守りつつ、長期的なキャリアを築くためには、ホワイト企業を選ぶことが賢明な選択です。
SESインフラエンジニアの将来性と業界トレンド
SESインフラエンジニアの将来性は、IT業界全体の進化と密接に関連しています。
特にクラウド技術の急速な普及やセキュリティへの関心の高まりによって、SESエンジニアに求められるスキルや役割は大きく変化しています。
ここでは、最新技術や業界のトレンドに基づき、SESインフラエンジニアのキャリアにどう影響するかを解説します。
SESインフラエンジニアに求められる最新技術とは?
SESインフラエンジニアには、従来のネットワークやサーバーの運用スキルだけでなく、最新のクラウド技術や自動化ツールの知識が求められます。
AWSやAzureといったクラウドプラットフォームに関するスキルは、現代のITインフラ業界では必須となりつつあります。
また、AnsibleやTerraformなどのインフラ自動化ツールを活用して、効率的にシステムの構築・運用を行う能力も求められています。
また、セキュリティやコンテナ技術(Docker、Kubernetes)の知識も重要であり、特にリモートワークやDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代において、これらの技術の習得はこれからの時代に不可欠です。
今後のITインフラ業界の動向
ITインフラ業界は、今後も急速な変化を続けると予想されています。
クラウド化の進展により、企業は従来のオンプレミス(社内サーバー)からクラウドへの移行を進めており、これに伴いクラウド環境の構築・運用スキルを持つSESエンジニアの需要がますます高まるでしょう。
また、リモートワークの普及により、ネットワークセキュリティの強化や、仮想デスクトップインフラ(VDI)への対応も重要な課題となってきています。
このような背景から、ITインフラ業界ではSESエンジニアが関与できるプロジェクトが増加しており、今後も安定した需要が続くと考えられます。
クラウド技術の普及とSESインフラエンジニアの需要
クラウド技術の普及により、SESインフラエンジニアの需要を大きく押し上げています。
今後もクラウド化の波は広がり続け、SESインフラエンジニアの需要は高まる一方です。
SESエンジニアは、複数のクライアントやプロジェクトを通じて幅広いクラウド技術を習得できるため、特にクラウド移行プロジェクトやクラウド環境の最適化において重要な役割を担います。
さらに、クラウド技術の普及により、企業はセキュリティ対策やコスト管理を重視しており、SESインフラエンジニアには、クラウドのセキュリティやコスト最適化に関する知識も必要とされています。
SESインフラエンジニアにおすすめの転職エージェント3選
SESインフラエンジニアとして転職を考える際、信頼できる転職エージェントのサポートは非常に重要です。
ここでは、SESインフラエンジニアに特におすすめの転職エージェントを3つ紹介します。
活学キャリア
活学キャリアは、ITエンジニアに特化した転職エージェントで、特にSESエンジニアのキャリアアップ支援に力を入れています。
多くのSES企業やITインフラ関連企業との強力なネットワークを持っており、SESインフラエンジニアに最適な求人を紹介してくれます。
活学キャリアは、求職者のスキルと希望に基づいて、技術的な成長が見込める企業を紹介することを重視しているのが特徴です。
そのため、利用満足度は90%以上と高水準です。
また、転職後のキャリアアッププランまで含めたサポートを提供しており、長期的な視野でキャリア形成を支援してくれる点が大きな強みです。
レバテックキャリア
レバテックキャリアは、ITエンジニアやクリエイターに特化した転職エージェントで、SESエンジニアの転職支援にも非常に強い実績があります。
特にインフラエンジニア向けの求人が多く、ネットワーク、クラウド、サーバー関連のプロジェクトを数多く扱っているのが特徴です。
加えて、レバテックキャリアは転職希望者のキャリアパスに基づいたサポートを提供しており、SESから社内SE、さらにはフリーランスとしてのキャリアも視野に入れた提案をしてくれる点が魅力です。
マイナビIT AGENT
マイナビIT AGENTは、マイナビグループが運営するITエンジニア専門の転職エージェントです。
SESエンジニア向けの求人も多く取り扱っており、特に社内SEやインフラ運用管理職への転職を目指すエンジニアに最適なエージェントです。
専任のキャリアアドバイザーが転職活動全般をサポートし、内定獲得までのプロセスをしっかりとフォローしてくれる点も大きな特徴です。
SESインフラエンジニアに関するよくある質問【Q&A】
SESインフラエンジニアとして働く上で、よくある質問と回答を紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
SESインフラエンジニアは年収はどれくらい?
SESインフラエンジニアの年収は、スキルや経験年数、所属する企業やクライアント先のプロジェクトによって異なりますが一般的に、SESインフラエンジニアの平均年収は400万円〜600万円ほどです。
新人や経験の浅いエンジニアの場合、300万円台からのスタートが多く、技術力やプロジェクトマネジメント経験が豊富なエンジニアであれば、年収700万円以上を目指すことも可能です。
また、AWSやAzureなどのクラウド技術や、ネットワーク・サーバーに関する高度なスキルを持つエンジニアは、さらに高い収入を得られるチャンスがあります。
SESからフリーランスに転向する際の注意点は?
SESインフラエンジニアとして働いていて、フリーランスに転向する際には、いくつかの重要な注意点があります。
フリーランスは、常に自分で案件を探し続ける必要があり、安定した収入を得るためには継続的な営業活動が不可欠です。
契約書の確認や報酬の支払い時期の確認は特に注意が必要です。
支払いの遅れや報酬額が契約通りに支払われないリスクもあるため、信頼できるクライアントと取引することが重要。
さらに、税金や社会保険の手続きも自分で行わなければならないため、フリーランスとしての知識や準備が必要です。
SESと自社開発の違いは?
SESと自社開発には、働き方やキャリアパスに大きな違いがあります。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、クライアント企業に常駐してシステムの運用・保守やインフラ構築を行う形態が一般的です。
短期間で複数のプロジェクトに関わることができるため、幅広い技術や経験を積むことができます。
しかし、プロジェクトごとにクライアントの要求に応じて働くため、長期的なシステム開発や深い専門スキルを積む機会は少なくなることがあります。
一方、自社開発では、自社内で長期的にシステムの設計・開発・運用を行うため、特定の分野で深い知識と技術を積み上げることが可能です。
自社開発では、自分たちの製品やサービスに責任を持って取り組むため、プロジェクトの一貫性や安定した環境で働くことができます。
ただし、技術の範囲が限られる場合もあり、異なる技術やプロジェクトに頻繁に関わるチャンスはSESほど多くありません。
どちらを選ぶかは、エンジニアとしてのキャリアや働き方の希望に応じて判断することが重要です。
まとめ:SESインフラエンジニアとして環境を活かしてキャリアアップしよう
SESインフラエンジニアは、多様なプロジェクトに参加できる環境にあるため、技術や経験を広げる大きなチャンスが得られます。
しかし、プロジェクトごとの安定性や働き方がさまざまなので、しっかりと自分に合った環境を見極めることが重要です。
長時間労働やプロジェクトの待機期間といったSES特有のデメリットをカバーするため、働きやすい環境やサポート体制が整った企業を選ぶことが、長期的なキャリア成功につながります。
失敗しないためにも転職エージェントに相談してみましょう。

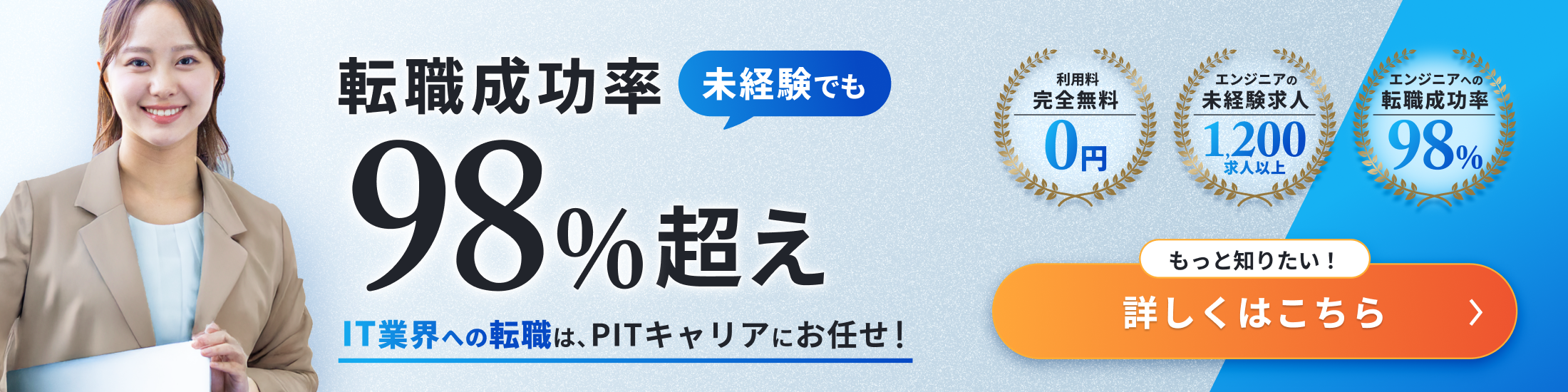
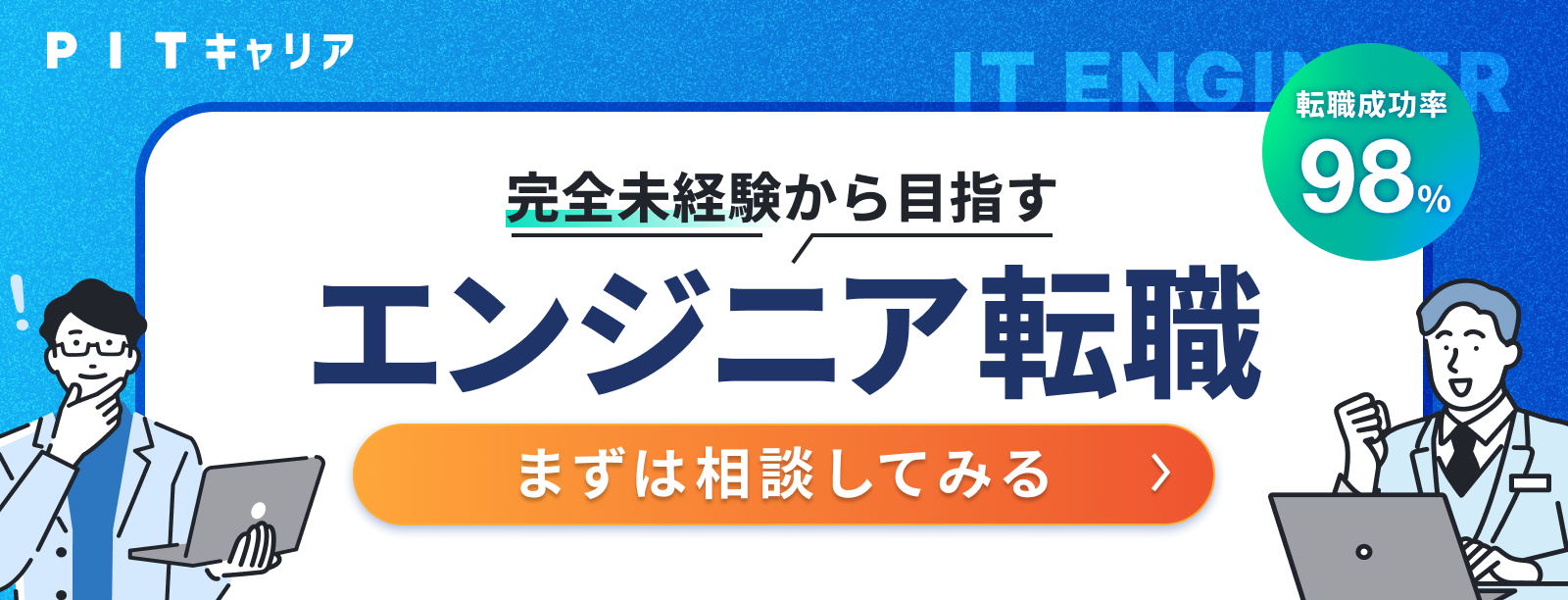
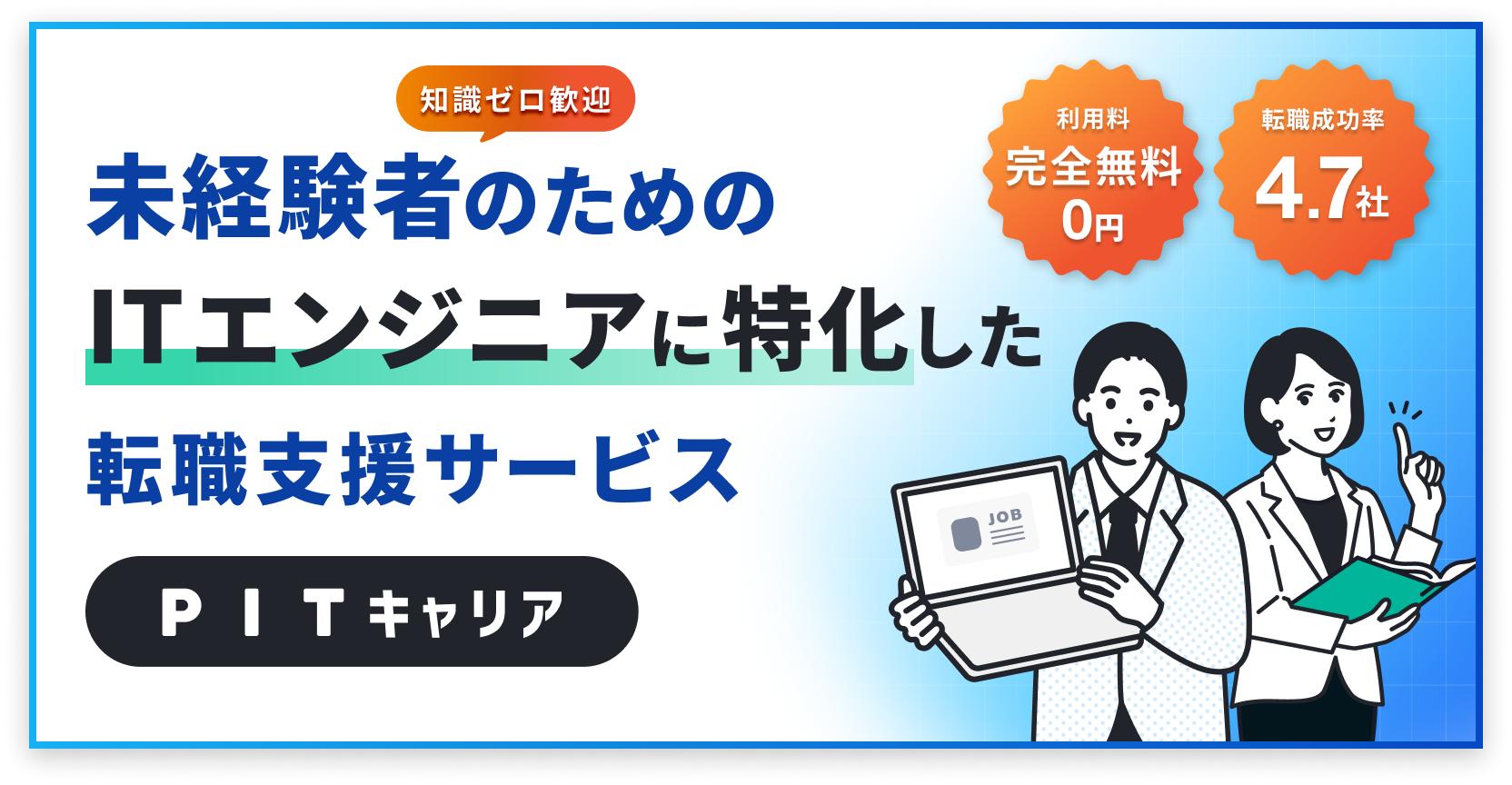



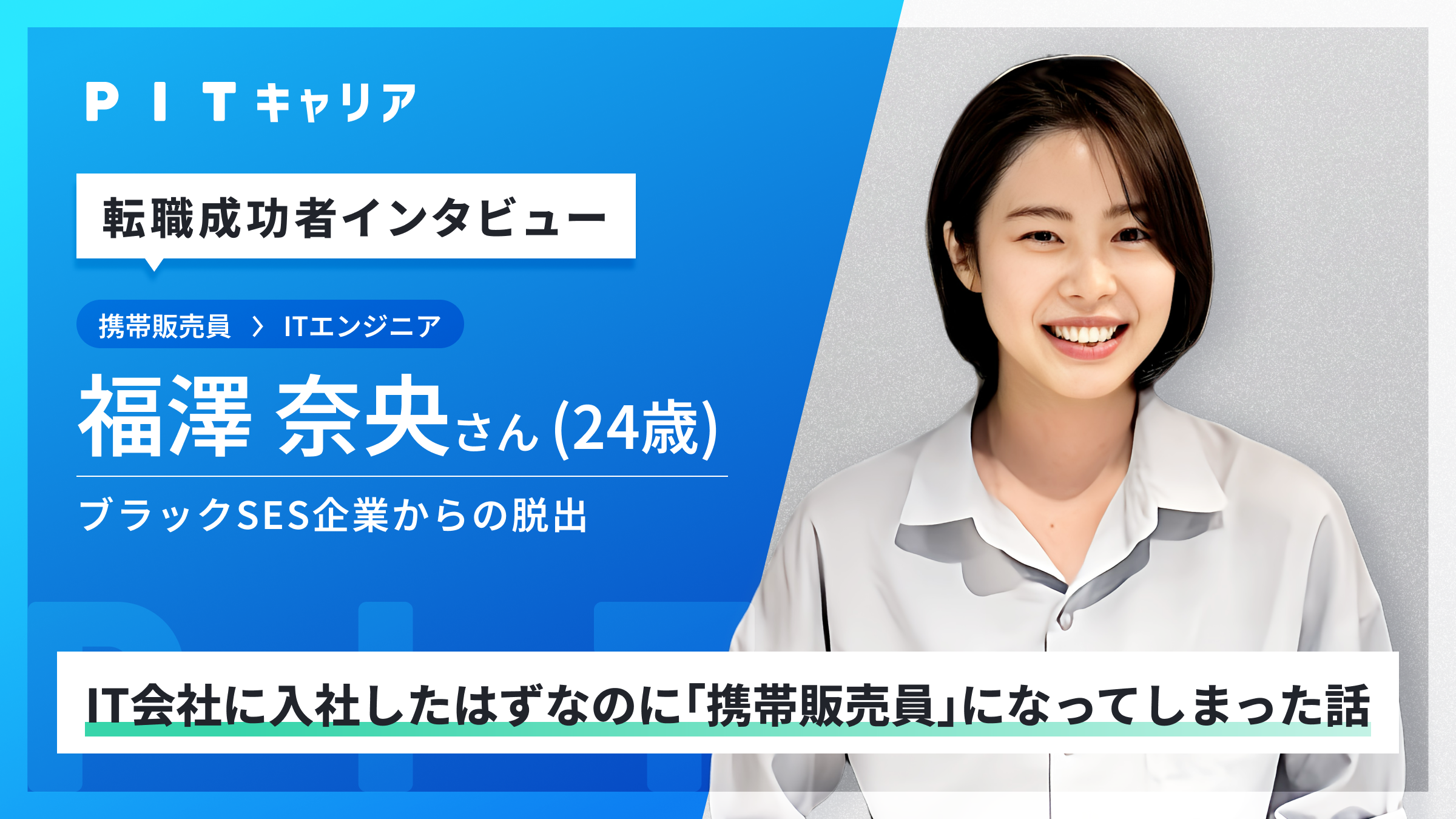


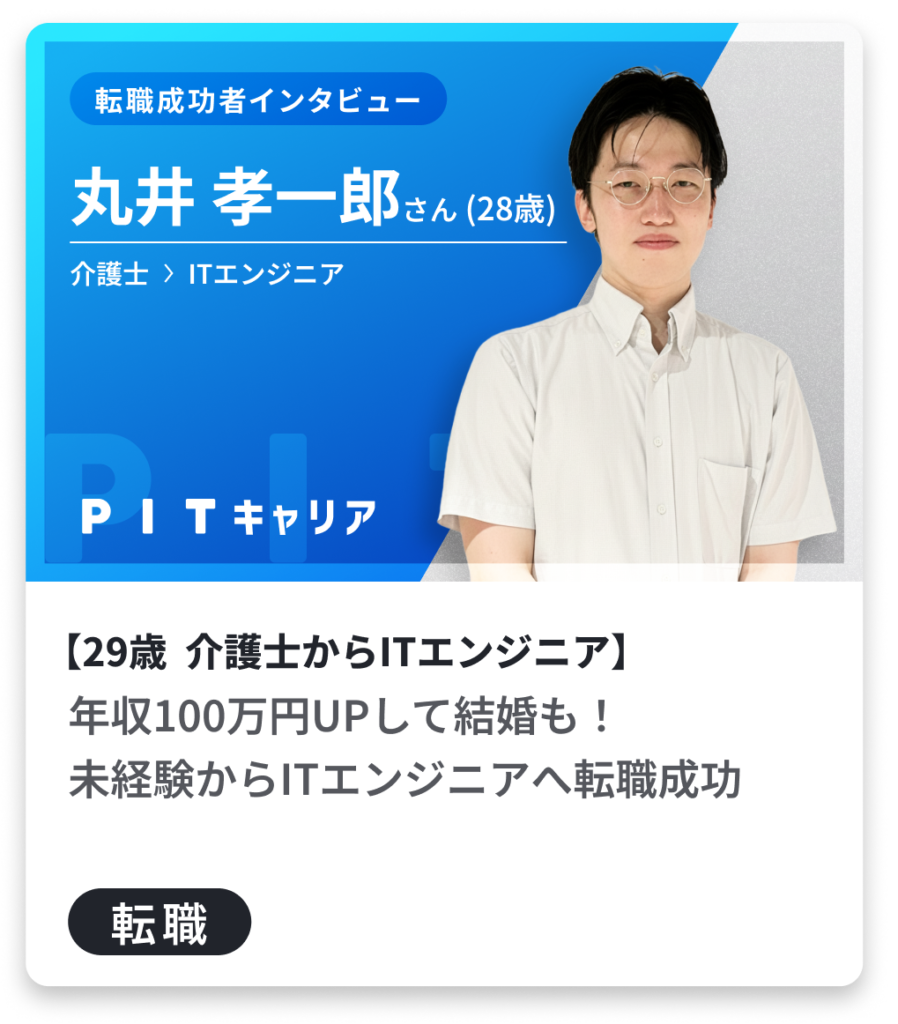
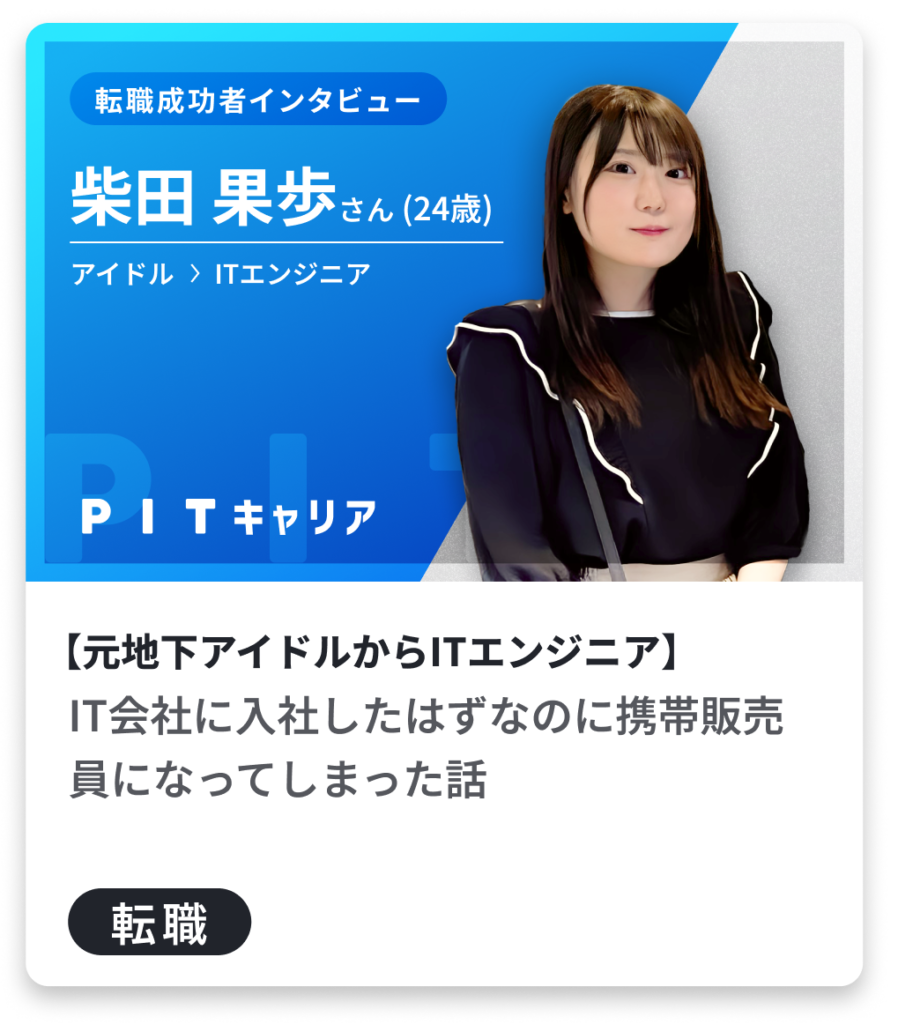
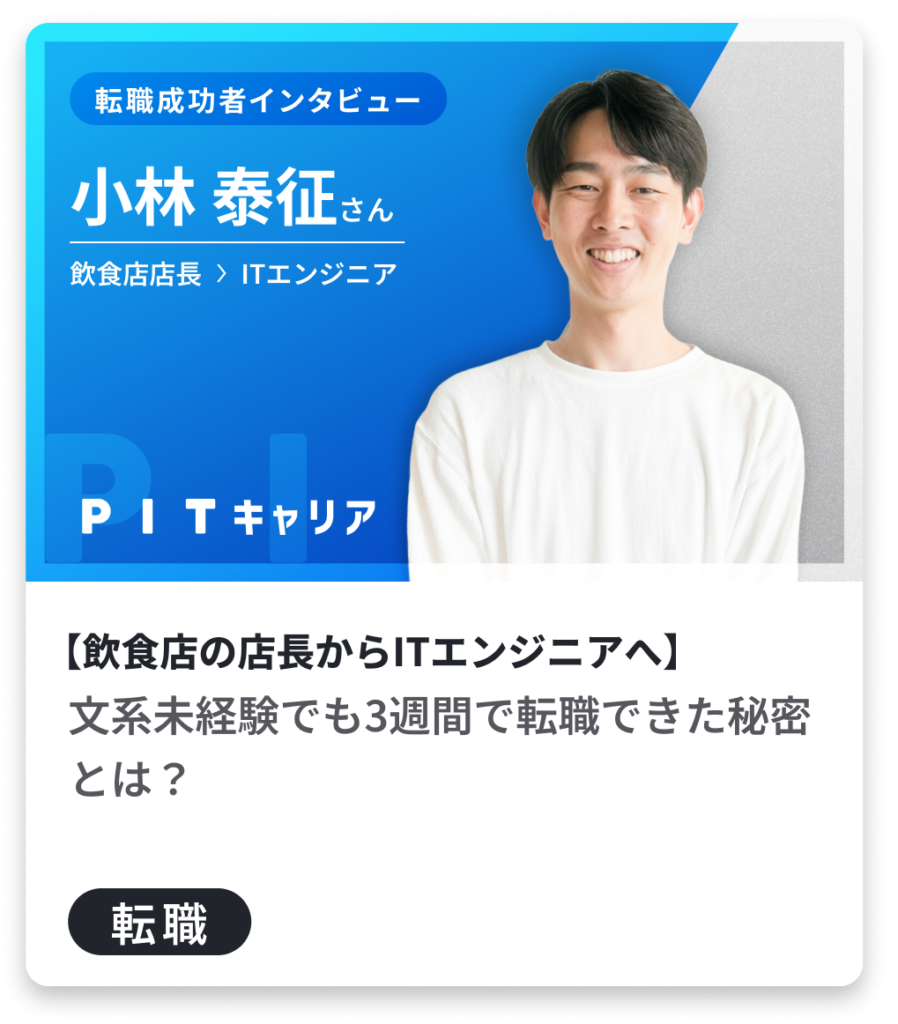

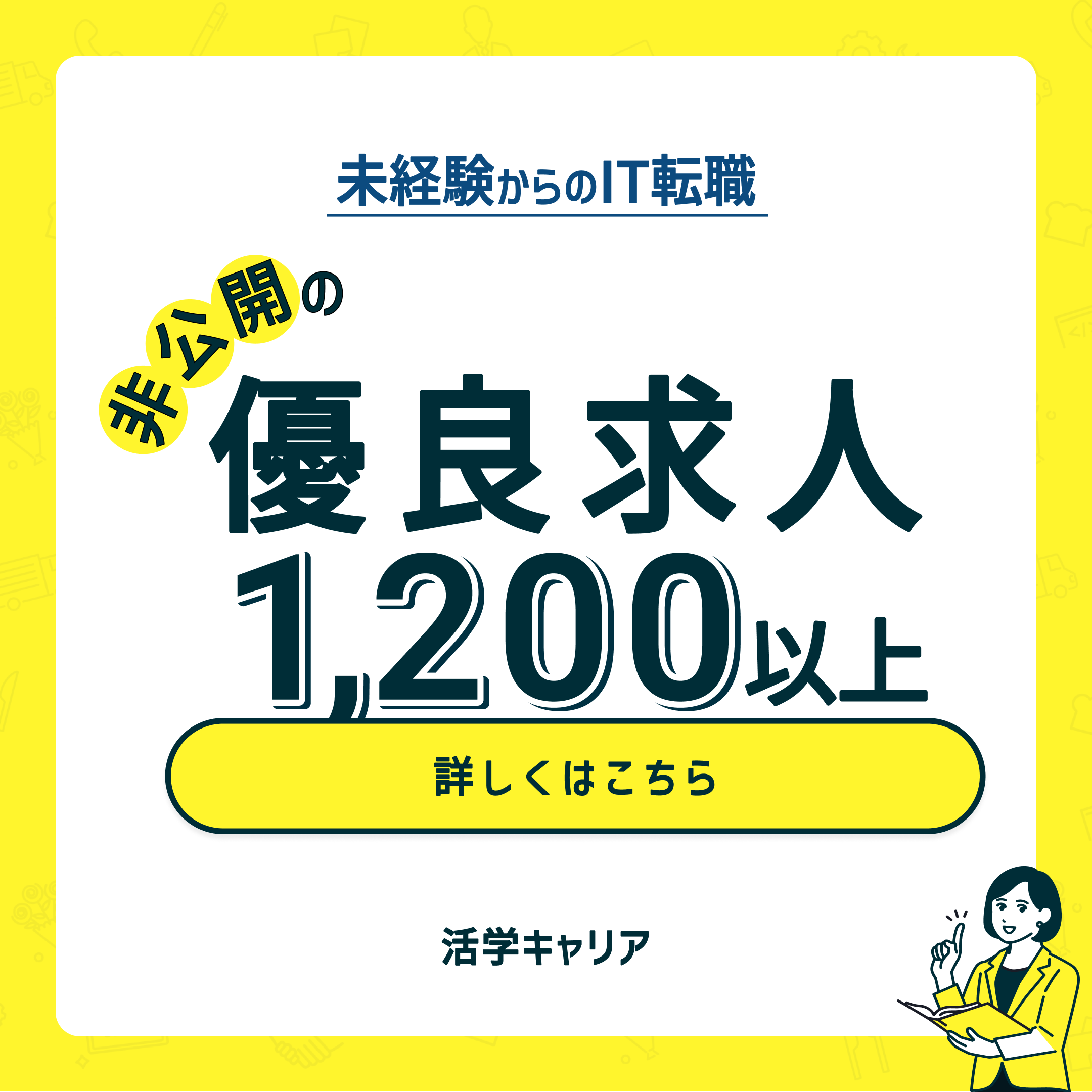

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
