カテゴリー
SES面談で違法になるケースとは?企業もエンジニアも危険!
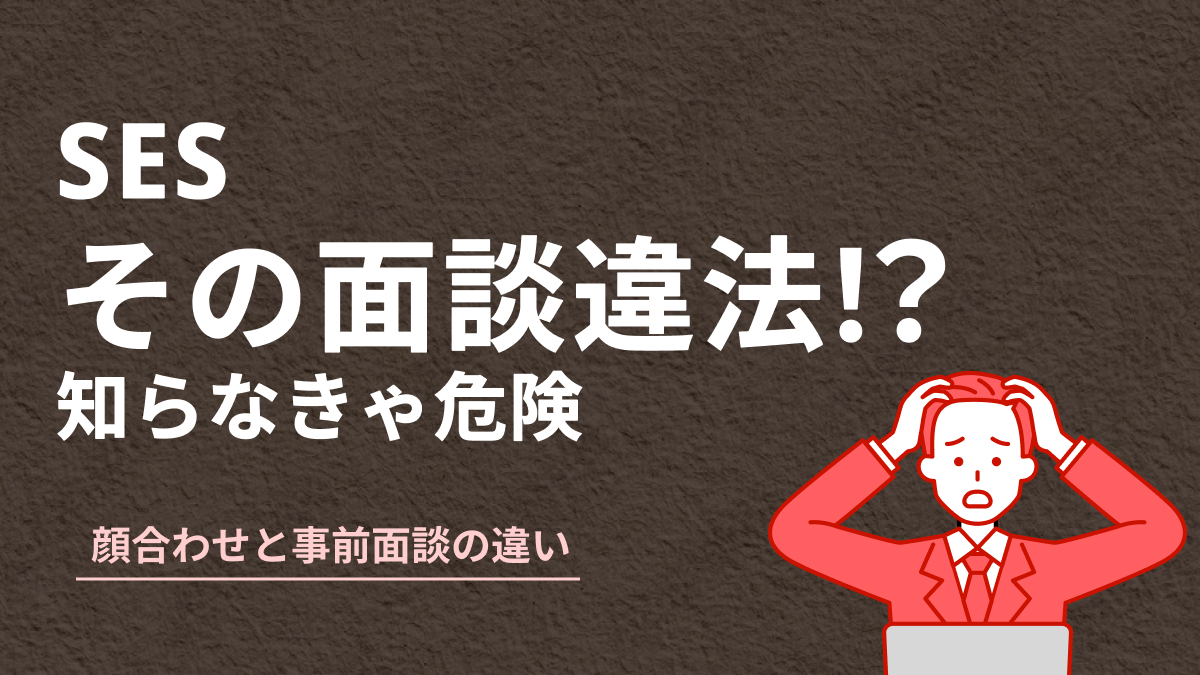

「SESの面談って本当本当は違法なの?」



「もし違法だったら、どうなるんだろう…」
こんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実際、SES面談には法律的なリスクが潜んでいます。
この記事では、企業やエンジニアが知らずに違法となってしまうケースを詳しく解説します。
合わせて読みたい⇒SESはやめとけ?体験談をもとに理由を徹底分析!
SES面談の違法性を避けるための基礎知識
SES契約や面談において、法律の理解不足が原因で違法行為とみなされる可能性があります。
特に、SES契約は派遣契約や請負契約と異なるため、それぞれの違いを明確に把握することが重要です。
以下で、SES契約の基本や、よく混同される派遣契約との違いを説明します。
SES契約と派遣契約の違いを理解しよう
SES契約では、SES企業(エンジニアを雇用・派遣する会社)がエンジニアに対する指揮命令を行う一方、派遣契約ではクライアント(エンジニアを受け入れる会社)が直接指示を出します。
この違いは、法的なリスクを回避する上で非常に重要です。
SES契約の場合、SES企業がエンジニアに対して指示を出し、業務の責任を持つため、クライアントが直接指示を出すことは違法となります。
SES契約では、クライアントとの役割分担が明確でなければ、違法行為に発展する可能性があります。
| 項目 | SES契約 | 派遣契約 |
|---|---|---|
| 指示命令系統 | SES企業 | クライアント |
| 契約内容 | 技術的な業務提供 | 労働力提供 |
| 法律適用 | 技術者派遣法適用外 | 労働者派遣法の適用 |
労働者派遣法とSES契約の違いは?
労働者派遣法は、派遣労働者の保護を目的とした法律です。
一方、SES契約は労働者派遣法の適用外です。
しかし、SES契約が実質的に派遣契約と同様の働き方をしている場合、偽装派遣として違法となる可能性があります。
クライアントがSES技術者に業務上の具体的な指示を行う場合、この法律に抵触しやすくなるため、契約内容と業務実態をきちんと区別する必要があります。
例えば、SESエンジニアがクライアントから
「このプロジェクトのスケジュールに遅れないよう、このタスクを優先して進めてください」
と直接指示を受けた場合、それは実質的に派遣労働者として指示を受けたことになり、労働者派遣法違反となる可能性があります。
SES契約においては、エンジニアへの指示はすべてSES企業を通じて行われるべきであり、クライアントが技術者に直接的な業務指示を出さないようにすることが重要です。
SES面談が違法にならないための方法とは?
SES面談は、SESエンジニアのスキル確認や業務内容の理解のために行われるもので、労働者派遣法に抵触しないようにすることが重要です。
違法にならない面談を行うためには、クライアントがSESエンジニアに具体的な業務指示を与えないことが前提です。
面談時には、技術力の評価やプロジェクトの理解度を確認することに留め、指示や指揮命令はSES企業側が行う形を徹底することが必要です。
SESで客先面談は違法?合法と違法の境界線
SES契約での客先(SESエンジニアが実際に働く場所、クライアントのオフィスなど)面談が合法か違法かを見分けるには、労働者派遣法に基づいて判断します。
SES企業がSESエンジニアに対する指揮命令を保持している場合、客先での面談は合法となります。
しかし、クライアントがSESエンジニアに業務指示を行った場合、その行為は違法とみなされる可能性が高まります。
客先面談が違法となる具体的ケース
SES面談が違法となる例として、クライアントがSESエンジニアに対して業務の具体的な指示を出す場合があります。
たとえば、SESエンジニアが担当する仕事の進め方や優先順位について、クライアントが直接指示をしてしまうと、それは労働者派遣法に違反する可能性があります。
また、SES企業が関与せずに、クライアントとSESエンジニアが直接やり取りをして仕事を進める状況も、偽装請負とみなされる場合があり、これも違法となるリスクがあります。
ポイントは、クライアントがSESエンジニアに対して具体的な指示を出さないよう、SES企業が指揮命令を管理することが必要です。
SES契約での客先面談が許容される条件
SES契約で客先面談が合法になるためには、SES企業がエンジニアに対して指示を出し、クライアントが具体的な業務指示をしないことが必要です。
例えば、SES企業がエンジニアに「プロジェクトの進行状況を確認してください」と指示を出すのは問題ありませんが、クライアントが「このタスクを最優先で進めてください」と直接指示を出すと違法になる可能性があります。
SES企業は事前にエンジニアの業務内容を把握し、クライアントと連携して指示系統を管理することで、法律に違反しないようにすることが重要です。
SES面談に潜む法的リスクの回避方法
SES面談には、多くの法的リスクが潜んでいます。
特に、SES企業とクライアントの役割分担が曖昧な場合、面談の内容が違法性を帯びることがあります。
まとめとして一覧表にしましたので、参考にしてください。
| 状況 | 違反か違反でないか | 理由・解説 |
|---|---|---|
| クライアントがSESエンジニアに直接業務指示を出す | 違反 | SES契約では、指揮命令権はSES企業にあるため、くらいあんとが直接指示を出すと労働派遣法違反となる可能性がある |
| SES企業が面談時に指示系統を保持している場合 | 違反でない | SES企業が技術者への指示を管理している場合、クライアントはSESエンジニアに直接指示を出さず、スキル確認に留めるため合法 |
| クライアントがSESエンジニアに進行状況を確認する | 違反でない | 進捗確認は業務指示ではなく、SES企業が主導で関与していれば問題ない |
| クライアントがSES企業を通じて指示を出す | 違反でない | クライアントがSES企業を通じて指示を出し、SES企業がエンジニアへの対応を行う場合は合法となる |
| SES企業が不在でクライアントとエンジニアが直接交渉する | 違反 | SES企業が関与しない場合、エンジニアがクライアントから直接指示を受けることになり、偽装請負や労働派遣法違反となる |
クライアント:
SES企業からSESエンジニアを派遣してもらう企業
SES企業:
SES企業は、自社で雇用しているエンジニア(SESエンジニア)を他の企業(クライアント)に派遣し、技術的なサービスを提供する企業
SES面談で「顔合わせ」と「事前面談」の違いと合法性
「顔合わせ」は業務に関する指示がない状況での単なるスキル確認。
「事前面談」は業務内容に関する具体的な指示が含まれる。
これらを混同しないように明確な対応を行うことが、合法的な面談の実施に必要です。
「顔合わせ」が合法になるための条件
SES面談での「顔合わせ」が合法であるためには、クライアントが業務内容に関する指示を一切出さないことが重要です。
例えば、
「どんなプロジェクトを経験してきましたか?」
「チームで働くのが得意ですか?」
といった、技術者のスキルや相性を確認するための軽いコミュニケーションは問題ありません。
ただし、
「このプロジェクトを具体的にどう進めてほしいか」
という業務の詳細な指示が含まれると、労働者派遣法に違反するリスクが高まります。
このため、業務指示はすべてSES企業が管理し、クライアントは面談の範囲を超えないように注意が必要です。
SES面談で「顔合わせ」を行うメリットとデメリット
「顔合わせ」を行うことで、SES企業はクライアントと技術者の相性を確認し、プロジェクトの成功率を高めることができます。
ただし、「顔合わせ」がクライアントによる業務指示を含む場合、労働者派遣法に違反するリスクが生じる可能性があります。
このため、SES企業は「顔合わせ」の目的と範囲を明確に定義し、面談の際の進行を適切に管理する必要があります。
SES面談で問題になりやすい「事前面談」の実態
「事前面談」は、SES契約のもとでエンジニアとクライアントが業務内容について詳しく話し合う場ですが、違法行為を引き起こす可能性があります。
例えば、クライアントが
「このタスクをこの手順で進めてください」
と具体的な指示を出してしまうと、偽装派遣とみなされ、労働者派遣法に違反することがあります。
そのため、SES企業は事前に面談内容を整理し、面談中にクライアントがエンジニアに業務指示を出さないように調整する必要があります。
SES企業が面談の進行を管理し、クライアントとエンジニアの間に介入することで、違法性を回避することが重要です。
SESの二重(多重)派遣は違法?見逃せない注意点
二重派遣、または多重派遣は、SES契約においてしばしば問題視される違法行為の一つです。
実は、SESエンジニアとして働く中でこの違法行為に巻き込まれると、思わぬトラブルや責任問題に発展する可能性があります。
これから解説する注意点を押さえておくことで、リスクを回避し、安心して働くことができます。
SESの二重(多重)派遣とは?
SESの二重(多重)派遣とは・・・
SES契約で派遣されたエンジニアが、クライアント(派遣先企業)からさらに別の会社や現場に派遣されることを指します。
これは、労働者派遣法に違反する行為であり、SES契約のルールに反する違法な形態です。
例えば、SES企業がエンジニアAをクライアントBに派遣したとします。
しかし、クライアントBがそのエンジニアAを、さらに別の会社Cで働かせるよう指示した場合、これが二重派遣に該当します。
二重派遣を避けるためにSESエンジニアが行うべき対策
SESエンジニアが二重派遣を避けるためのポイントを5つ紹介します。
- 指示を受ける相手を確認する
SES契約では、エンジニアはSES企業(派遣元)からの指示を受けるとされています。
クライアント(派遣先)から直接の指示を受けると、労働者派遣法違反となる場合があります。
もしクライアントから業務に関する具体的な指示を受ける場合は、SES企業に報告し、適切な対
応を依頼しましょう。 - 別の現場や企業に派遣されないか確認する
自分が契約しているSES企業以外の指示で別の企業や現場に行かされるようなことがあれば、それは二重派遣の可能性があります。
クライアントが自分をさらに別の場所に派遣しようとした場合は、SES企業に報告しましょう。 - 自分の契約内容を確認する
契約書をしっかり確認し、どの範囲で業務を行うか、どこで働くか、指示系統がどうなっているかを理解することが大切です。
契約内容を超えた指示が出された場合は、SES企業に相談してください。
業務範囲や指示系統が曖昧な場合は、SES企業に明確にしてもらいましょう。 - トラブルが発生したらすぐに報告する
クライアントから違法な指示や業務範囲外の仕事を求められた場合、または二重派遣の可能性がある場合は、すぐにSES企業に報告しましょう。
報告を怠ると、エンジニア自身が違法行為に巻き込まれてしまう可能性があるので、早めの対応が大事です。 - 定期的にSES企業と連絡を取る
SES企業がエンジニアの業務内容を把握し、問題がないかを確認することが重要です。
定期的にSES企業とコミュニケーションを取り、業務状況を報告しましょう。
SES企業と連絡を取ることで、クライアントからの違法な指示や業務範囲の変更を防ぐことができます。
二重派遣に関する最新の法律動向と影響
労働者派遣法は定期的に改正されており、二重派遣に関する規制はますます厳しくなっています。
最近の法改正では、二重派遣が発生した際の責任や罰則が明確化され、労働環境の適正な運用がより重視されました。
SESエンジニアは、契約内容や働く環境を常に確認し、疑問があればSES企業に相談することが重要です。
最新の法律動向を理解しておくことで、自身が不利な立場に置かれないよう、法的リスクを回避できるようにしましょう。
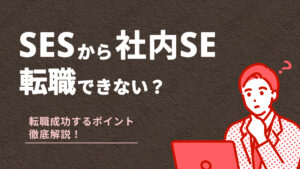
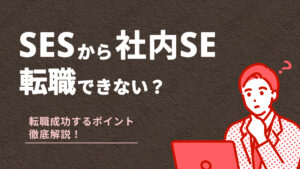
【実は違法】一人で常駐先に派遣するSES企業の危険性
SES契約の下で、エンジニアがクライアント先に一人で派遣されるケースは少なくありませんが、これには大きなリスクがあります。
特に、エンジニアが一人で常駐することで、労働者派遣法に違反する可能性が高まり、エンジニア自身がトラブルに巻き込まれることもあります。
一人常駐が違法になる理由とリスク
一人でクライアント先に派遣されると、SES企業がエンジニアの業務を管理しにくくなり、クライアントから直接指示を受けることが増えることがあります。
たとえば、SESエンジニアとして派遣されたあなたが、最初は軽い指示を受けていたものの、次第に
「このプロジェクトの進め方をこう変えてくれ」
「優先するタスクをこれにしてほしい」
といった具体的な業務指示を直接受けるようになった場合、これはすでに労働者派遣法に違反する状態です。
SES契約では、指揮命令権はSES企業にありますが、クライアントが直接業務指示を出すと、その構図が崩れ、偽装派遣とみなされるリスクが生じます。
これはSES企業だけでなく、エンジニア自身にも法的な影響を与える可能性があります。
一人常駐を避けるために確認すべきポイント
SESエンジニアとして一人常駐する場合、まず確認すべきは、指示系統が守られているかどうかです。
たとえば、クライアントが業務について具体的な指示を出そうとした際に、
「この内容はSES企業を通じて確認します」
と伝えることで、指揮命令系統を明確にすることができます。
また、SES企業が定期的にあなたの業務状況を確認しているか、クライアントからの指示内容を把握しているかも重要なポイントです。
もし、SES企業との連絡が途絶えている場合や、クライアントが日常的に具体的な指示を出す状況が続いている場合は、すぐにSES企業に報告し、状況を改善してもらうことが必要です。
一人常駐で起きたトラブル事例とその対策
【トラブル事例】
実際に、あるSESエンジニアが一人常駐していた現場では、最初はSES企業との連絡がありましたが、次第にクライアントからの直接指示が増え、SES企業はほとんど関与しなくなりました。
この結果、エンジニアはクライアントの一員として扱われるようになり、業務の内容や優先順位がすべてクライアントの指示に従って進められることになりました。
このケースでは、労働者派遣法違反が疑われる状況となり、最終的にSES企業が介入してクライアントとの契約内容を見直し、エンジニアがクライアントから直接指示を受けないように調整されました。
このようなトラブルを避けるためにも、エンジニア自身が業務状況を常に把握し、クライアントからの指示に違和感を感じたらすぐにSES企業に報告することが大切です。
一人常駐は、業務の効率が上がるように見えるかもしれませんが、指示系統が崩れることで、違法行為に巻き込まれるリスクが高まります。
SESエンジニアとしては、クライアントとSES企業の間で適切な役割分担が守られているかを確認し、トラブルを未然に防ぐ行動が求められます。
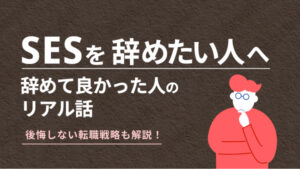
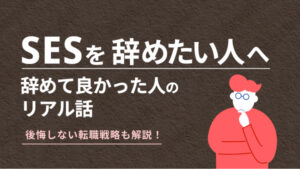
SES面談で違法とならない行為とは?
SESエンジニアとして、面談で違法行為に巻き込まれないためにも、クライアントとのやり取りで何に注意すべきかを解説します。
面談での質問にどう対応する?
面談中にクライアントから技術的なスキルや経験について質問されることは問題ありませんが、業務の進行に関わる具体的な指示を受けると違法な状況になる可能性があることを覚えておきましょう。
例えば、以下のような質問は問題ありません。
「これまでにどのようなプロジェクトを担当しましたか?」
「特定の技術に関する知識や経験はありますか?」
しかし、以下のような質問には注意が必要です。
「このプロジェクトでは、この部分をどう進めますか?」
「このタスクを具体的にどう解決しますか?」
SESエンジニアは、業務指示がクライアントからではなく、SES企業を通じて行われることを前提にしているため、具体的な業務内容に関する指示や質問はSES企業が介入するべきです。
面談時に不安を感じた場合は、SES企業に相談し、指示系統が守られていることを確認しましょう。
SES契約後の「引き抜き」どう対応する?
SES契約が終了した後、クライアントからの引き抜きにあたる転職の誘いを受ける場合があります。
これが即座に違法となるわけではありませんが、契約内容によっては問題になることもあるので注意が必要です。
一般的に、SES契約には「競業避止義務」や「引き抜き制限条項」といった条項が含まれているケースが多く、これに違反して転職を行った場合、法的なトラブルが生じる可能性があります。
たとえば、SES契約が終わってすぐにクライアントに転職する場合、契約違反とみなされるリスクがあります。
以下3つの点に注意してください。
1、契約書を確認する
転職や引き抜きに関する制限条項が含まれているかどうかを確認しましょう。
2、SES企業に相談する
引き抜きの誘いを受けた場合は、SES企業に報告し、適切な対応を相談しましょう。
3、法的アドバイスを求める
複雑な状況の場合、労働法の専門家に相談して自分の権利を確認することが大切です。
SESで経歴詐称を強要されたら?
SES契約のもとで働いているエンジニアが、クライアントやSES企業から経歴の誇張や詐称を強要されることがあります。
これは明確な違法行為であり、エンジニア自身や企業に深刻な法的リスクをもたらす可能性があります。
例えば、実際に経験していないプロジェクトに関与したと偽るように求められたり、持っていない資格を持っているかのように装うよう指示されるケースが挙げられます。
こうした行為に従うことは、エンジニアのキャリアや信頼性を損なうだけでなく、法的にも重大な問題を引き起こす可能性があります。
対処法を3つ紹介します。
・毅然と拒否する
経歴詐称を求められた場合は、はっきりと拒否し、自分の正当な実績を守ることが大切です。
・SES企業に報告する
クライアントから強要された場合は、すぐにSES企業に報告し、対応を求めましょう。
SES企業が関与することで、適切な対処をしてもらいやすいです。
・法的支援を求める
もしも詐称が強制され続けた場合は、労働相談センターや弁護士などの法的機関に相談することが有効です。
SESエンジニアは、自分の実績を正確に示し、経歴詐称に巻き込まれないように常に注意を払うことが必要です。正直なキャリアを築くことで、長期的な信頼を得ることができます。


SES契約を巡るトラブル事例
SES契約において、クライアントやSES企業が法的なルールを誤解したり無視したりすることで、さまざまなトラブルが発生することがあります。
ここでは、実際に起きた典型的な法的トラブルを具体的に説明します。
【事例1】クライアントが直接業務指示を出した
あるSESエンジニアAさんは、大手企業BにSES契約で派遣されました。
当初はSES企業を通じて業務指示が行われていましたが、クライアントBがプロジェクトの進行に焦りを感じ始め、エンジニアAさんに直接「このタスクをこの方法で進めてほしい」と具体的な指示を出すようになりました。
Aさんもその場の流れに従い、クライアントBの指示で業務を進めましたが、これは偽装派遣と見なされ、労働者派遣法違反となる可能性がありました。
SES企業にこの事実が発覚し、急遽プロジェクトを修正。
クライアントBには労働者派遣法の遵守を求める書面が送られ、SESエンジニアへの直接指示が厳禁であることが再確認されました。
Aさん自身もSES企業に報告し、適切な業務指示を再設定することで、違法行為を回避しました。
【事例2】二重派遣が発覚
SESエンジニアCさんは、中規模企業Dに派遣され、システム開発を担当していました。
ところが、クライアントDはCさんをさらに自社の別部署や別の企業に送り込み、その現場での業務も担当させました。
Cさんは複数の場所で指示を受け、SES企業の許可なく働いていたため、二重派遣とみなされました。
これは労働者派遣法に違反する行為であり、SES企業、クライアントDともに法的な責任を問われる事態となりましたが、SES企業とクライアントDが問題を解決するために契約内容を見直し、Cさんは本来の契約範囲内での業務に戻ることになりました。
二重派遣に関する罰則が厳格化されていたため、クライアントDには注意喚起が行われ、今後同様の違法行為を繰り返さないことが約束されました。
【事例3】エンジニアが経歴詐称を強要
SESエンジニアEさんは、SES企業Fに雇用され、クライアントGへの派遣が決まりました。
ところが、SES企業FはEさんに対し、クライアントGに提出する書類に「経験したことのない技術やプロジェクトに参加していた」と記載するよう指示しました。
Eさんは困惑しましたが、SES企業Fの指示を拒否し、実際の経験に基づく内容で書類を提出しました。
しかし、その後もSES企業Fから同様の強要が続いたため、Eさんは労働相談センターに相談し、弁護士を通じてSES企業Fに対し正式な抗議を行いました。
最終的にSES企業Fは経歴詐称の強要を認め、Eさんには謝罪が行われ、Eさんは新たなSES企業との契約を結び、安心して働ける環境を取り戻しました。
これらの実例は、SES契約で起こりがちな法的トラブルの一部に過ぎません。
エンジニアは、自分の役割や契約内容を正確に理解し、問題が発生した際には早めにSES企業や専門家に相談することが重要です。
SESの面談違法を避けるためのチェックリスト
SES面談で違法を避けるために、以下の10のチェックリストを活用してください。
1、クライアントが直接業務指示を出していないか確認
面談はあくまでスキル確認であり、業務指示はSES企業を通じて行われるべきです。
2、「顔合わせ」や「事前面談」との区別が明確か
面談内容がスキル確認や相性確認にとどまることを確認。
3、SES企業が指揮命令を保持しているか確認
エンジニアへの指示がSES企業を通じて行われているか、しっかり確認しましょう。
4、業務内容について詳細な指示が出ていないか
クライアントが具体的な業務指示を出すことは労働者派遣法違反となる可能性があります。
5、SES企業との連携が取れているか
SES企業が面談の状況や内容を把握しているかどうか確認。
6、契約内容に基づいた面談かどうか確認
契約書に沿って、適切な手順で進められているかを確認。
7、クライアントとのやり取りが適切か
クライアントとのやり取りが指揮命令を受けない形で行われているか確認。
8、面談内容をSES企業に報告する
面談後、SES企業に面談の内容を共有し、問題がないか確認。
9、業務内容に変更がないか確認
面談後に業務内容が変更された場合は、SES企業を通じて確認を行いましょう。
10、問題があれば即報告
不適切な指示や疑問があれば、すぐにSES企業に報告して対策を取りましょう。
まとめ:SES面談は違法ではないが、違法を行う企業には要注意
この記事では、SES契約の概要、違法面談、違法行為について説明してきました。
SESにおける違法行為と、誤解されやすいですが違法ではない行為のまとめです。
違法行為は下記の通りです。
・二重(多重)派遣
SES企業から派遣された労働者をさらに他の企業に派遣する行為
・偽装請負(指揮命令系統の違反、客先に一人で常駐させる)
客先にエンジニアを一人で派遣し、指揮命令を客先に与える行為
一方で、以下の行為は、誤解されやすいですが違法ではありません。
・SES契約
エンジニアの技術提供を目的とした契約
・引き抜き転職
SES契約終了後にクライアントへの転職
・経歴詐称
違法ではないものの、倫理的に問題があるため注意
・客先事前面談
顔合わせや職場見学
特に、経歴詐称を強要するような企業は危険ですので、すぐに転職を検討しましょう。
転職時にはIT業界に特化した転職エージェントを活用し、同様の違法行為を行う企業を避けるようにすることが大切です。

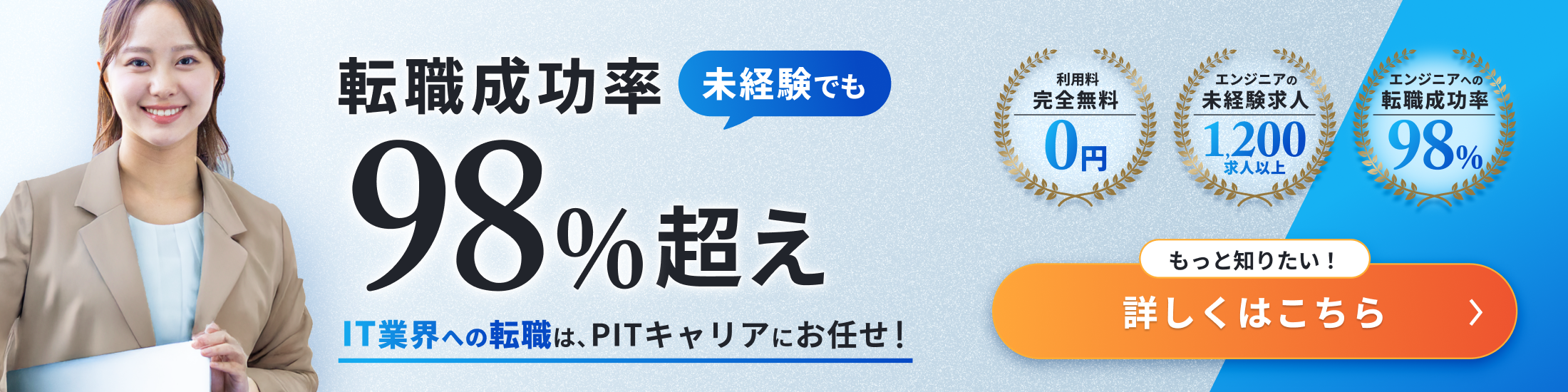
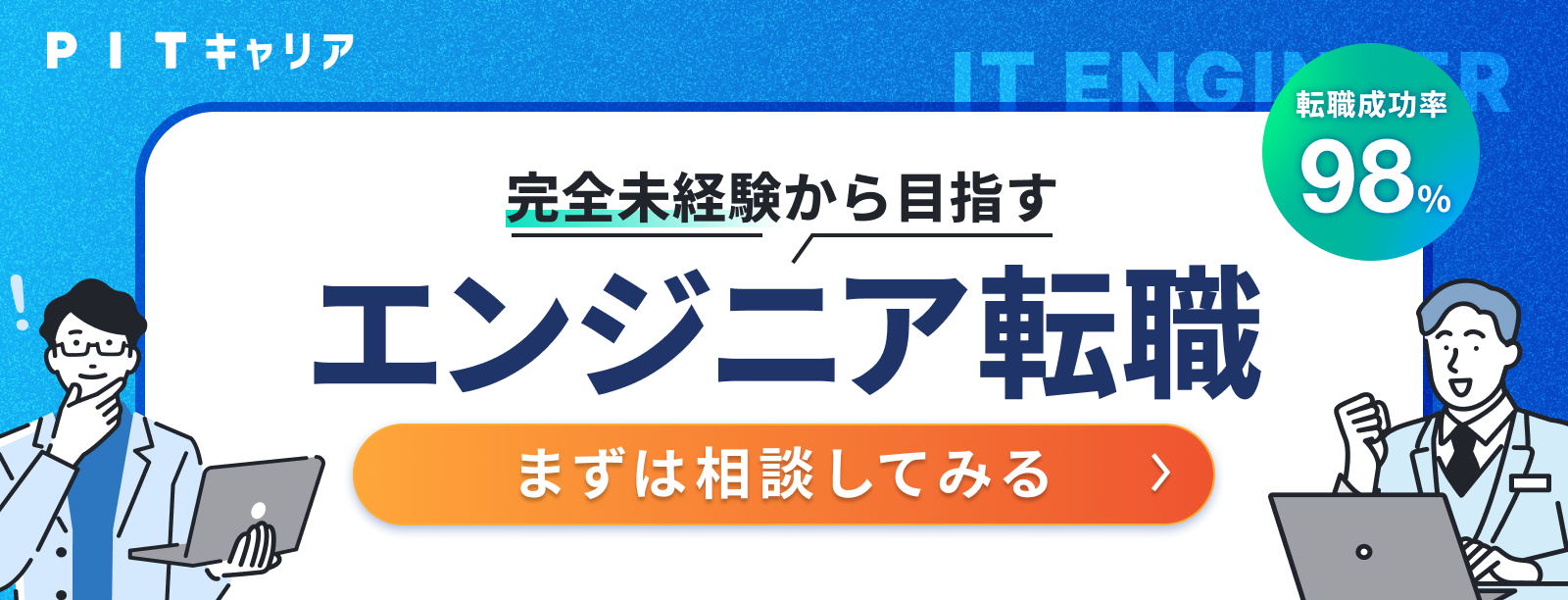
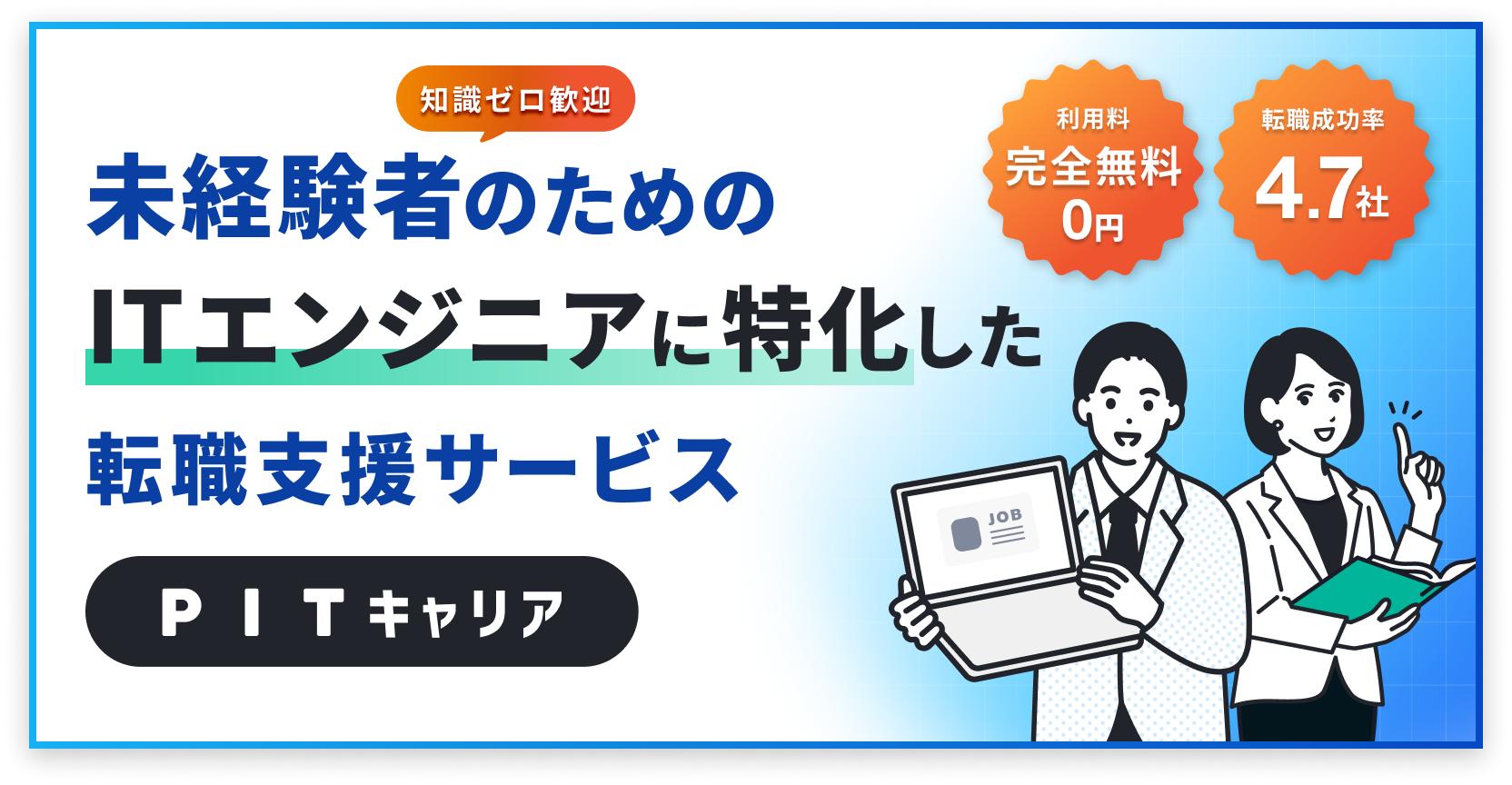


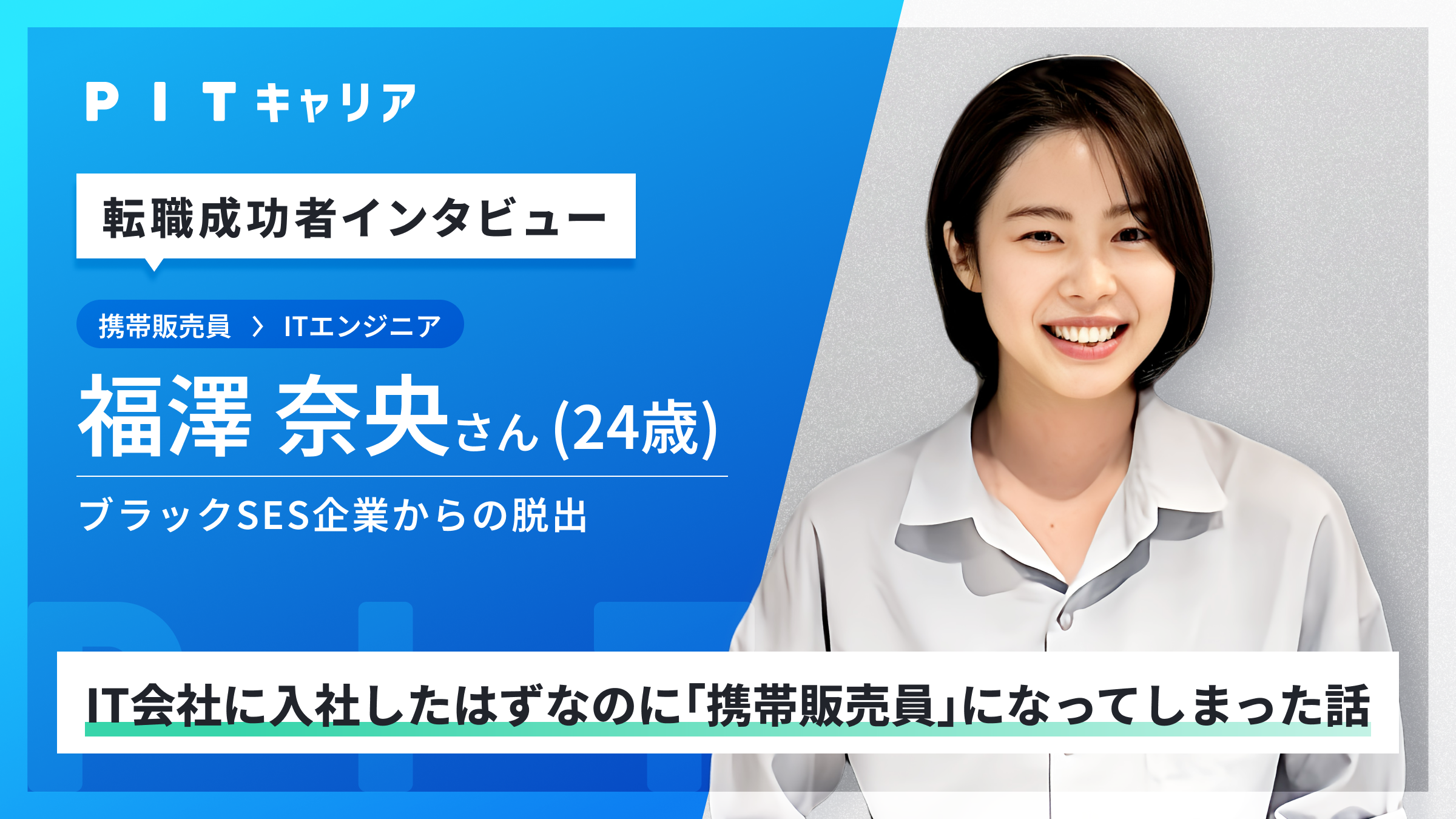


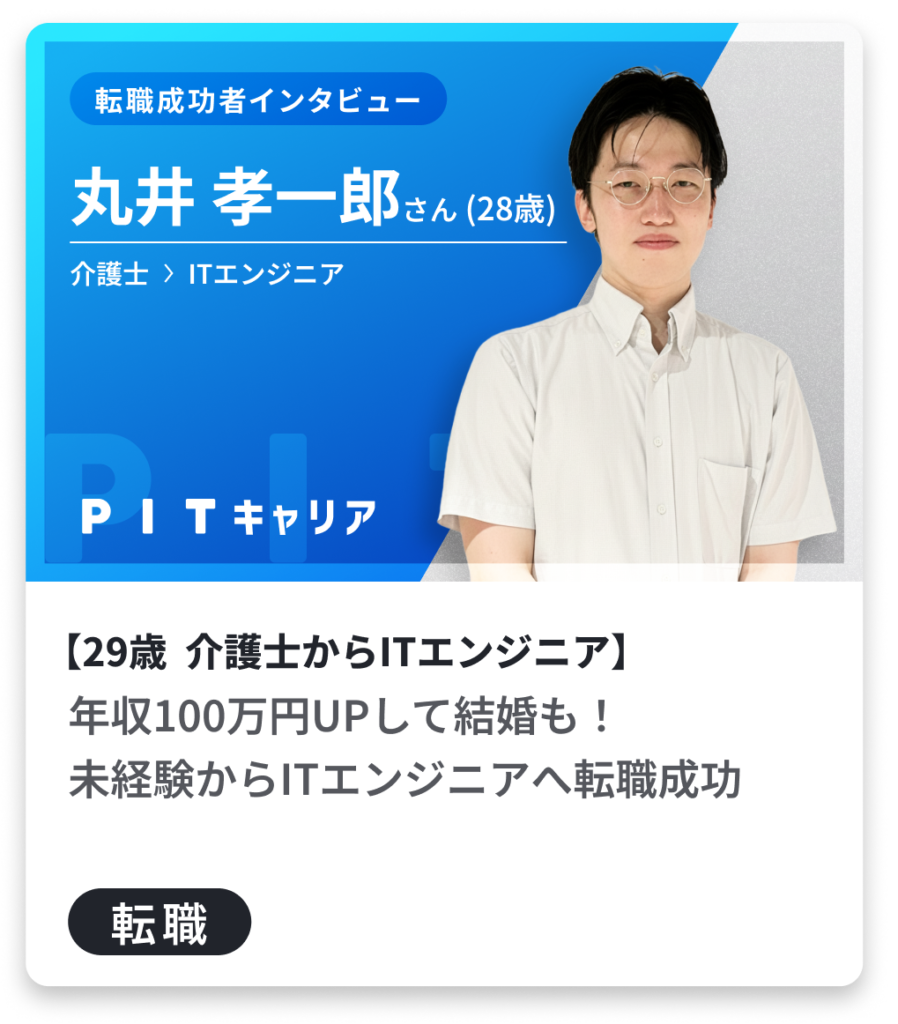
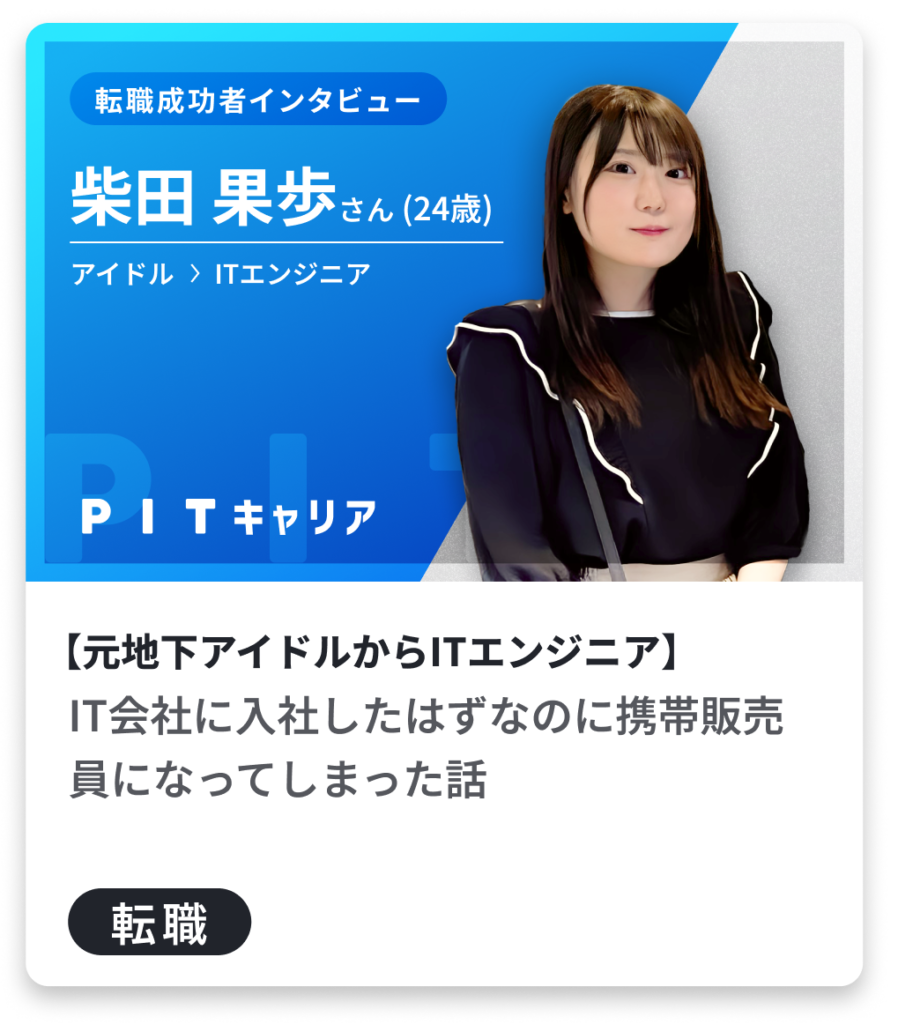
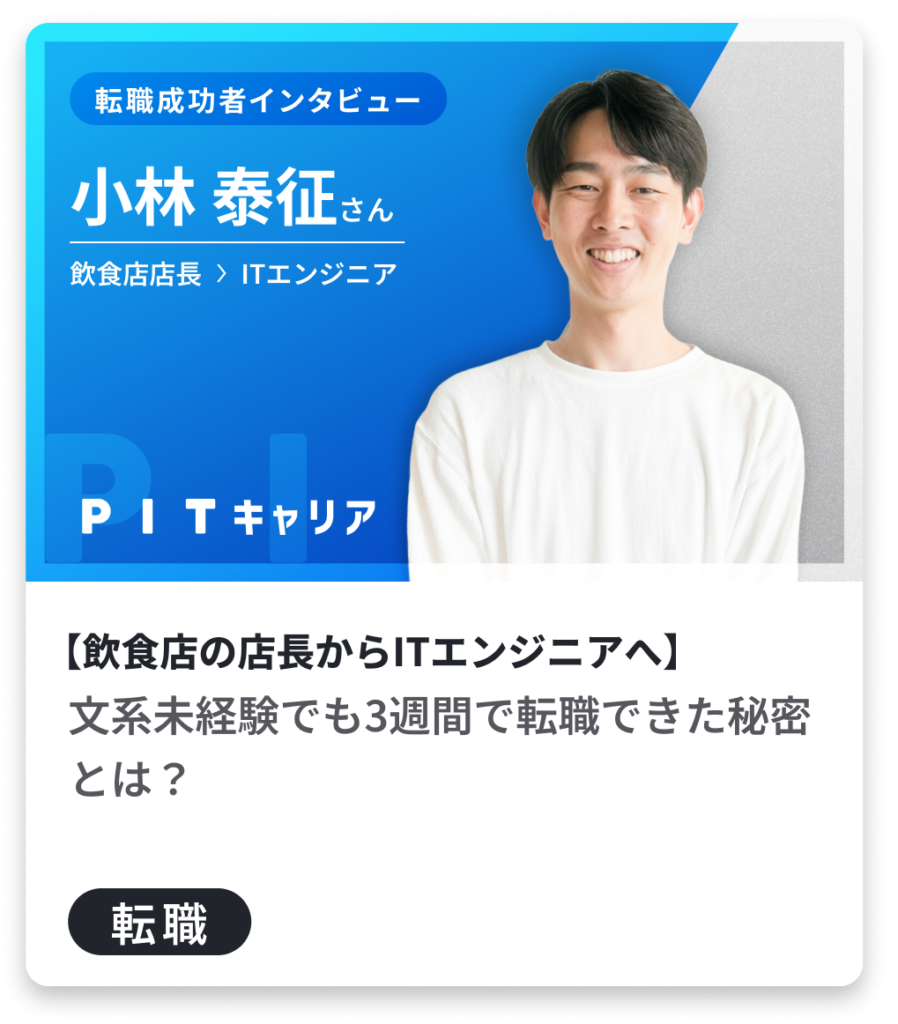

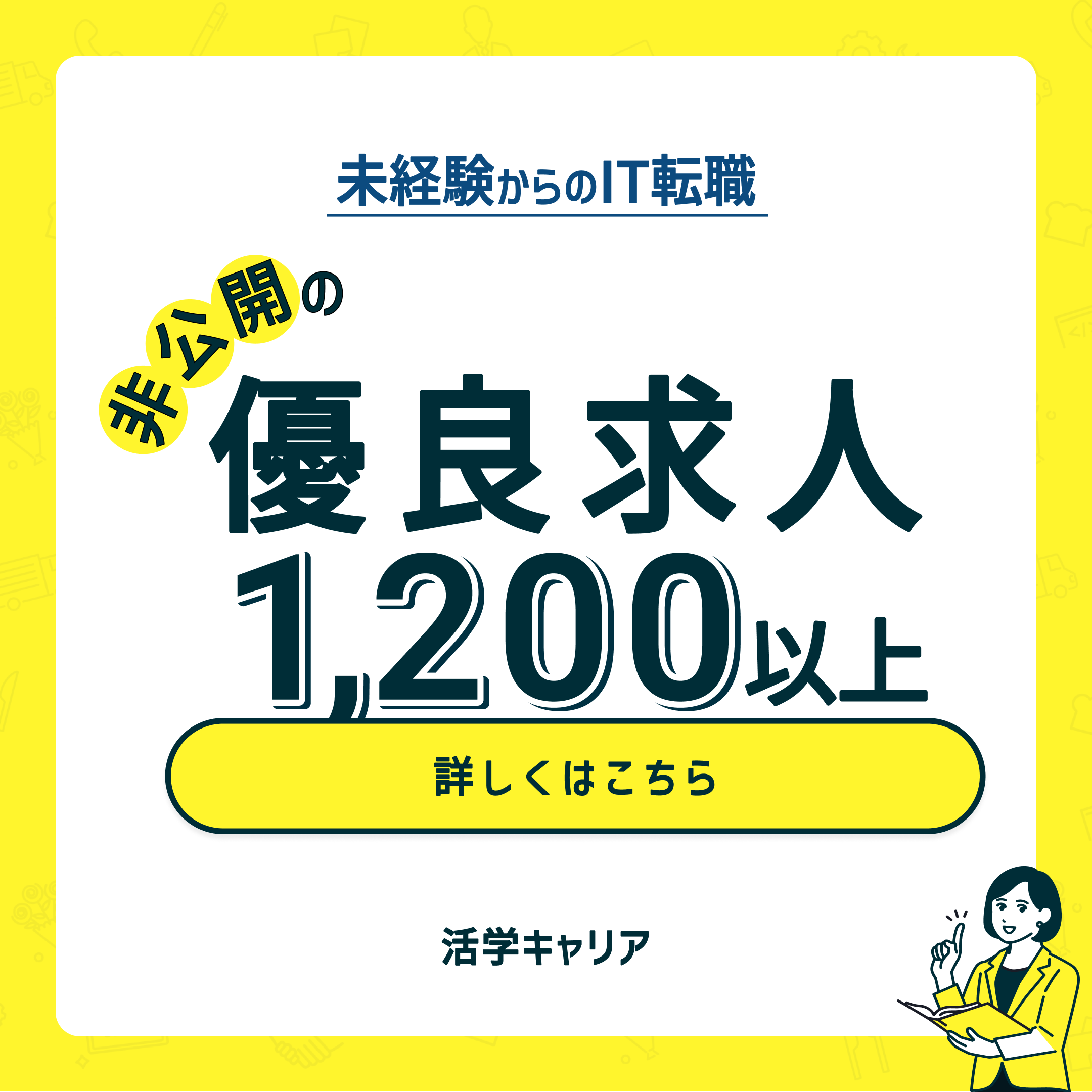

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
