カテゴリー
SESの将来性は?不安とオワコン論にエンジニア視点で答える


「SESの仕事って、今後も需要があるのかな…」



「SESで働いているけど、このまま続けていけるか心配」
そんな疑問を抱く方も多いでしょう。
本記事では、SESの基本的な仕組みや、なぜ今後も必要とされ続けるのか、その理由を詳しく解説します。
- SESの将来性の結論と根拠
- 伸びる領域/避ける環境
- 年収を上げる90日プラン
- 法的グレーの避け方・転職/案件変更の判断軸
結論|SESは「なくならない」。ただし選び方で将来は分かれる
SESは今後も必要とされ続ける働き方です。
IT業界の人材不足やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、SES企業へのニーズは今も高いままです。
ただし、どんなSES企業で働くか・どんなスキルを身につけるかで、将来は大きく変わります。
将来性を高める働き方
・クラウドやセキュリティ、自動化などの成長分野にスキルを寄せる
・案件選びで一次請け比率や評価制度を確認する
・客先評価を記録し、次の案件で活かす
将来を閉ざす働き方
・単純作業だけを繰り返す
・待機控除が常態化している
・昇給や単価基準が曖昧な環境
データで見るSESの将来性
SESの将来性を判断するには、感覚ではなく一次情報のデータを見るのが確実です。
IT人材は今後も不足が続く
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」では、2030年までに最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。
企業は外部人材を活用せざるを得ない状況が続いており、SESの需要は今後も安定して高いと考えられます。
出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」
DX(デジタル化)はさらに加速
IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2023」によると、DXに取り組む企業の割合は2021年度から2022年度にかけて約13%増加。
DX推進に伴い、SESエンジニアが活躍する現場は増え続けています。
出典:IPA「DX白書2023」
IT投資は年々拡大
矢野経済研究所によると、2023年度の国内民間IT市場は前年比6.3%増の約15兆円に達しています。
企業のIT投資が増える限り、SESエンジニアの需要は継続します。
出典:矢野経済研究所
伸びる領域と避けたい環境
SESの将来性を左右するのは、どの領域でスキルを積むか・どんな環境で働くかです。
今後も伸びる分野
・クラウド基盤(AWS、Azure、GCP)
・セキュリティ運用(EDR、ゼロトラスト)
・インフラ自動化(Ansible、Terraform)
・データ分析や監視基盤(Prometheus、Grafana)
避けたい環境の特徴
・多重構造で自社の立ち位置が不明確
・待機控除が常態化している
・評価や昇給の基準が非公開
・営業担当が現場を把握していない
こうした環境を見抜く方法は、SES企業の見分け方の記事で詳しく紹介しています。
年収とキャリアを上げる90日プラン
「どう動けば将来性を上げられるのか?」 そんな方に向けて、3か月で結果を出す現実的なステップを紹介します。
Day1〜7:現状を整理
担当業務・障害対応・チケット数などを記録。
自分が「どんな価値を出しているか」を見える化します。
Week2〜4:伸びる分野を学ぶ
クラウド資格(AWS SAAなど)の学習を始める
・Ansibleで手順自動化
・DX関連業務を担当する機会を提案する。
Week5〜8:成果を形にする
業務改善提案書
・自動化スクリプト
・監視設計書
などを成果物として残します。評価を受け取れる形にしましょう。
Week9〜12:評価と単価を交渉
営業担当との面談で成果を共有し、単価アップ交渉を行います。
もし現場を変えたい場合は、SES案件から抜けたい時の手順も参考にしてください。
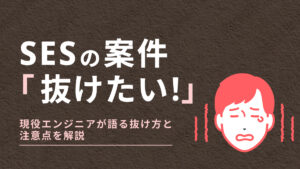
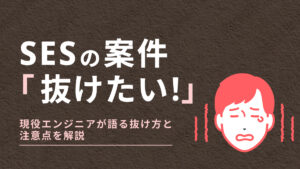
法的リスクとグレーな構造を避ける
SESは契約形態の複雑さから「グレー」と言われることもありますが、正しく理解すれば怖くありません。
契約時に必ず確認するポイント
・指揮命令系統が明確か
・待機時の給与や残業代の支払い条件
・契約形態が請負か準委任か
・派遣法抵触の有無
万一トラブルが起きた場合
まずSES企業に相談し、それでも解決しない場合は労働局や労基署へ。
⇒厚生労働省:契約・労働関係の相談先
ブラックSESの特徴や逆質問の例はこちらの記事で紹介しています。
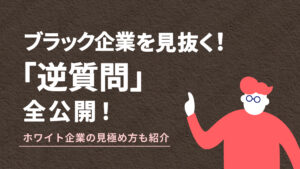
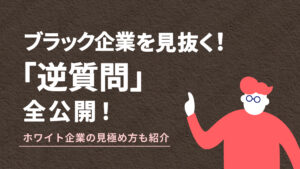
【体験談】「運用止まり」から半年で年収+70万円
「将来性なんてない」
と思いながら、夜勤中心の監視業務を続けていた27歳のインフラエンジニア。
毎日同じ作業の繰り返しに焦りを感じ、Ansibleを使った自動化提案を試みました。
最初は上手くいかず苦戦しましたが、少しずつ仕組み化を進めた結果、MTTR(障害対応時間)を30%短縮。
その取り組みが客先で評価され、次の案件ではSRE補助として参画。
半年後には単価が4万円アップし、年収ベースで+70万円に。
「環境を選び、動けば結果は出る」と実感できた瞬間でした。
同じように“現場に留まって不安を感じている人”は、 まず自分の経験を活かせる現場やスキル分野を見直してみましょう。
キャリアの方向性に迷ったときは、SESを辞めてよかった理由の記事や IT特化エージェント活学キャリアへの相談も参考になります。
迷ったときの選択肢
「今のSESで頑張るべき?」「転職した方がいい?」 そう感じたときは、3つの方向を考えてみましょう。
今の環境でスキルを伸ばす
クラウドや自動化を学び、社内で評価される成果をつくる。
具体例はSES年収の上げ方でも紹介しています。
案件を変えてリスタート
現場を変えたいときは、評価を落とさない伝え方が大切です。
SES案件を抜けたい時の手順で安全な方法をまとめています。
転職して環境を変える
転職でキャリアを広げたい方は、SESを辞めてよかった理由の記事で実例をチェック。
優良企業ランキングも参考にできます。
もし迷ったら、IT専門の転職支援サービス「活学キャリア」で無料相談するのもおすすめです。
あなたの経験をもとに、将来性のある働き方を一緒に考えてくれます。
なぜSESはなくならない?企業側の仕組みと将来性の理由
SESは、課題を抱える側面もありますが、企業に多大なメリットを提供しています。
そのため、SESの需要は現在も高く、今後もその存在意義を失うことはないと考えられます。
採用や教育コストが削減できる
SESを利用することで、企業は採用や教育にかかる時間と費用を大幅に削減できます。
正社員の育成には多大なリソースが必要ですが、SESを活用することで、即戦力となる人材を短期間で確保可能です。
これにより、プロジェクトのスタートが迅速化し、運用の効率が向上します。
正社員は容易に解雇できない
日本の法律では正社員の解雇が厳しく制限されているため、企業にとって正社員の人件費は大きな負担となります。
一方、SES契約ではプロジェクトごとに人員を配置し、期間が終了すれば解約が可能です。
この柔軟性が、多くの企業にとってSESを選択する重要な理由の一つです。
エンジニア不足で頼らざるを得ない
IT分野全体でエンジニア不足が深刻化する中、SESはプロジェクトを支える重要なリソースとなっています。
短期間で必要なスキルを持つ人材を確保する手段として、SESは欠かせない存在です。
この背景が、企業がSESに依存する理由となっています。
人員の入れ替えがしやすい
SESは、プロジェクトの進捗や内容に応じて柔軟に人員を調整できる仕組みです。
これにより、企業は必要なタイミングで適切なスキルを持つエンジニアを確保し、効率的なプロジェクト運営を実現できます。
この柔軟な特性は、SESの大きな魅力といえます。
定期的な売上が見込める
SES企業にとって、エンジニアを派遣することで得られる報酬は安定した収益源となります。
一方、クライアント企業側でも、SES契約によりプロジェクト単位でコスト管理が可能となり、予算計画が立てやすいという利点があります。
こうした相互の利益がSESの需要を支えています。
参入障壁が低い
SES業界は、初期投資が少なくても事業を開始できるため、比較的参入しやすい市場です。
その結果、多くの企業がSES事業に参加しています。
ただし、新規参入が容易な分、企業間の競争が激しくなり、サービスの質に差が出ることもあります。
信頼性の高い企業を選ぶことが重要です。
リモートワークの普及
近年、リモートワークの普及がSES契約にも変化をもたらしています。
エンジニアがリモートで働くことで、物理的な制約が減少し、企業は全国から優れた人材を確保できるようになりました。
この柔軟な働き方がSESのさらなる普及を後押ししています。
優良企業が増えてきている
SES業界はかつて劣悪な労働環境が問題視されていましたが、最近ではホワイトSES企業の台頭が進んでいます。
こうした企業は、労働条件の改善やスキルアップ支援を積極的に行い、エンジニアが安心して働ける環境を提供しています。
この変化により、SESの働き方も見直されつつあります。


エンジニアのキャリアから見たSESの将来性と伸びる方向
エンジニアとして、SESとしてキャリアを形成していくうえで、



SES業界の将来性って大丈夫なのかな?
と気になる方も少なくないと思います。
結論から言うと、SESには将来性があります。
IT業界の成長とともにエンジニアの需要は増え続けており、SESは多様な現場で経験を積めるキャリア形成の場として注目されています。
ここでは、SESの現状と将来性をわかりやすく解説します。
IT業界とSESの現状
IT業界はデジタル化やリモートワークの普及によって急成長しており、エンジニアの需要が増え続けています。
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」(2019年)では、2025年までに最大で約79万人のIT人材が不足する可能性が指摘されています。
SES(システムエンジニアリングサービス)は企業がプロジェクト単位でエンジニアを確保できる手段として活用され、特にシステム開発や運用保守、プロジェクト管理といった業務で多く利用されています。
SESの市場規模の推移
SES(システムエンジニアリングサービス)の市場規模は、IT業界全体の成長とともに拡大しています。
矢野経済研究所の「2022国内企業のIT投資実態と予測」によれば、2021年度の国内民間IT市場規模は約13兆5,500億円であり、2023年以降もテレワークの普及に伴い、基幹システムの刷新やクラウドサービスの導入が進むと予測されています。
このような背景から、SES市場も今後さらなる成長が期待されています。
SESエンジニアの需要と将来性
SES(システムエンジニアリングサービス)市場の拡大には、次の2つの要因があります。
・デジタル化(DX)の加速
・IT業界の人材不足
ここでは、それぞれの要因がSESの将来性にどう関わってくるかについて解説していきます。
・デジタル化(DX)の加速
最近では、デジタル化(DX)の進展が世界中で加速しており、日本でも同様の動きが見られます。
IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2023」によると、DXに取り組んでいる企業の割合は2021年度から2022年度にかけて約13%増加しています。
ですが、総務省が発表した「令和5年度版 情報通信白書」では、大企業の約25%と中小企業の約70%が未だにデジタル化に取り組んでいないと回答しています。
このことからも、DX化の動きはこれからも続くと予想され、SESエンジニアの需要は引き続き高まると見込まれます。
よくある質問(FAQ)
Q. SESに将来性はありますか?
A. はい。人材不足とIT投資の拡大が続いており、SESは企業の即戦力確保に欠かせない仕組みです。
Q. 「オワコン」と言われるのはなぜ?
A. 多重構造や評価制度が整っていない企業が一部存在するためです。環境を選べば十分に将来性があります。
多重構造についてはこちらの記事で解説しています。
Q. SESで将来性を高めるには?
A. クラウドや自動化などの成長領域にスキルを寄せ、評価を単価に反映できる環境を選ぶのがポイントです。
まとめ:SESの将来性は「選び方」で決まる
SESが“オワコン”と言われるのは一部の話で、実際には業界の需要は今も拡大中です。
SESは、エンジニア不足の解消やDX推進といった企業のニーズに応える形で、今後も需要が増えていくことが予想されます。
また、ホワイトSES企業の増加やリモートワークの普及により、働きやすい環境が整いつつあります。
伸びる分野にスキルを寄せ、評価される環境で働くことが、将来をつくる一番の近道です。
もし今の働き方に不安があるなら、活学キャリアに相談してみてください。
あなたの強みを整理し、安心して働けるキャリアプランを一緒に考えてくれます。

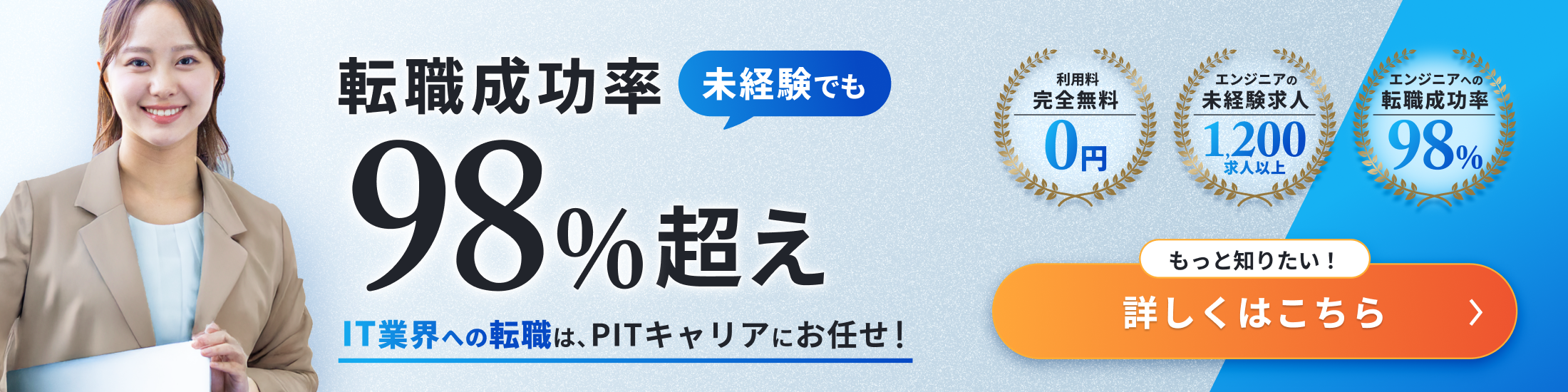
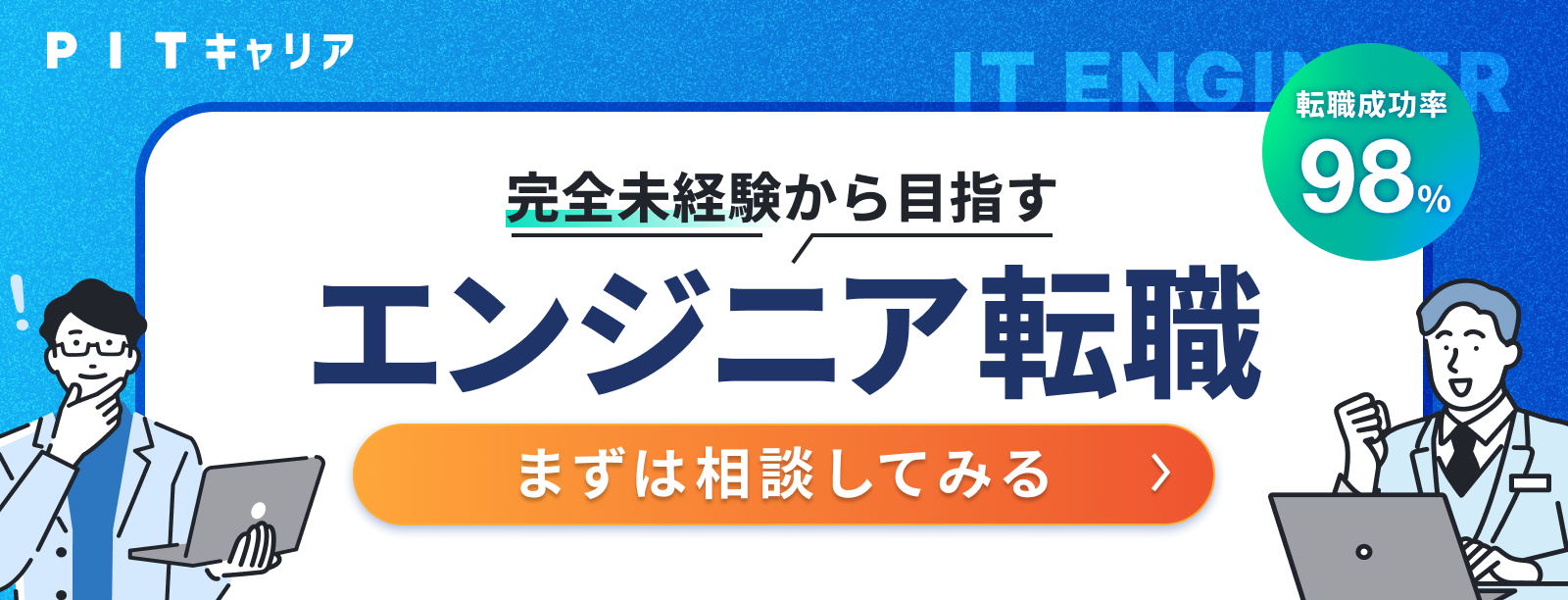
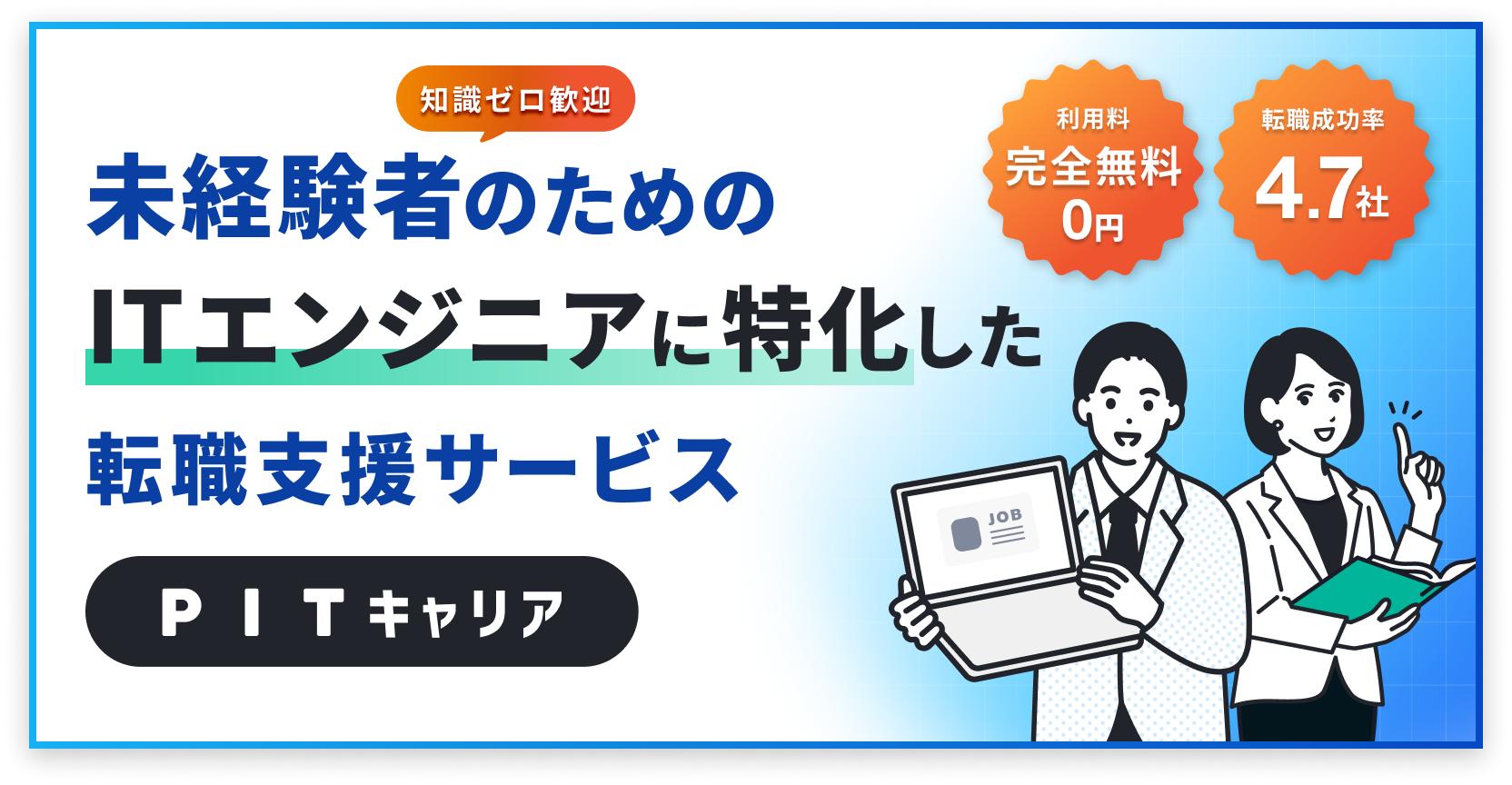


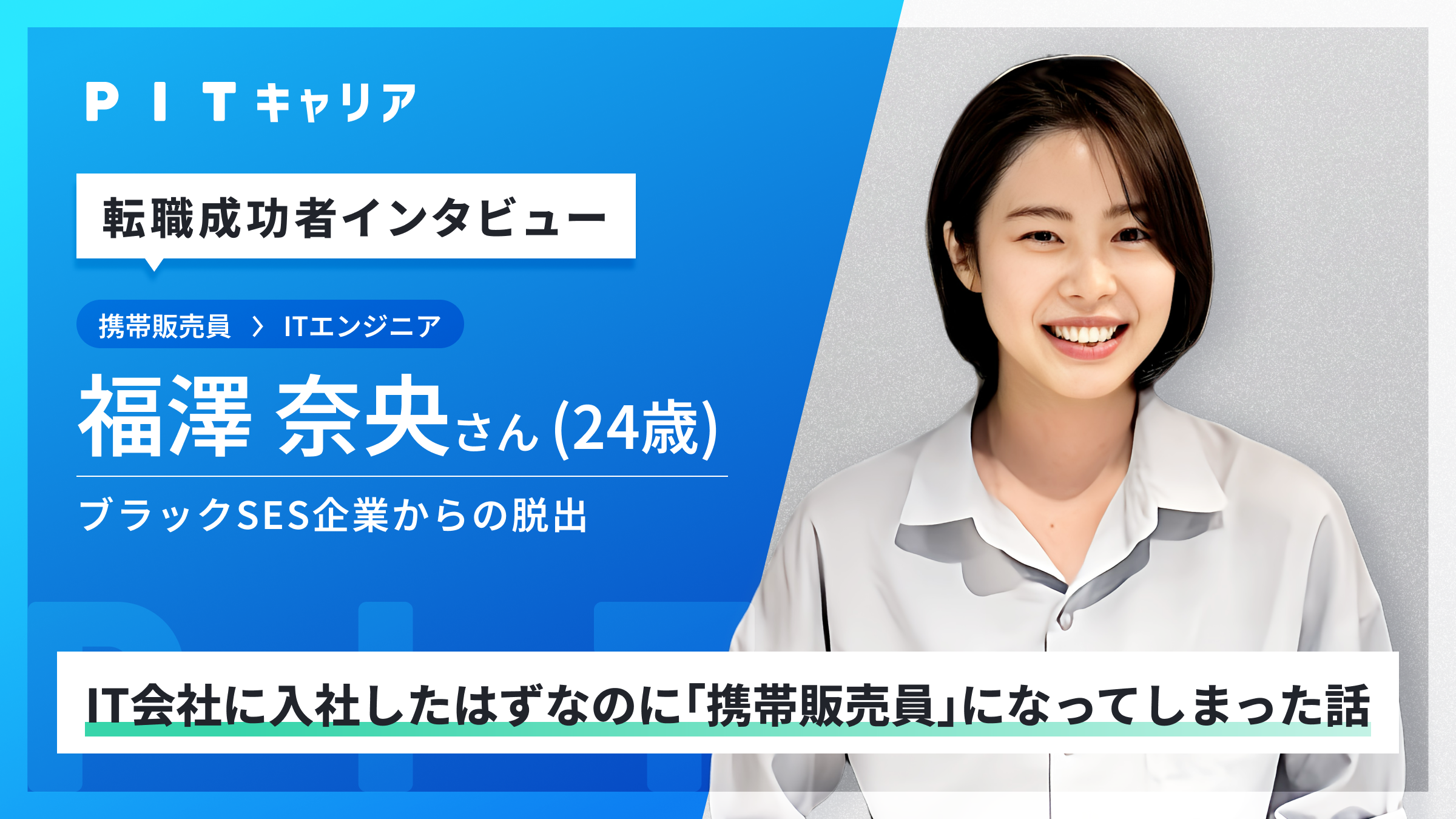


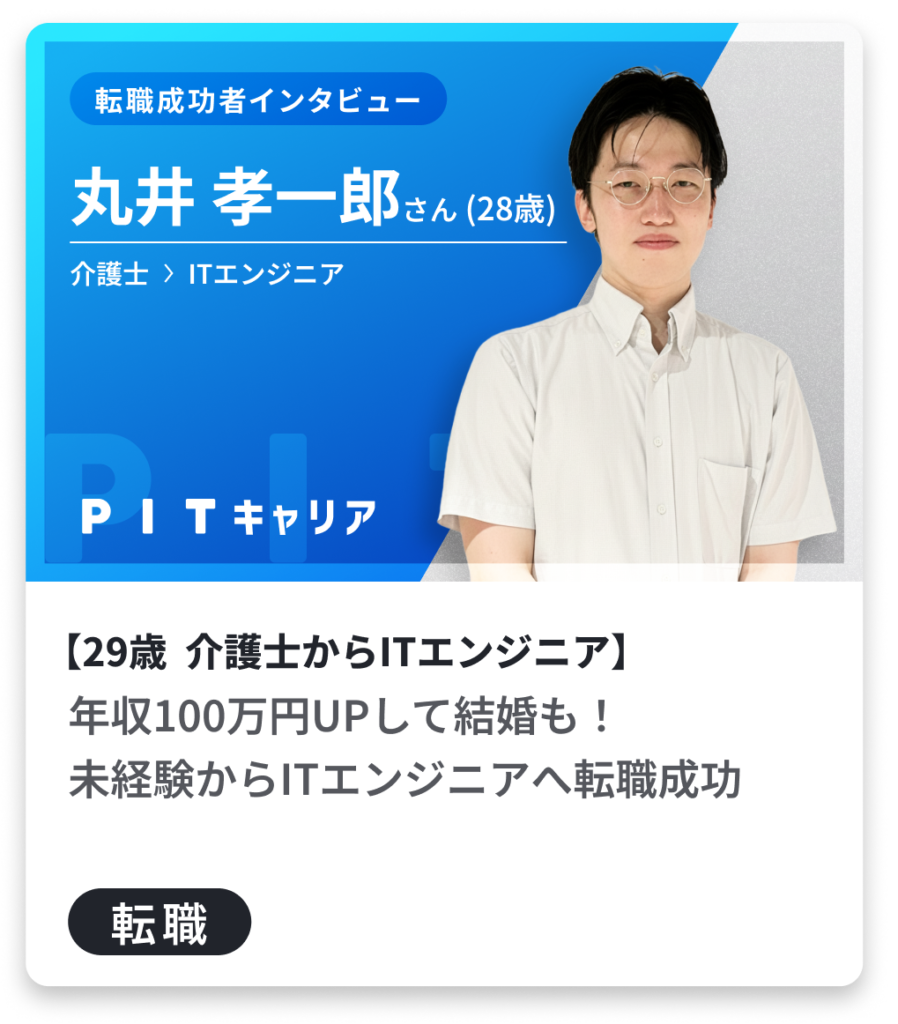
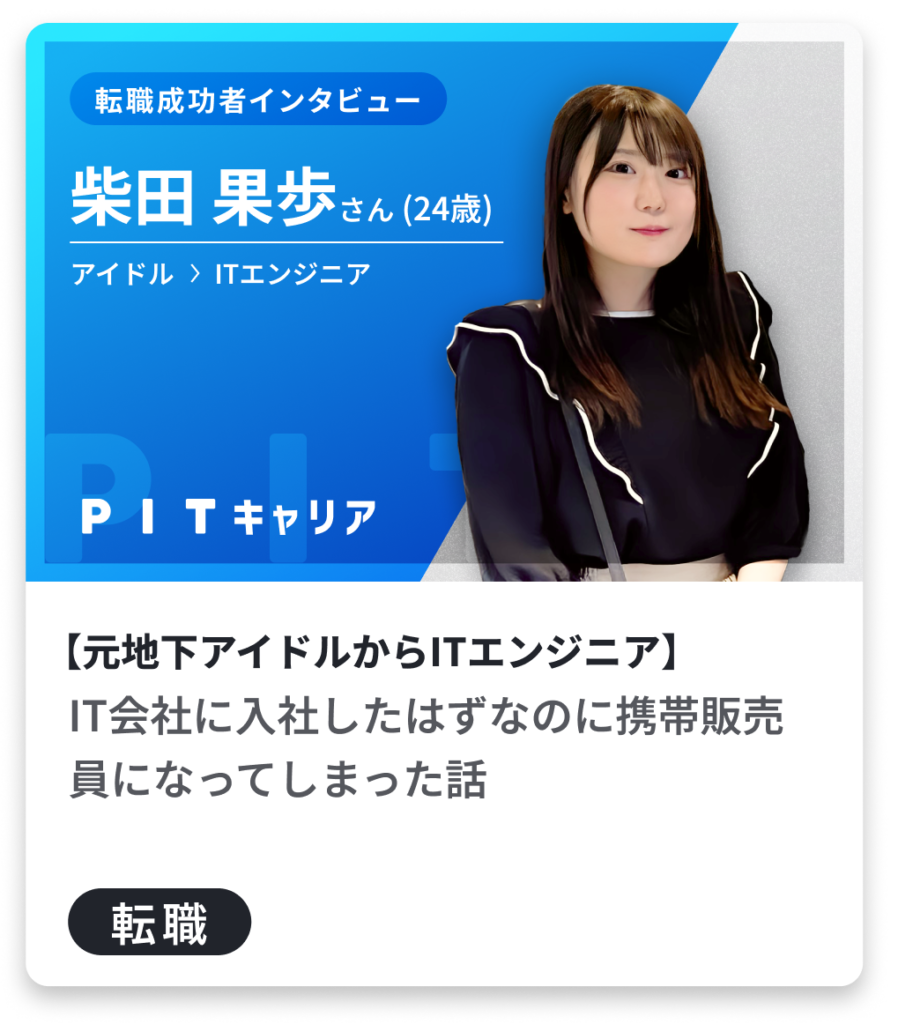
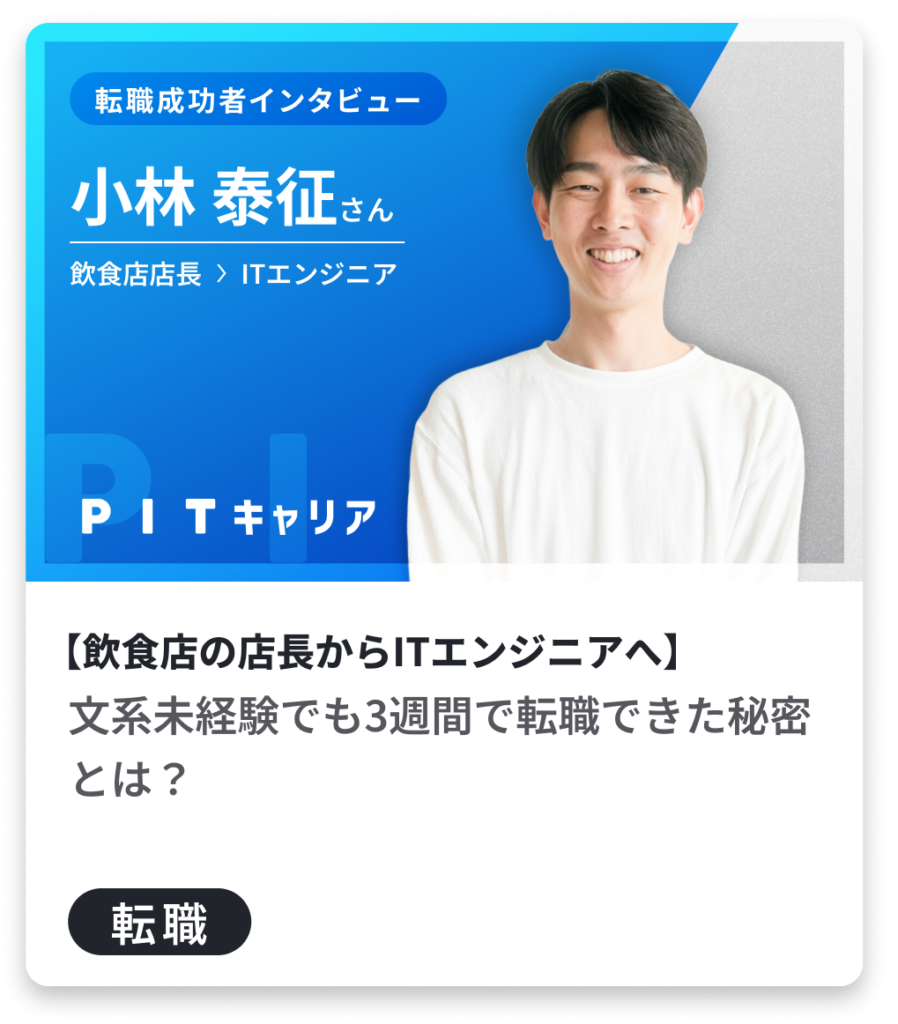

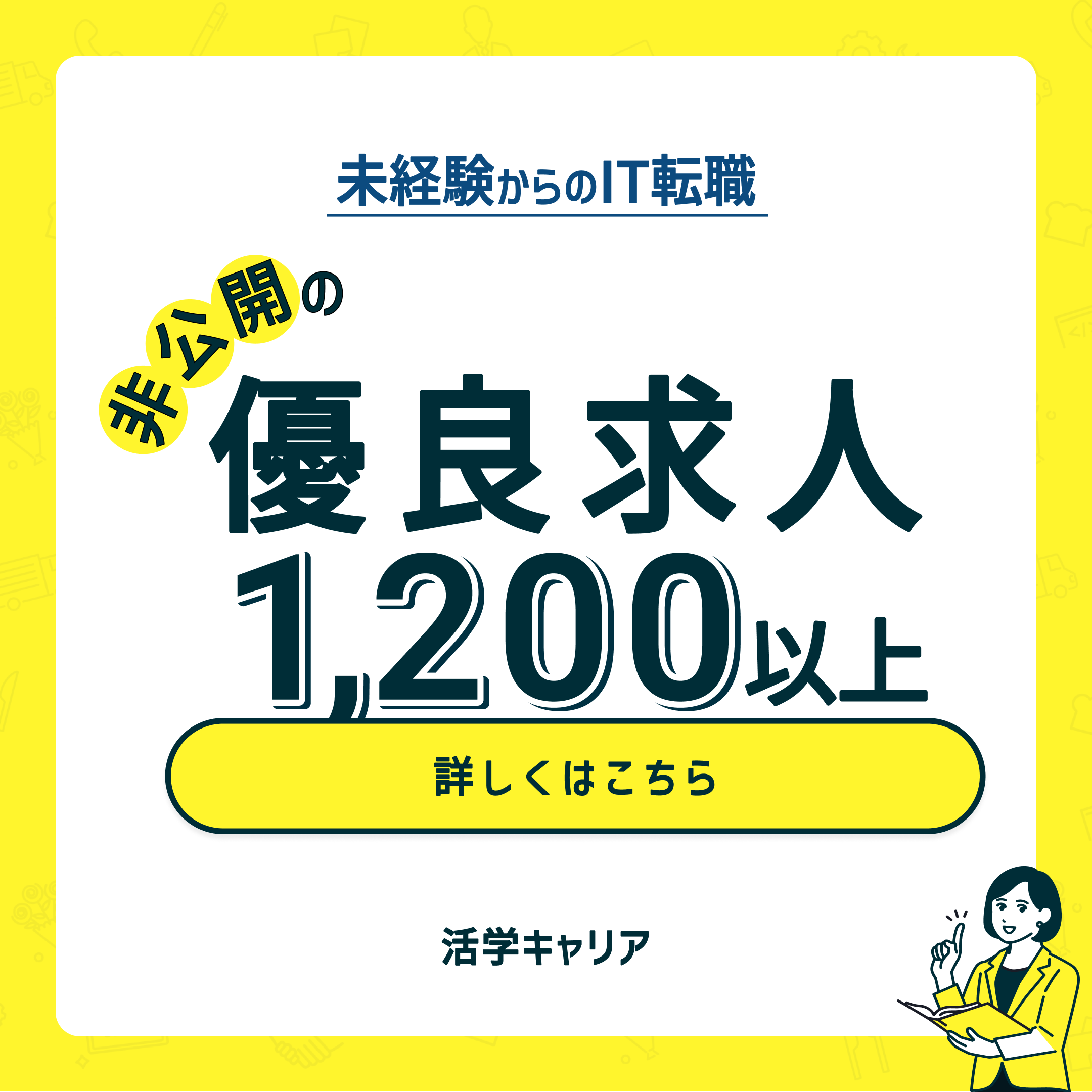

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
