カテゴリー
インフラエンジニアになるには?未経験から最短で目指すロードマップ
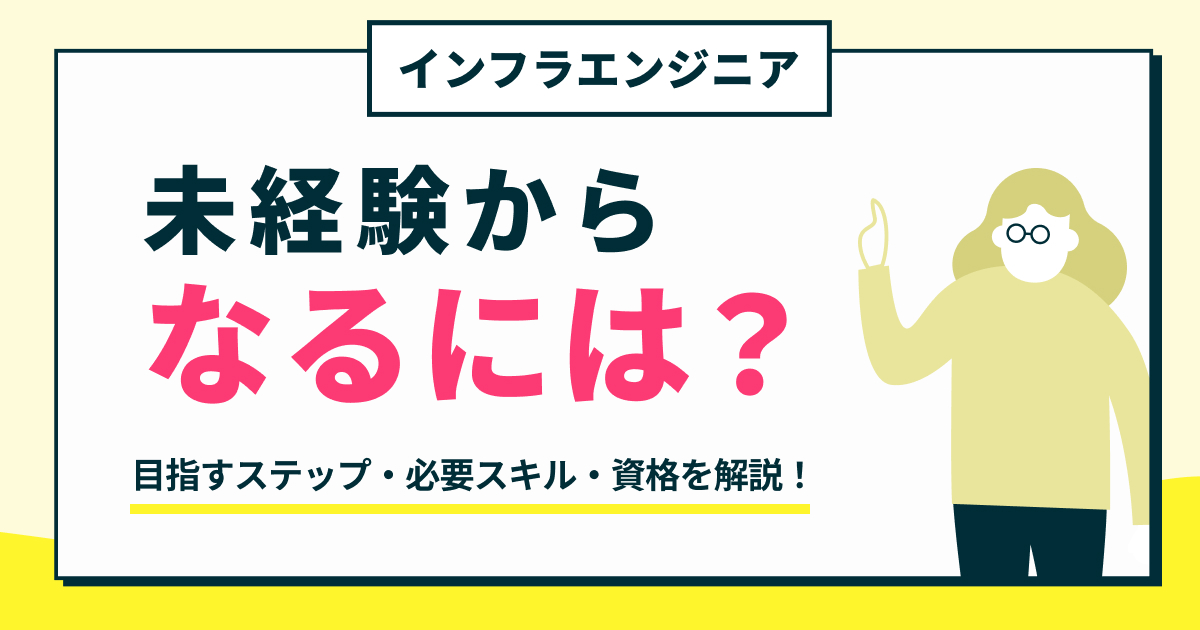

インフラエンジニアには、どうやったらなれるの?



まずは何をすればいい・・?
インフラエンジニアは、ITシステムの土台を支える重要な職種です。
近年ではクラウドの普及によりニーズが高まり、未経験からでも目指せるキャリアとして注目されています。
本記事では、インフラエンジニアになるには何から始めればよいのか?という疑問に答えるべく、必要なスキルや資格、学習ステップをわかりやすく解説します。
未経験からインフラエンジニアを目指す具体的なロードマップや体験談は、別記事で詳しく解説しています。
▶︎未経験からインフラエンジニアを目指すロードマップ完全版
インフラエンジニアを目指す前に知っておきたい基礎知識
インフラエンジニアを目指すなら、まずは業務の全体像を知っておくことが大切です。
自分がどんな役割を担うのかを理解してから資格や学習を始めることで、効率的にスキルを身につけられます。
具体的な仕事内容や役割については、インフラエンジニアとは?仕事内容をわかりやすく解説の記事で詳しく紹介しています。
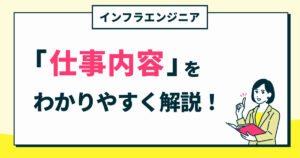
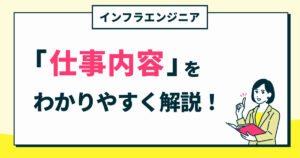
インフラエンジニアになるために求められる5つの要件
| 要件 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 基礎知識 | Linux操作・TCP/IP・クラウド基礎の理解 | 模擬環境や教材で基礎問題を解けるか |
| 資格取得 | CCNA・LPIC-1・AWS CLFなどでスキル証明 | 合格証や学習ログで確認可能 |
| 実践経験 | ラボ環境やハンズオンでの演習経験 | GitHubや学習ブログに記録 |
| 応募書類 | 志望動機・職務経歴書で意欲を示す | 応募書類を第三者にレビューしてもらう |
| 将来像 | キャリアパスや成長意欲を描けること | 面接で具体的に語れるか |
インフラエンジニアの職種・種類【目指す方向性を知ろう】
インフラエンジニアの仕事内容や職種の違いは、専用記事で図解しています。
ここでは概要のみ触れます。インフラエンジニアとは?仕事内容をわかりやすく解説
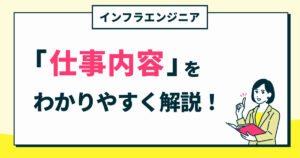
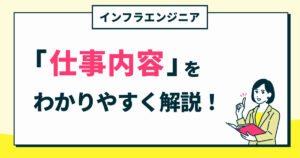
インフラエンジニアになるまでの5ステップ【未経験でも安心】
インフラエンジニアを目指すにあたって、「まず何から始めればいいのか」「どんな順序でスキルを身につけていけばよいのか」と悩む方も多いでしょう。
未経験からでも着実に成長できるよう、ここでは5つのステップに分けて解説します。
ひとつずつクリアしていくことで、自信を持ってインフラエンジニアとしてのキャリアをスタートできます。
- ①ITの基礎知識を身につける
- ②スキルを証明できる資格を取得する
- ③実践経験を積む
- ④キャリアパスを考慮して転職先を選ぶ
- ⑤転職後は、実務や個人学習を通じてさらなる成長を目指す
①ITの基礎知識を身につける
まずは「ITとは何か」という土台を固めることから始めましょう。
ネットワーク・サーバー・クラウド・OS・セキュリティといった、インフラ分野の基礎的な用語や仕組みを理解することが重要です。
おすすめの学習方法:
・ITパスポートなどの初級資格の学習
・書籍(『できるシリーズ』『スッキリわかる入門シリーズ』など)
・YouTubeやITスクールの無料コンテンツで動画学習
②スキルを証明できる資格を取得する
まずは基礎力を証明できる資格を1つ取得しましょう。
代表的なのはCCNA・LPIC-1・AWSクラウドプラクティショナーです。
これらは学習の目安になり、転職活動でも評価されます。
詳細な比較・難易度・学習方法は下記にまとめています。
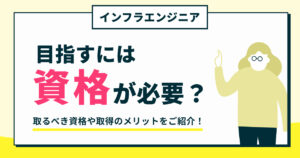
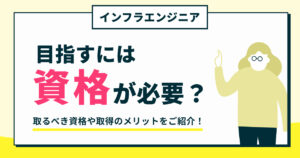
③実践経験を積む
資格を取ったあとは、実務に近い経験を積むことで自信とスキルを深めましょう。
実践経験の積み方:
・自宅に検証環境を作る(VirtualBoxなどで仮想サーバー構築)
・クラウド(AWS や GCP)で簡単なサーバー構築を体験する
・ITスクールやオンライン講座で実機演習
④キャリアパスを考慮して転職先を選ぶ
●未経験の場合
学習→資格→運用経験を経て設計・クラウドへ進む流れが一般的です。
詳細は以下記事にて詳しく解説しています。
●新卒の場合
学修実績や研究テーマを活かし、将来像を描いた志望動機を準備すると有利です。
●経験者の場合
運用経験から設計やクラウドへスキルシフトすることで、年収・裁量の拡大が可能です。
未経験者が自分ひとりで求人を選別するのは非常に難しいのも事実です。
企業の情報を読み解くにも専門的な視点が求められるため、「入ってみたら思っていた仕事と違った」というミスマッチも起こりがちです。
⑤転職後は、実務や個人学習を通じてさらなる成長を目指す
インフラ分野は技術進化が早く、学び続けることが求められます。
転職後こそ、「現場で覚える+継続的な学習」が成長のカギになります。
おすすめの取り組み:
・業務で扱った内容をノートやブログで記録・整理する
・興味のある技術(IaC、Docker、Kubernetesなど)を個人環境で試してみる
・資格のステップアップ(例:LinuC Level2 → Level3、AWS Associate → Professional)
また、同じ会社にとどまるだけでなく、2〜3年後により専門的な業務を扱う企業へ転職することも、キャリア形成の一環です。
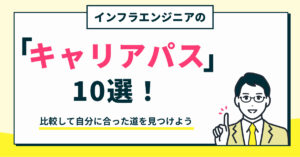
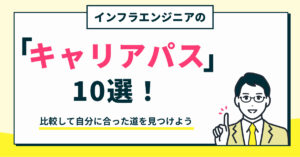
インフラエンジニアを目指す人によくある悩みとその解決策
未経験からインフラエンジニアを目指す方の多くが、「何から始めればいいの?」「自分にもできるのか不安…」といった悩みを抱えています。
この章では、そんなお悩みに対して具体的な解決策を紹介します。
- 何から始めればいいかわからない
- 文系・未経験でも本当に大丈夫?
- スキル不足が怖い…
何から始めればいいかわからない
未経験からインフラエンジニアを目指す場合、まず何から手をつけてよいか分からず、不安になる方も多いです。
まずは以下のような流れで進めていきましょう。
・ステップ1:ITの基礎知識を学ぶ(ネットワーク・サーバー・クラウドの仕組み)
・ステップ2:資格取得で知識を体系的に習得(CCNA、LinuCなど)
・ステップ3:仮想環境などで実践してみる
順序立てて取り組めば、未経験でもインフラの全体像を理解し、着実にスキルを身につけられます。
文系・未経験でも本当に大丈夫?
「文系出身だけどインフラエンジニアになれるの?」「理系じゃないと難しそう…」といった声もよく耳にしますが、結論から言えば、文系・未経験でも十分に目指せます。
実際、インフラエンジニアとして活躍している人の中には、文系出身者も多くいます。
求められるのは“論理的に物事を考える力”や“問題解決への粘り強さ”であり、学部や前職よりも「これから学ぼうとする意欲」のほうが重要視されます。
未経験から挑戦する場合は、以下のようなサポートを活用するとスムーズです:
・ITスクールや就職支援サービスの利用
・初学者向け資格の取得(例:ITパスポート、LinuC Lv1 など)
・実機やシミュレータを使ったハンズオン学習
「未経験だからこそ学べる柔軟性」があるというポジティブな視点で、まずは一歩踏み出してみましょう。
スキル不足が怖い…
「転職してから通用するか不安…」「技術に追いつけなかったらどうしよう」と、スキル面での不安を抱く人も多いでしょう。
確かにインフラ分野には、OS、ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど多岐にわたるスキルが存在します。
ただし、最初からすべてを完璧にこなす必要はありません。
むしろ、現場に入ってから学んでいくことが前提の職種です。
それでも不安な方は、以下のような準備をしておくことで自信につながります:
・基本的なLinux操作を覚えておく
・ネットワークの基礎(TCP/IPやサブネット)を学ぶ
・LPICやCCNAなどの資格学習に取り組む
また、実際の転職活動では「スキルよりも学習意欲や姿勢」を見られることも多いため、“今どんな勉強をしているか”を伝えられることが重要です。
もし「一人で学ぶのは不安…」「学習の順番がわからない…」という場合には、未経験特化のITスクールを活用するのも一つの方法です。
活学ITスクールでは、
・CCNAやLPICなど、インフラ系資格に特化したカリキュラム
・仮想環境を用いた実践型の学習
・経験豊富な講師による個別サポート
など、未経験者でも着実にスキルが身につく環境を整えています。
厚生労働省が認定した特定一般教育訓練給付制度あるいは一般教育訓練給付制度の対象なので、今なら条件に当てはまる場合、受講料の最大40%(講座によっては20%)の支給も受けられます。
今なら無料カウンセリングも受付中ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。
転職で失敗しないために意識すべきポイント
未経験からインフラエンジニアを目指す場合、やみくもに転職活動を始めるのは危険です。
せっかく学んだことを活かせなかったり、理想とかけ離れた職場環境に後悔するケースもあります。
ここでは、転職で後悔しないために意識したい5つのポイントを紹介します。
- 学習や実践の「成果」を具体的にアピールする
- 「どんなエンジニアになりたいか」の方向性を持つ
- 最初から理想の職場を求めすぎない
- 面接では「姿勢」と「自走力」が評価される
- IT業界に強い転職エージェントを活用する
学習や実践の「成果」を具体的にアピールする
未経験者は実務経験が少ないため、「どんなことを学んだか」「どう工夫して学習したか」をアピールしましょう。
難しいことをする必要はありません。
たとえば以下のような内容でも、立派な“成果”として評価されます。
・ITパスポートの勉強をして、ITの基本用語が理解できるようになった
・自分のパソコンにLinuxをインストールし、基本的なコマンド操作ができるようになった
・仮想環境(VirtualBoxなど)でサーバー構築の練習をした
「何を学び、どう成長したか」を自分の言葉で説明できるようにしておくと、面接で好印象につながります。
「どんなエンジニアになりたいか」の方向性を持つ
インフラエンジニアといっても、サーバー構築・ネットワーク運用・クラウドエンジニア・SREなど多様な分野があります。
自分が将来的にどの領域に進みたいかをある程度描いておくと、転職先の選定や面接での軸がぶれません。
方向性が定まっていない場合は、CCNAやLinuCなど幅広い基礎を学べる資格取得の過程で、自分の適性を見つけていくのも手です。
最初から理想の職場を求めすぎない
未経験でインフラエンジニアを目指す場合、最初から高年収・リモート・残業少なめの職場を求めるのは非現実的です。
最初は少しハードでも、学びながらステップアップできる環境を選ぶことが、結果的に早い成長につながります。
理想の職場は、経験を積んだ2社目・3社目で実現できるケースが多いです。
面接では「姿勢」と「自走力」が評価される
未経験者の面接では、「スキルの完成度」よりも、学ぶ姿勢と自発的に動ける力(自走力)が重視されます。
自己学習の進め方や、苦手な内容にどう向き合ったかを具体的に話せると好印象です。
例:
・「Linuxが難しかったが、毎日コマンドを1つずつ復習して習得した」
・「仮想環境がうまく構築できなかったので、複数の教材を組み合わせて独自に解決策を考えた」など
IT業界に強い転職エージェントを活用する
インフラエンジニアの求人は、ITに詳しくない一般的な転職エージェントでは、ミスマッチや説明不足が起きがちです。
インフラ分野に強いエージェントを選ぶことで、自分のスキル・希望に合った求人を紹介してもらいやすくなります。
特に、学習支援からキャリア支援まで一貫して行ってくれるエージェントなら、未経験者でも安心してチャレンジできます。
インフラエンジニアに必要なスキル10選【初心者にもわかりやすく解説】
インフラエンジニアを目指す上で、「どんなスキルが必要なのか」「初心者がどこから手を付ければいいのか」はよくある悩みです。
この章では、基礎から順に、インフラエンジニアに求められる主要なスキルをやさしく解説していきます。
- OSの知識(Linux/Windows Server)
- ネットワークの基礎知識
- クラウドの理解(AWS/Azure/GCP)
- 仮想化技術(VMware/KVM/VirtualBox)
- データベースの知識
- 監視・ログ管理のスキル
- スクリプト・自動化の知識(Shell/Pythonなど)
- セキュリティに関する基礎知識
- トラブルシューティング力
- ヒューマンスキル
OSの知識(Linux/Windows Server)
サーバーを構築・運用するうえで、サーバーを動かすためのOS(オペレーティングシステム)の理解、操作は必須です。
現場では主に Linux系OS と Windows Server のどちらか、または両方を扱うケースが多くあります。
まずは、それぞれのOSの違いを以下の表で整理してみましょう。
| 項目 | Linux | Windows Server |
| 主な用途 | Webサーバー / クラウド / 開発環境 | 社内システム / ファイルサーバー |
| 操作方法 | コマンド中心 | マウス操作など中心 |
| 初心者のとっつきやすさ | 難易度高めだが習得すれば応用が利く | 比較的わかりやすく初心者向け |
| 学習環境の構築 | 仮想環境(VirtualBoxなど)で自由に試せる | 評価版を使用して自宅PCでも構築可能 |
| 代表的な機能・知識 | ユーザー管理、ファイル操作、パーミッション | 共有フォルダ、ドメイン管理 |
未経験の方は、仮想環境(VirtualBoxなど)でLinuxの練習から始めるのがおすすめです。
私自身も最初は「ls」や「cd」の意味すら分からず、コマンド1つでエラーが出て慌てたことがあります。
ただ、繰り返し手を動かすことで、1週間ほどで「何が起きているか」が読めるようになり、ログを見るのが楽しくなってきました。初心者こそ“動かしながら覚える”ことが成長への近道です。
ネットワークの基礎知識
インフラエンジニアにとって、ネットワークの仕組みを理解することは避けて通れません。
「通信ってどうやって届いてるの?」「IPアドレスって何?」といった素朴な疑問に答えられるようになることが第一歩です。
以下に初心者が押さえておきたいことをまとめておきます。
| 項目 | 説明 |
| IPアドレス | インターネット上の“住所”。機器ごとに割り当てられており、通信先を特定するために必要です。 |
| DNS(名前解決) | 「ドメイン名→IPアドレス」に変換するしくみ。URLを打つだけで通信できるのはDNSのおかげです。 |
| ルーター・スイッチ | ネットワーク機器。ルーターは外とつなぐ、スイッチは社内のPC同士をつなぐ役割。 |
| TCP/IP | ネットワーク通信のルール(プロトコル)。インターネットの土台となる基本中の基本です。 |
| ping / tracertコマンド | 通信が届いているかを確認するための簡単な診断コマンド。初心者でも使いやすいネットワーク確認ツール。 |
「ネットワークって難しそう…」と思いがちですが、イメージをつかむところから始めれば大丈夫です。
たとえば、パケットの流れを図解で確認したり、自分のPCでpingを打ってみたりするだけでも、理解が深まります。
クラウドの理解(AWS/Azure/GCP)
最近のインフラエンジニアには、クラウドの基本的な理解が求められる場面が増えています。
手元にある物理サーバーを自分で操作する時代から、インターネット経由で遠方のネットワーク上にあるサーバーやストレージを借りる時代へと変化しているからです。
初心者が押さえるべき3つの代表的クラウドサービス
| サービス名 | 説明 | 運営企業 |
| AWS | 世界No.1シェアのクラウド。サービス数が豊富で、企業の導入実績も多数。 | Amazon |
| Azure | Microsoft製。Windowsサーバーとの親和性が高く、Office製品との連携も◎。 | Microsoft |
| GCP | Googleのクラウド。AI・ビッグデータ系に強み。エンジニア向けの機能も充実。 |
初心者の方は、まずAWSの「無料利用枠」を使って、仮想サーバーを立ててみるのがおすすめです。
サーバーの起動や停止、セキュリティ設定など、現場で役立つ操作感が身につきます。
仮想化技術(VMware/KVM/VirtualBox)
インフラエンジニアを目指すうえで、仮想化の基本を知っておくことはとても重要です。
「仮想化」とは、1台のパソコンの中に「何台ものパソコン」を作るようなイメージです。
これにより、用意するコンピューターの台数が少なく済むので、運用コストを下げることができます。
代表的な仮想化ソフトには次のものがあります。
| 仮想化ソフト名 | 特徴 | 対象・用途 |
| VMware | 実務でよく使われる有料ソフト。安定性が高く、企業でも多く導入されている。 | 商用利用・実務寄り |
| KVM | Linuxに標準搭載されている仮想化機能。コマンド操作が中心で、やや上級者向け。 | Linuxサーバーの仮想化に使われる |
| VirtualBox | 無料で使える初心者向け仮想化ソフト。個人の学習用途でよく使われている。 | 学習用・個人開発向け |
初心者の方は、VirtualBoxを使って、Linuxサーバーを立ち上げてみるとよいでしょう。
データベースの知識
インフラエンジニアといえば「サーバーやネットワーク」のイメージが強いかもしれませんが、実はデータベース(DB)の基本も重要です。
なぜなら、多くのシステムは「データ」を保存・検索・更新する仕組み(データベース)を使って動いているからです。
たとえば「社員の情報」「商品の在庫」「注文履歴」などを一元管理できます。
よく使われるデータベースの種類は次の通りです。
| 種類 | 特徴 | 代表例 |
| リレーショナルDB(RDB) | 表形式でデータを管理。SQLという言語で操作する。 | MySQL、PostgreSQL、Oracle |
| NoSQL | 柔軟なデータ構造を持ち、大量のデータを高速に処理できる。 | MongoDB、Redis |
初心者の方は、書籍やWeb教材を使って、簡単なSQL文(SELECT, INSERT, UPDATEなど)を学んでみてください。
監視・ログ管理のスキル
システムが「正常に動いているか」「トラブルが起きていないか」を常に見守るのも、インフラエンジニアの大切な役割です。
そのために欠かせないのが「監視」と「ログ(記録)管理」のスキルです。
代表的な監視対象
| 監視するもの | 例 |
| 死活監視 | サーバーが動いているかどうか |
| リソース監視 | CPU・メモリ・ディスクの使用率など |
| サービス監視 | WebサーバーやDBサーバーが応答しているか |
| ログ監視 | エラーや警告が記録されていないか |
初心者の方は、Linuxの基本的なログの見方などを学んでおくとよいでしょう。
スクリプト・自動化の知識(Shell/Pythonなど)
インフラエンジニアの仕事は、「何度も繰り返す作業」が多くあります。
その作業を自動化することで、ミスを減らし、作業効率を大きく高めることができます。
この自動化に使われるのが、「スクリプト」と呼ばれる簡易的なプログラムです。
よく使われる言語
| 言語 | 特徴 | 初心者おすすめ度 |
| Shell | Linuxに標準搭載。コマンドを組み合わせて手軽に使える | ★★★★★ |
| Python | 可読性が高く、インフラ以外の分野でも活用できる | ★★★★☆ |
| PowerShell | Windowsサーバーの操作に強い | ★★★☆☆ |
「Shellスクリプト」から始めるのがおすすめです。
Linuxの基本操作とあわせて覚えると理解が深まります。
セキュリティに関する基礎知識
どれだけ高性能なサーバーを構築しても、セキュリティが甘いとすぐに脅威にさらされてしまうため、基本的なセキュリティ知識は必須です。
セキュリティの知識は、サーバーやネットワークの知識を学ぶ中である程度身につけることができますが、その他にIPAや日系クロステックなどで、セキュリティに関するニュースを1日1つ読む習慣をつけると効果的です。
トラブルシューティング力
トラブルシューティングとは、サーバーやネットワークで問題(サーバーに接続できない、Webページが表示されないなど)が起きたときに、原因を見つけて解決する力のことです。
インフラエンジニアにとっては、日常的に求められるスキルであり、現場では「とりあえず直せる人」がとても重宝されます。
初心者が身につけるべき考え方
・原因を一つ一つ切り分ける
・ログを見る癖をつける
・自分で直せたら、どう解決したかメモに残す
おすすめの練習法
・Linuxの仮想環境であえてサービスを止め、復旧手順を練習する
・ping、traceroute、netstat などのネットワーク系コマンドに慣れる
やはりサーバーやネットワークについて学ぶ中で、地道に身につけていくのがよいでしょう。
ヒューマンスキル
インフラエンジニアに限らず、現場で働く上で欠かせないのがヒューマンスキルですが、特にインフラ分野では、チームでの連携や、他部署との調整が多く発生するため、技術力と同じくらい重要といっても過言ではありません。
次のような場面でこのスキルが求められます。
| シーン | 求められるスキル |
| 障害発生時 | チームへの状況共有・報告の正確さ |
| 作業前の調整 | 他部署(開発、セキュリティチームなど)とのやりとり |
| 手順書作成 | 誰が読んでも理解できる明確な記述力 |
| メール・チャット対応 | ビジネスマナー+端的で丁寧な表現 |
多くの企業では、特に初心者に対しては、技術スキルよりも“学ぶ姿勢”や“協調性”を重視する傾向があります。
・「わからないことを素直に聞ける」
・「作業を振り返って改善できる」
・「まわりと協力して取り組める」
こうした姿勢は、どんな現場でも通用する武器になります。
インフラエンジニアに資格は必要?持っていると有利な理由
インフラエンジニアになるために資格は必須ではありません。
しかし、転職やキャリアアップの場面では「基礎知識がある」「即戦力として育成しやすい」と判断されやすく、資格を持っていることで有利に働きます。
どの資格を優先的に取得すべきかは、インフラエンジニア資格まとめの記事で詳しく解説しています。
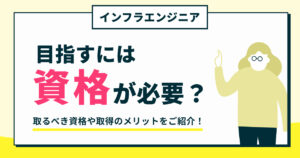
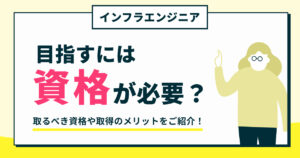
インフラエンジニアを目指す際に学習が必要な理由と学び方の選択肢
インフラエンジニアは実務で学ぶことも多いですが、基礎知識がないと最初の転職や就職でつまずきやすい職種です。そのため、独学やスクールなどで事前に学んでおくことが大切です。
「どんな教材を選べばよいか」「独学とスクールの違いは?」といった具体的な勉強方法については、「インフラエンジニアの勉強法完全ガイド」で詳しく解説しています。
現役インフラエンジニアのリアルな声【働き方のイメージ】
実際にインフラエンジニアとして働いている人たちは、日々どんなことを感じているのでしょうか。
やりがいや難しさ、転職してよかったと感じる瞬間について、リアルな声をご紹介します。
- 「初めて任されたプロジェクトで成長を実感した瞬間」
- 「学習と実務の間にあるギャップ」
- 「キャリアチェンジで得られた安心感と成長実感」
初めて任されたプロジェクトで成長を実感した瞬間
入社して数か月後、初めて小さなサーバー構築を一人で任されました。
最初は不安でしたが、資格勉強で学んだ知識を活かしながら作業を進め、無事にリリースできたとき「自分にもできる」と強い自信につながりました。
実務を通じて得た達成感は、勉強だけでは得られない大きな成長のきっかけになりました。
インフラエンジニアのやりがいについてはインフラエンジニアのやりがいで詳しく解説しています。
「学習と実務の間にあるギャップ」
・現場で飛び交う専門用語が最初は理解できなかった。
・構築手順や手配業務など、経験して初めてわかる“現場ならでは”の作法に戸惑った。
・「聞いたことはあるけど触ったことがない」技術が多く、実機演習の大切さを痛感。
現場に出てからの“キャッチアップ力”が求められる点は、どのインフラエンジニアも共通の課題です。
「キャリアチェンジで得られた安心感と成長実感」
・前職よりも手に職がつき、将来に対する安心感が得られた。
・技術を磨けばキャリアアップできる明確な道筋が見えた。
・チームで問題を解決するやりがいや、技術の奥深さを知ることができた。
「未経験からでもチャレンジしてよかった」と話す方が多く、継続的な学習意欲があれば、着実に成長できる職種であることがうかがえます。
さらに詳しく知りたい方は、ぜひこちらの転職体験談もご覧ください。
インフラエンジニアになるには…よくある質問
最後に、インフラエンジニアを目指すうえで、よく寄せられる不安や疑問にお答えします。
転職前に気になるポイントをここで解消しておきましょう。
Q.プログラミングができなくても大丈夫?
はい、大丈夫です。
インフラエンジニアは、主にネットワークやサーバー、クラウドの構築・運用を行う職種です。
プログラミングスキルが求められる場面もありますが、未経験者がいきなり高度なコードを書ける必要はありません。
まずは「コマンド操作」や「ネットワークの仕組み」など、インフラ系の基本を理解することが優先です。
学習を進める中で、自動化やスクリプト(簡単なプログラム)に触れるようになったタイミングでプログラミングも徐々に身につけていけば問題ありません。
Q.年齢がネックになることはありますか?
30代以上であっても、インフラエンジニアを目指す方は多数います。
年齢よりも「学ぶ姿勢」と「今後の伸びしろ」を評価する企業が増えており、未経験からでも十分チャンスはあります。
特に、前職での社会人経験や対人スキルが評価されやすい点もインフラ系の特徴です。
実際、活学ITスクールでも20代後半〜30代前半でインフラエンジニアを目指す方が多く、転職成功事例も多数あります。
Q.転職活動は在職中でも進められますか?
はい、在職中でも無理なく転職活動を進めることは可能です。
特に未経験からインフラエンジニアを目指す場合は、事前準備や学習にある程度の時間がかかるため、在職中から少しずつ動き始めるのが理想的です。
また、転職エージェントを活用することで、求人紹介や面接日程の調整などもスムーズになります。
学習と転職支援をセットで受けられる「活学キャリア」のようなサービスを利用すれば、在職中でも効率よく進められるでしょう。
まとめ:インフラエンジニアになるには準備が何よりも大事!
インフラエンジニアは、ITインフラを支える“縁の下の力持ち”的な存在。
だからこそ、確かな知識と着実な準備が求められます。
未経験からでも、正しい学習ステップを踏み、必要なスキルや資格を身につけていけば、必ずチャンスをつかめます。
・まずは ITの基礎知識 を身につける
・転職活動の方向性 を明確にする
・一人で不安なら ITスクールや転職エージェントの力を借りる
不安があるのは当然です。
しかし、動き出せば必ず景色は変わります。ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。

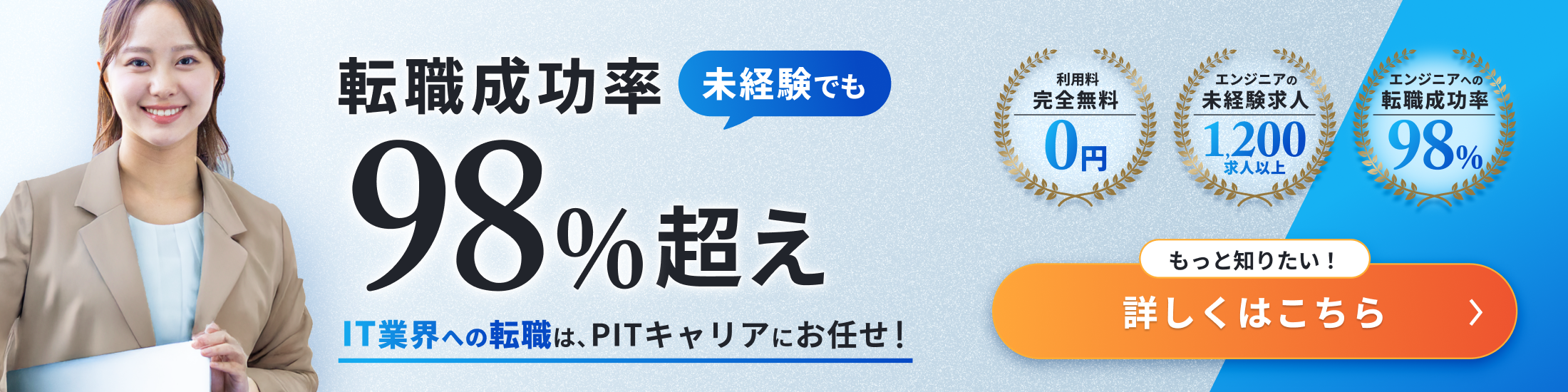
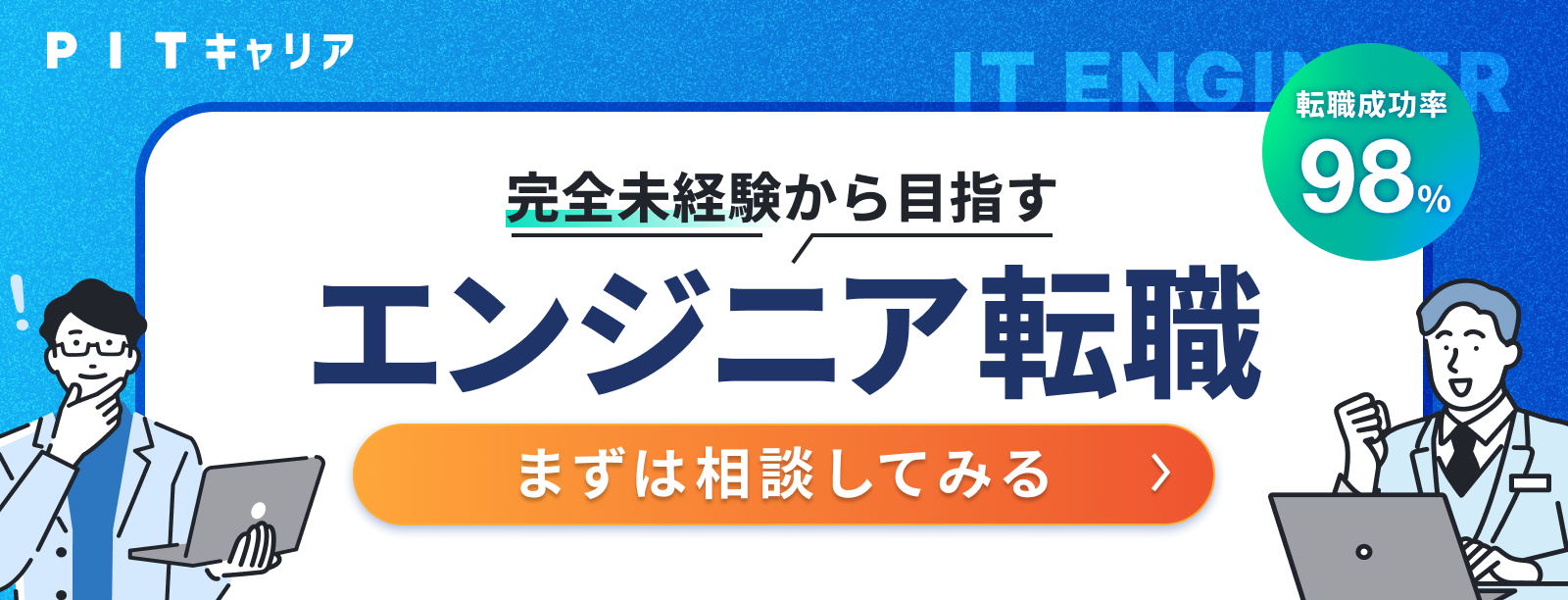
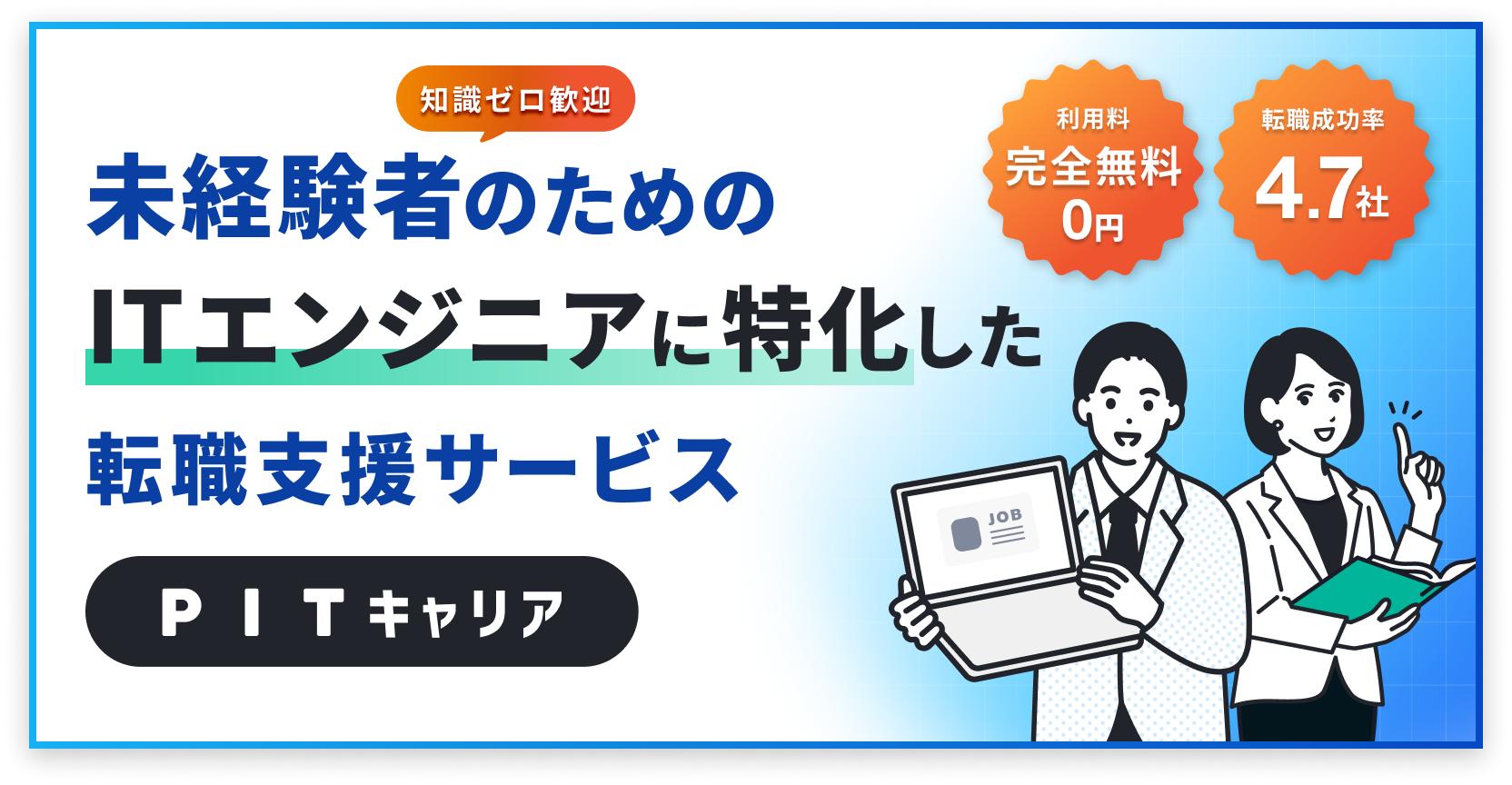
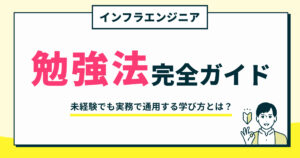
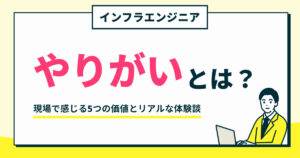



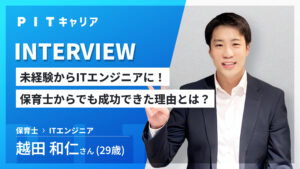



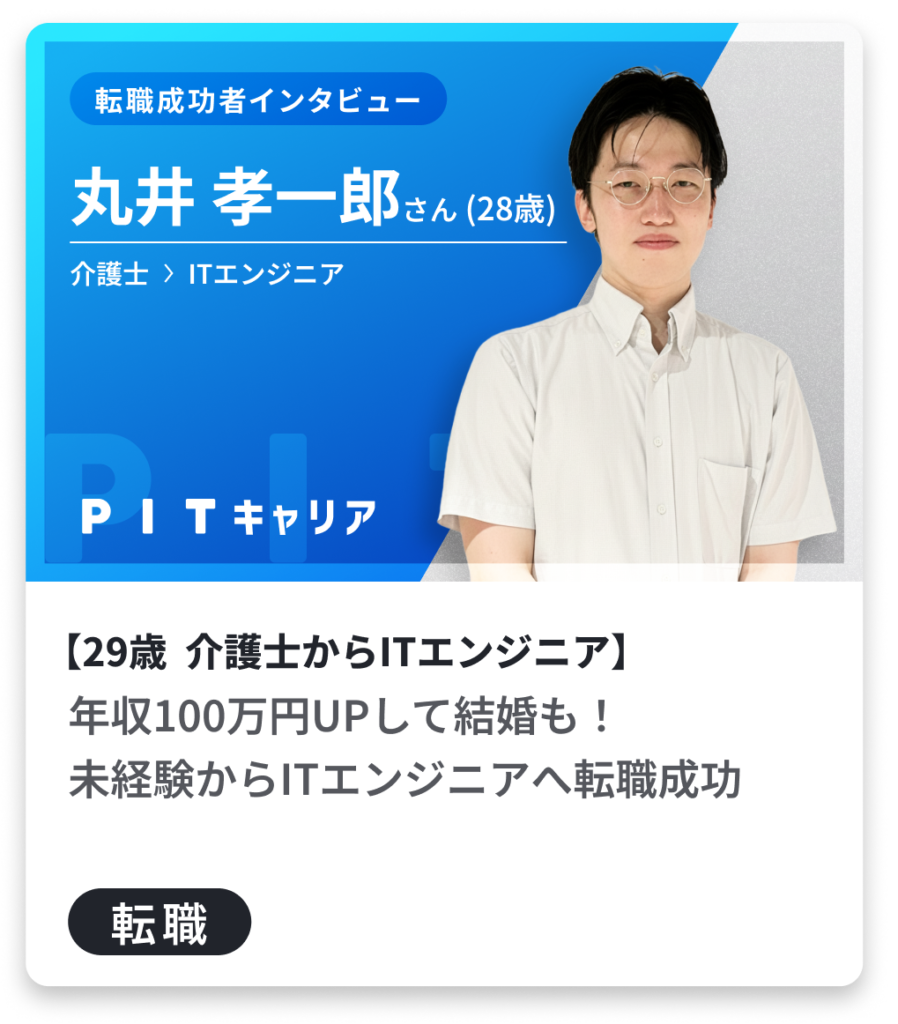
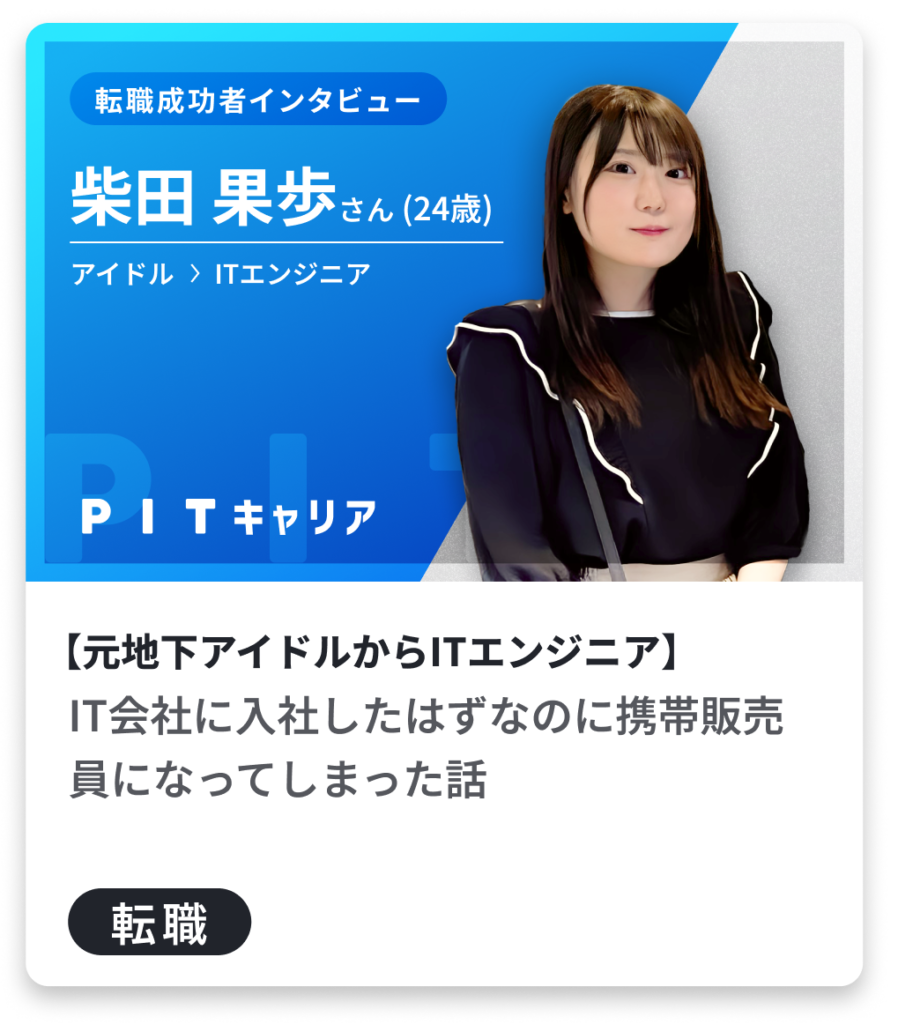
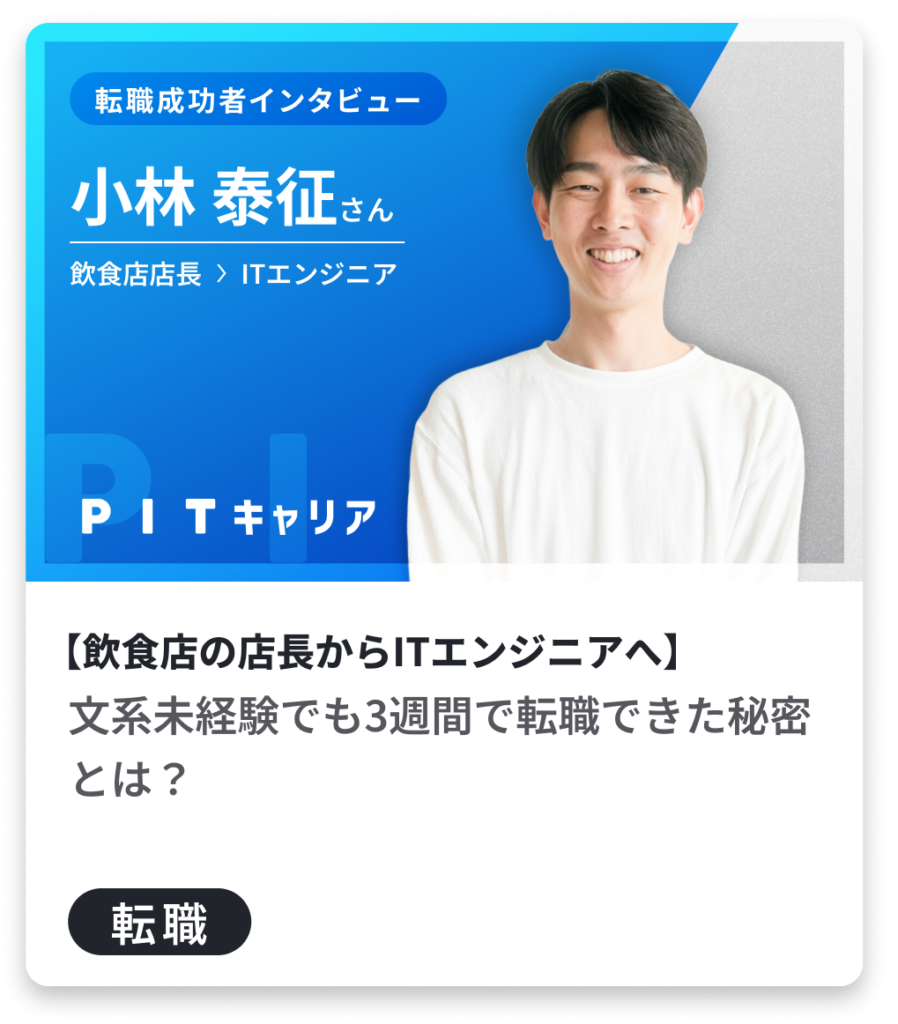

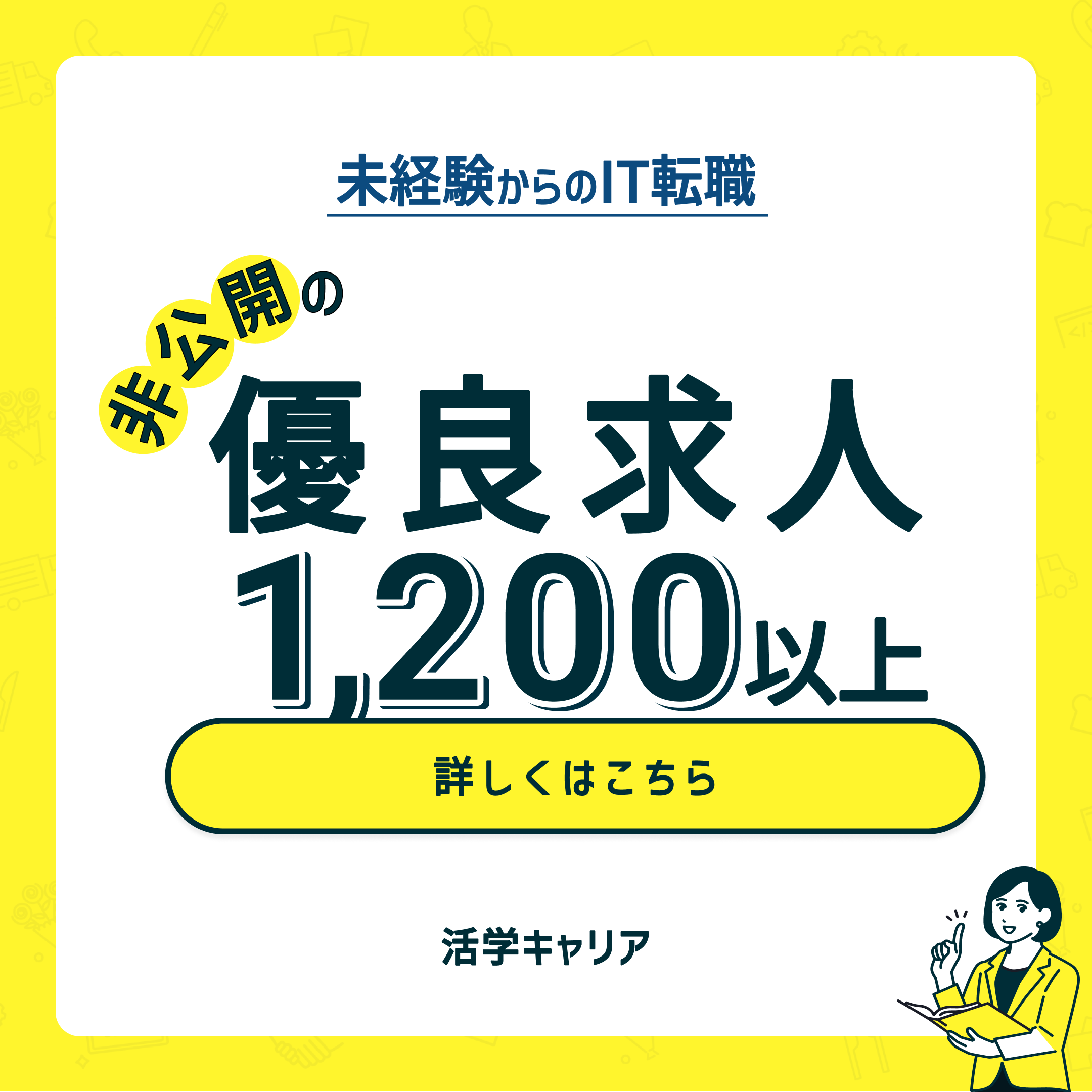

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
