カテゴリー
インフラエンジニアがきついといわれる9つの理由と乗り越えるメリット
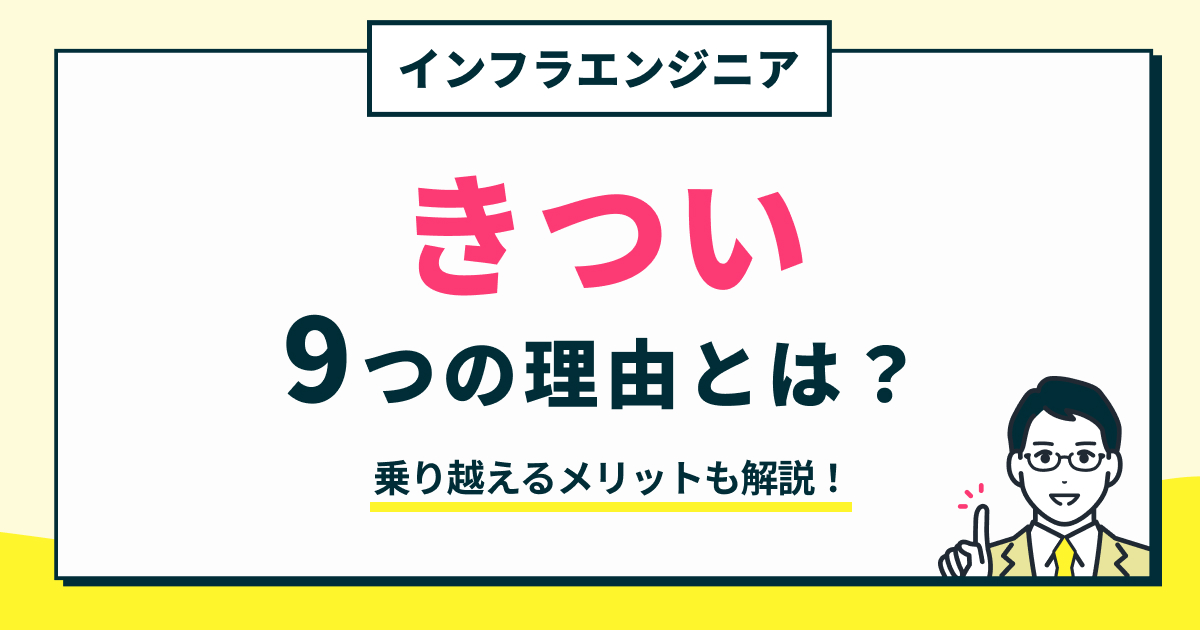

インフラエンジニアはきついって聞いたけど・・
インフラエンジニアは確かにハードな一面もありますが、それだけで敬遠してしまうにはもったいない仕事です。



筆者自身もインフラエンジニアとしてキャリアをスタートし、夜間対応や急なトラブル対応で苦労したこともありましたが、だからこそ得られたスキルや達成感も大きかったと感じています。
本記事では、インフラエンジニアが「きつい」と言われる理由を正しく理解したうえで、仕事の魅力やきつい面の乗り越え方まで解説します。
- インフラエンジニアがきついと言われる理由
- それでもインフラエンジニアを目指すべき理由
- インフラエンジニアの「きつい」を乗り越えるためには
きつい一面だけでなく、この仕事ならではのやりがいも知っておくと、より前向きにキャリアを描けます。
インフラエンジニアという仕事の“本当の実態”を知りたいなら、さまざまな現場の内情を把握している転職エージェントの話を聞くのが一番確実です。
転職エージェント「活学キャリア」はこれまでに多くの方々をインフラエージェントデビューさせてきました。
サポートを受けて入社した98%の方が、今も現場で活躍を続けています。
本記事でも後で紹介しますが、実は「転職先をしっかり選ぶこと」こそが、インフラエンジニアとして無理なく働くための最大のカギです。
もし少しでもインフラエンジニアの仕事にご興味があるなら、まずは【活学キャリア】の無料カウンセリングをお気軽にご利用ください。
現場を熟知したアドバイザーが、あなたの不安や疑問にしっかりお答えします。
インフラエンジニアがきついといわれる9つの理由
大切なのは、インフラエンジニアの仕事が「きつい」と言われる理由を正しく理解し、自分に合った働き方やキャリアの選択をしていくことです。
ここでは、インフラエンジニアがきついと言われる主な9つの理由について、実情とともに解説します。
- 地味・単調な作業が多い
- 夜勤・シフト勤務の現実と体調管理術
- 急なトラブル対応による精神的負担
- きつい作業環境
- 技術の進化が速く、学び続ける必要がある
- ドキュメントが不十分な現場もある
- トラブル対応によるプレッシャー
- 短納期での構築依頼もある
- 成果が見えにくく評価されにくい
ネガティブな面を理解したうえで、将来どう成長していけるかを知ることも大切です。
地味・単調な作業が多い
インフラエンジニアの仕事は、「目立たないけれど必要不可欠」な作業の連続です。
特に運用・保守フェーズでは、ログ監視やトラブル対応、定期点検など、同じ作業を毎日繰り返すことも多く、やりがいを見失いがちです。



筆者自身も、最初は単調な作業に対して「この仕事に意味があるのか?」と感じることがありました。
ですが、ある時ふと、トラブルがまったく起きていない日常こそが、自分の仕事の成果なのだと気づき、そこから意識が変わりました。
裏方だからこそ「トラブルを未然に防ぐ」ことに価値があり、そこにプロとしての誇りを持つ人も多くいます。
夜勤・シフト勤務の現実と体調管理術
システムは24時間365日稼働しているため、インフラエンジニアには夜勤やシフト勤務が必要な現場もあります。
とくに運用保守系の業務では、深夜の監視や障害対応が避けられない場合も多く、生活リズムが崩れることで心身の負担を感じやすくなります。



私もキャリア初期、夜勤のある現場で勤務しており、睡眠不足や体調不良に悩まされたことがありました。
ただ、深夜帯は比較的トラブルが少なく、空き時間を自己学習や資格勉強にあてられることも多かったため、スキルアップのきっかけにもなりました。
また、深夜手当が加算されるため、同じ時間働くよりも収入が増えるというメリットもあります。
とはいえ、生活リズムが合わない人にとっては負担が大きくなりやすいため、長期的には夜勤なしの現場や日勤中心のポジションを選ぶことも視野に入れると良いでしょう。
最近は夜勤なしで働ける求人も増えており、ライフスタイルに合った働き方を選べる可能性は十分にあります。
▶︎後悔談も含めた体験は、インフラエンジニアになって後悔する理由を参考にしてください。
急なトラブル対応による精神的負担
「いつ何が起きるか分からない」のがインフラの世界。
システム障害やサーバーダウンなど、急なトラブル対応が発生すると、帰宅直前でも残業や休日出勤が求められます。
精神的にも時間的にも余裕がなくなるため、常に冷静な判断力と対応力が求められる仕事です。



帰ろうとした矢先に監視アラートが鳴り、終電ギリギリまで復旧対応に追われた経験があります。
トラブル対応中はプレッシャーも大きいですが、無事に復旧できたときの達成感や「ありがとう」の一言が支えになる場面もありました。
トラブルがあるからこそ、インフラの存在意義が実感できる―そんな瞬間があるのも、この仕事のリアルです。
実際に後悔したケースやその背景は、インフラエンジニアになって後悔する理由で紹介しています。
きつい作業環境
データセンターでの作業や、サーバールームでの配線・設置など、物理的に厳しい環境での作業もあります。
室温が極端に低かったり、スペースが狭かったり、重い機材を持ち運ぶなど、体力的にきついと感じる場面も少なくありません。



私も新人時代、真冬のデータセンターで凍えるような環境の中、長時間ラック内で作業をしたことがあり、そのときは正直「この仕事、続けられるかな」と思ったこともあります。
ただ、防寒対策を工夫したり、作業の合間に温かい飲み物で体を温めたりすることで、なんとか乗り切ることができました。
こうした現場経験を経て得られたスキルや、現場でしか見えない視点は、今のキャリアにしっかりとつながっています。
筆者も、すべての現場がこのような環境というわけではありません。
最近では物理的な作業が減ってリモート対応が増えてきている現場も多く、働き方改革の影響もあり、交代制やシフトの整備など、働きやすさを意識した改善を図る企業も確実に増えてきています。
技術の進化が速く、学び続ける必要がある
インフラ分野は、クラウド、自動化など、次々に新しい技術が登場する世界です。
少し油断すると知識がすぐに古くなってしまい、「いつまでも勉強が必要」と感じる人にとっては負担になることもあります。



私も、オンプレミス中心の現場からクラウドへと技術が大きく移行するタイミングで、学び直しを迫られた経験があります。
当時は正直プレッシャーもありましたが、新しい技術を習得することで選べる仕事の幅が広がり、キャリアの可能性が一気に広がった実感もありました。
好奇心を持って学び続けられる人にとっては、大きなやりがいを感じられる分野です。
ドキュメントが不十分な現場もある
本来であれば、設計書や構成図、手順書がしっかり整備されているべきですが、現実には「前任者の頭の中だけ」という属人化した現場も少なくありません。
そのため、調査や確認に時間がかかり、作業効率が落ちたり、ミスが起きやすくなることもあります。



初めて入った現場でマニュアルが一切なく、「ケーブル1本抜くのにも確認が必要」という状況に直面したことがあります。
最初は戸惑いましたが、何が分かっていて何が分からないのかを整理し、少しずつ構成をドキュメント化していくことで、現場の信頼を得ることができました。
逆境も乗り越え方次第では、現場の中心的な存在になれるチャンスです。
トラブル対応によるプレッシャー
インフラのトラブルは、会社全体の業務やサービスに大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、障害時にはプレッシャーが非常に強く、短時間で冷静かつ正確な判断が求められる状況に直面します。



あるシステム障害でサービスが全面停止し、関係各所から連絡が鳴り止まない中、復旧作業の判断を一手に任された経験があります。
あのときの緊張感は今でも忘れられませんが、後に「よくやってくれた」と評価されたことで、自信にもつながりました。
人によっては「責任の重さ」に耐えきれず、精神的なストレスを感じることもありますが、対応を重ねることで冷静さと判断力が磨かれ、技術者としての成長を実感できる場面でもあります。
短納期での構築依頼もある
「この日までにサーバーを構築してほしい」「急ぎで環境を用意してほしい」といった、無理のあるスケジュールで仕事を振られることもあります。
準備不足のまま本番作業に入らざるを得ないこともあり、時間に追われてミスを誘発するリスクも高まります。
こうした場面では、交渉力やタスク管理のスキルが特に求められます。



筆者も初期の頃、短納期の案件で連日の徹夜作業を経験しました。
当時はスケジュール調整の難しさを痛感し、無理な依頼に対しては適切に上司やクライアントと交渉する重要性を学びました。
成果が見えにくく評価されにくい
インフラエンジニアは「トラブルが起きなかった=仕事がうまくいっている」職種です。
逆に言えば、何も起こらなければ成果が見えにくく、評価されにくいという側面があります。
営業や開発のように「目に見える成果」がない分、モチベーションの維持が難しいと感じる人も少なくありません。



筆者も、トラブルがなかった日々が続くと「自分の仕事は本当に役に立っているのか」と感じることがありました。
しかし、そうした日常の積み重ねこそがシステムの安定稼働を支えていると理解し、自己評価を見直すことでモチベーションを保てるようになりました。
きついはずのインフラエンジニアを目指すべき9つの理由
「大変そう」「激務では?」といった声がある一方で、インフラエンジニアを勧める声も多数あります。
筆者も実際にインフラエンジニアには多くの目指すべき理由があると考えます。
ここでは、その理由を9つご紹介します。
- 社会インフラを支えるやりがい
- 堅実なスキルが身につく
- 学歴によらない
- 高収入を目指せる
- 需要が高く、安定している
- 一人で集中して作業ができる
- 大手で働くチャンスがある
- 将来のキャリアパスが広い
- 知れば知るほど奥深く、仕組みを作る面白さがある
インフラエンジニアのやりがいについては、こちらの記事でも特集しています。
社会インフラを支えるやりがい
ITインフラは、私たちの生活や社会活動の基盤となっています。
病院の電子カルテ、金融機関の決済システム、物流の管理システム、行政の各種サービス…これらすべてがスムーズに機能するのは、インフラエンジニアが裏側でシステムを支えているからこそです。



筆者自身も、ある医療機関のシステム運用を担当した際、日々の安定稼働が患者さんの命に直結していると強く実感しました。
社会の安全と発展に貢献している実感が得られるのが、何よりのやりがいです。
堅実なスキルが身につく
サーバー、ネットワーク、クラウド、セキュリティといったスキルは、IT業界全体で非常に需要が高く、どの分野に進んでも役立つ基礎技術です。



筆者自身も、最初はLinuxやネットワークの基礎からじっくり学び、そこからクラウドやセキュリティの分野へとキャリアを広げてきました。
これらのスキルがあったおかげで、転職や新しい技術習得もスムーズに進み、安定したキャリア形成につながっています。
未経験からインフラエンジニアを目指す方にとっても、こうした「普遍的なスキル」を身につけることは、将来の選択肢を大きく広げる大きなメリットと言えるでしょう。
学歴によらない
インフラエンジニアの世界は、実力主義が基本であり、大学名や学部よりも「何ができるか」が重視されます。
未経験であっても、資格取得や実務経験を着実に積み上げることで、確かなキャリアを築くことが十分に可能です。



筆者自身、大学院まで進学し、いわゆる「高学歴」と呼ばれる部類に入ります。
しかし、最初に配属された現場では、決して学歴が高くないメンバーのほうが、はるかに頼りにされていました。
技術的な知識やスキルもさることながら、障害対応時の冷静な判断力、困難な状況でも周囲を落ち着かせる姿勢、そういったものに心底感銘を受けました。
彼から多くのことを学び、エンジニアとして成長するきっかけを得られたと思っています。
高収入を目指せる
年収500万~700万円を超えることも十分可能です。
特にクラウドやセキュリティなどの分野に強いインフラエンジニアは需要が高く、フリーランスとして独立したり、外資系企業で働くことで年収1,000万円超えを目指すことも夢ではありません。
スキルと実績次第で、大きな収入アップが見込める職種です。
インフラエンジニアの年収については次の記事もご参照ください。
需要が高く、安定している
デジタル化やクラウド移行の加速により、インフラエンジニアを含むITインフラ人材のニーズは年々高まっています。
経済産業省の報告によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足する可能性があるとされています。
特にインフラを支える技術者は「土台」として不可欠であり、今後も安定した需要が見込まれています。
出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」(2020年、みずほ情報総研)
一人で集中して作業ができる
インフラエンジニアの仕事は、トラブル対応の緊急時を除けば、黙々とサーバーやネットワークの構築・設定に集中する時間が多いのが特徴です。
一人でじっくり手を動かして技術を磨きたい人にとっては、非常に適した環境と言えます。
もちろん、チームメンバーや関連部署との連携や報告など、コミュニケーションも重要ですが、日常の評価はやはり技術力や問題解決能力が大きくものを言います。
技術的な成果や知識が評価されやすいので、コミュニケーションが苦手でも努力次第で活躍できるのがこの職種の魅力の一つです。



私も初めはコミュニケーションに自信がなかったものの、技術面で認められることで次第に自信がつき、チームの信頼も得られるようになりました。
大手で働くチャンスがある
インフラエンジニアは、多くの大手企業にとって必要不可欠な存在です。
特に、自社で大規模なシステム基盤を持つ企業 、たとえば、データセンター運営企業や通信キャリア、金融機関などでは、安定稼働を担うインフラエンジニアのニーズが常にあります。
こうした企業では、求められるセキュリティの水準が高く、社会的な影響も大きいプロジェクトに関わることが多いため、やりがいも抜群です。
実際に、キャリアを積んでスキルを磨いて、NTTグループ、KDDI、富士通、NEC、楽天グループ、メガバンク、外資系クラウドベンダー(AWS、Google Cloud など)といった有名企業に転職する人も少なくありません。
将来のキャリアパスが広い
インフラエンジニアとしての構築や運用の経験は、IT業界において非常に価値の高いスキルです。
これを基盤に、以下のような多様なキャリアパスを目指すことが可能です。
- ・クラウドエンジニア(AWS、GCP、Azureなど)
-
クラウドサービスの設計・構築・運用を担当し、企業のデジタルトランスフォーメーションを推進する役割です。インフラの基礎知識がクラウド技術の理解を加速させます。
- ・セキュリティエンジニア
-
ネットワークやシステムの脆弱性を見つけ出し、対策を講じることで企業の情報資産を守ります。
インフラの知識がセキュリティ対策の根幹となるため、相性の良い分野です。 - ・インフラアーキテクト
-
システム全体のインフラ設計を担い、最適な構成を考案します。
技術だけでなく、設計力やプロジェクトマネジメント能力も求められ、より上流工程で活躍できます。
これらに加え、プロジェクトマネージャーやチームリーダーといった管理職へのステップアップも可能であり、経験を積めば積むほど、年収や役職のアップも期待できます。
より詳しくは、次の記事をご覧ください。
知れば知るほど奥深く、仕組みを作る面白さがある
インフラの構築や運用は、一見地味で単調な作業に見えがちですが、実は「仕組みを作り上げる面白さ」が詰まった仕事です。
サーバー、ネットワーク、ストレージ、セキュリティなど、複数の技術を組み合わせて一つのシステムを形作るため、要求通りに全てが連動して動いた瞬間の達成感は非常に大きいものがあります。
また、インフラは技術が進化し続けているため、学べば学ぶほど深みが増し、常に新しい知識やスキルを身につけていく楽しさもあります。
こうした奥深さこそが、長く続けられる理由の一つであり、技術好きにはたまらない魅力と言えるでしょう。
インフラエンジニアの「きつい」を乗り越えるための7つのヒント
インフラエンジニアには「きつい」と言われる側面もありますが、働き方や意識の持ち方次第で大きく軽減できます。
以下の7つのヒントは、未経験者から経験者まで実践できる、実践的な対処法です。
- 自分の「向いている働き方」を知る
- チームで支える現場を選ぶ
- スキルアップを継続する
- 自動化・効率化を意識する
- 無理に合わない職場に留まらない
- メンターや先輩に相談できる環境を持つ
- 将来のキャリアを意識して働く
自分の「向いている働き方」を知る
夜勤や突発トラブル対応が苦にならない人もいれば、日中の構築作業や長期プロジェクトで力を発揮できる人もいます。
「覚えることが多すぎる」「トラブル原因がわからない」といった負荷も、得意な領域に寄せることで軽減可能です。



私自身、キャリア初期は夜勤や障害対応に苦手意識があり、体力的にも精神的にも消耗していました。
しかし、設計や構築といった計画的に進める業務に比重を移すことで、強みを活かしながら成果を出せるようになりました。
自分の特性に合った働き方を見極めることが、長く続けられるキャリアの鍵です。
チームで支える現場を選ぶ
特にキャリア初期は、「覚えることが多すぎて圧倒される」「トラブル原因がわからず手が止まる」といった壁に直面しがちです。
そんなとき、先輩や同僚に相談できるチーム体制の現場であれば、負荷を大きく減らせます。



私も最初の配属は、ベテランが横にいてくれる現場でした。
トラブル対応で詰まったとき、リアルタイムで原因の切り分け方や調査のコツを教えてもらえたおかげで、独学より何倍も早く成長できました。
「一人で抱え込まない環境」を選ぶことは、安心して経験を積むための大きな武器になります。
スキルアップを継続する
インフラエンジニアは、OSやネットワークの基礎だけでなく、クラウドやセキュリティなど新しい技術にも対応し続ける必要があります。
特にキャリア初期は「覚えることが多すぎて圧倒される」と感じますが、逆に言えば、少しずつでも学び続ければ着実に差がつけられる世界です。



新人時代は、日中は業務で手一杯でしたが、帰宅後や週末にLinuxの検証環境を作って試行錯誤しました。
当時は地味な努力に思えましたが、その知識が後にクラウド案件やセキュリティ強化プロジェクトに抜擢されるきっかけになりました。
「昨日より今日、今日より明日、少しでも成長する」—この積み重ねが、長く活躍できる土台になります。
自動化・効率化を意識する
インフラ業務には、毎日・毎週繰り返すルーティン作業が多くあります。
これらを手作業で続けると時間も労力も大きく消耗してしまいがちです。
そこで鍵となるのが、単純作業を自動で行い効率化する「自動化」です。



私が最初に自動化したのは、数十サイト分のサーバ証明書の有効期限チェック。
以前は毎日1時間かけて手動で確認していましたが、スクリプト化して自動実行することで、作業時間は1/10に短縮。
ヒューマンエラーもゼロになりました。
自動化は小さな作業からでも始められ、積み重ねれば業務負担を大幅に軽減できます。
無理に合わない職場に留まらない
職場によっては、残業過多・人間関係・慢性的な人手不足など、個人の努力では解決できない問題があります。



筆者自身も最初の配属先で、夜勤やトラブル対応が頻繁にある環境に苦しみました。
しかし思い切って異動や転職を検討し、夜勤なしで設計中心の職場に移ったことで、心身の負担が劇的に軽減されました。
無理に合わない環境にとどまることは、長期的なキャリア形成を考えたらマイナスです。
自分に合った職場を見極め、必要なら環境を変える勇気も大切です。
メンターや先輩に相談できる環境を持つ
インフラエンジニアは職場環境、トラブル対応や人間関係で悩むことも少なくありません。
そんなとき、社内の先輩や仲間だけでなく、社外のメンターやコミュニティなど相談できる環境があると心強いです。



新人時代は、社内の先輩に加え、勉強会やオンラインコミュニティで知り合ったメンターに相談し、技術面だけでなく精神的な支えも得られました。
こうした多方面の相談相手がいることで、孤立感が減り、成長スピードも上がります。
職場選びやキャリア形成の際は、社内外の相談環境を意識することも大切です。
「活学ITスクール」では、経験豊富な講師陣によるメンターサポートや、学習者同士のコミュニティを提供しており、ネットワークやサーバーに関する技術習得だけでなくキャリアや悩み相談もできる環境を整えています。
安心して学び、成長できる場としてぜひご活用ください。
ご興味のある方はぜひ無料カウンセリングをご利用ください。
将来のキャリアを意識して働く
目の前の業務に追われるだけでは、どうしてもモチベーションが低下してしまいます。
そんな時は、将来どの方向に進みたいかを意識しながら働くと、長期的なモチベーション維持や成長につながります。



新人時代、ただ与えられた仕事をこなすだけでなく、クラウドやセキュリティなど興味のある分野の知識を少しずつ増やし、将来的に専門性を高める計画を立てていました。
日々の仕事に加えて、自分の将来像を描きながらスキルアップを図ることが大切です。
ここまで7つのヒントを述べてきましたが、どんなに工夫や努力をしても、職場環境や業務内容が自分と根本的に合わない場合もあります。
その場合は無理に我慢を続けず、早めに転職という選択肢を検討することも大切です。
キャリアは一度きり。
自分に合った環境で力を発揮できる場所を見つけることが、長くエンジニアとして成長し続けるための近道になります。
自分に合った働き方、環境、そしてキャリアパスを意識することが、インフラエンジニアを長く続けて成功するための鍵ですが、未経験者がそれらを実現できる職場を自力で見つけるのは決して簡単ではありません。
そこでおすすめしたいのが、転職エージェント「活学キャリア」です。
「活学キャリア」はインフラ分野に精通した専門スタッフが、あなたの適性や希望に合った求人を丁寧に紹介。
職場の実態や雰囲気、働き方の特徴まで詳しく把握しているため、ミスマッチを防ぎやすいのが強みです。
さらに、面接対策やキャリア相談も充実しており、初めての転職でも安心して挑戦できます。
未経験からインフラエンジニアとしての第一歩を踏み出すなら、ぜひ「活学キャリア」の無料カウンセリングをご利用ください。
「きつい」とされるインフラエンジニア職を苦にしない人の5つの特徴
「インフラエンジニア=きつい」という声は確かに存在します。
しかし、同じ環境下でもそれを苦にせず、むしろ楽しんでいる人も少なくありません。
ここでは、インフラエンジニアの仕事に前向きに取り組める人に共通する5つの特徴を紹介します。
- トラブル発生時に“パズル感覚”で解決を楽しめる人
- 縁の下の力持ちでいることに誇りを持てる人
- 継続的な学習に抵抗がない人
- 勤務形態よりも「仕事そのものの面白さ」を重視できる人
- 何よりも高収入を目指したい人
インフラエンジニアに向いている人について詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてみてください。
トラブル発生時に“パズル感覚”で解決を楽しめる人
システム障害や設定ミスなど、インフラ業務には予期せぬトラブルがつきものです。
それを「面倒」と捉えるか、「どう解決すればうまくいくか」とゲーム感覚で楽しめるかで、ストレスの感じ方は大きく変わります。



初めて大きな障害対応に携わった際は非常に緊張しましたが、原因を一つ一つ論理的に解きほぐしていく過程にやりがいを感じ、次第に「問題解決のゲーム」に夢中になっていきました。
この感覚が持てると、トラブル対応も苦ではなくなり、むしろ成長の機会として楽しめるようになります。
縁の下の力持ちでいることに誇りを持てる人
インフラエンジニアの仕事は、システムの裏側で支える縁の下の力持ち的存在です。
そのため、直接お客様やユーザーから感謝される機会は少なく、成果が見えにくいこともあります。
しかし、自分の仕事が目立たなくても、人を支える役割に価値を見出せるタイプの人は、長くインフラの仕事に向き合うことができます。
表に出ない貢献こそが、チームやサービスを支えているという実感を持てる人は強いです。
継続的な学習に抵抗がない人
インフラ技術はクラウド、自動化、セキュリティなど、常に新しい技術が登場し続けるため、学び続ける姿勢が欠かせません。
学習を義務感でとらえると負担に感じやすいですが、「自分の成長の糧」として前向きに捉えられる人は、自然とスキルアップでき、仕事へのやりがいも増していきます。



私も、変化の激しい技術トレンドに最初は戸惑いながらも、学び続ける楽しさを実感し、モチベーションを維持できました。
このような姿勢があれば、長くインフラの仕事を続けられるでしょう。
勤務形態よりも「仕事そのものの面白さ」を重視できる人
インフラエンジニアの仕事は、夜勤やシフト勤務、休日対応など勤務形態の負担が大きいこともあります。



初期の頃は夜勤で体調を崩した経験がありますが、それ以上に「多様な技術を駆使してシステムを支える面白さ」に惹かれて続けてこられました。
勤務形態の負担を受け入れ、それ以上に仕事の内容や成長機会に価値を見出せる人は、困難な環境でもモチベーションを保ちやすく、長く活躍できます。
何よりも高収入を目指したい人
インフラエンジニアは専門スキルを磨くことで、高収入を狙いやすい職種の一つです。
特にクラウドやセキュリティなどの先端分野に強みを持つと、年収700万円以上やフリーランスでの高収入も十分可能です。



私の経験でも、スキルアップと資格取得を積み重ねた結果、給与面での大きな伸びを実感できました。
資格取得はおすすめです。
収入を最優先にキャリア設計をしたい方にとっては、インフラエンジニアは魅力的な選択肢と言えます。
インフラエンジニアの仕事が特にきついと感じる人の5つの特徴
インフラエンジニアの仕事は責任も大きく、適性によっては「きつい」と感じる瞬間があります。
ここでは、そう感じやすい人の特徴と、それを軽減する方法を紹介します。
- トラブル対応が極端に苦手な人
- 深夜や早朝の対応に抵抗がある人
- コツコツした作業に飽きやすい人
- チームでのやり取りが苦手な人
- 作業の目的や背景に関心を持てない人
トラブル対応が極端に苦手な人
インフラの現場では、障害対応や不具合の原因調査など、突発的なトラブルに対応する場面が少なくありません。
冷静に原因を切り分けたり、迅速な判断を求められる場面も多いため、「イレギュラーな事態が怖い」と感じる人には大きなストレスとなることがあります。
【改善ポイント】
小規模案件や障害対応の少ない現場から経験を積むことで、徐々に対応スキルを磨けます。
社内の先輩や外部コミュニティでロールプレイング形式のトラブルシュート練習をするのも効果的です。
深夜や早朝の対応に抵抗がある人
インフラエンジニアは、システムの保守やアップデート、障害対応の都合で、深夜帯や早朝に業務が発生することもあります。
たとえ日勤中心の勤務でも、オンコール対応(呼び出し)などで生活リズムが乱れる場面は少なからずあります。
生活の安定を最優先したい人にとっては大きなネックです。



私も夜間対応に苦労した経験がありますが、職場選びや勤務形態の調整で改善できるケースも多いため、無理せず自分に合った環境を探すことが重要です。
【改善ポイント】
夜勤やオンコールが少ないプロジェクトを選ぶ、もしくは設計・構築寄りのポジションにキャリアをシフトするのがおすすめです。
また、生活リズムを安定させるために、シフト前後の睡眠・食事のルーティンを整えることも効果的です。
生活リズムを保ちながら働きたい方は、夜勤のないインフラエンジニア求人の探し方も参考にしてください。
コツコツした作業に飽きやすい人
ログの確認、設定ファイルの管理、障害の再現テストなど、地味で細かな作業が日常的に発生します。
地道な積み重ねが非常に多い仕事なので、「飽きっぽい」「同じ作業に耐えられない」という人には向いていないことがあります。



筆者も最初は単調な作業に苦戦しましたが、効率化や自動化を意識し、やりがいを見出せる工夫を重ねることで乗り越えました。
【改善ポイント】
単調作業は自動化スクリプトやツールを導入して効率化しましょう。
自動化に挑戦することで、技術力が高まり、作業時間削減とスキルアップの両方を実現できます。
自動化や効率化のスキルは学び方次第で伸ばせます。
インフラエンジニア向けの勉強法で効率的にスキルアップしましょう。
チームでのやり取りが苦手な人
インフラ業務は、一人で黙々と作業するだけでは完結しません。
運用チームや開発チーム、時には外部ベンダーとも密に連携し、システム全体を安定稼働させる必要があります。
このため、日々の報連相や進捗共有、トラブル発生時の迅速な情報交換が欠かせません。
コミュニケーションが苦手な場合、情報の行き違いや認識のズレが起こりやすく、その結果としてトラブルが長引くこともあります。
「技術力だけで完結する仕事ではない」という点を理解し、人と関わるスキルも磨く姿勢が求められます。
【改善ポイント】
日々の進捗報告やトラブル発生時の連絡は、定型フォーマットを作っておくと負担が減ります。
社内チャットやドキュメント共有を活用し、口頭だけでなく文章でも情報を伝える習慣を身につけましょう。
作業の目的や背景に関心を持てない人
インフラエンジニアの仕事は、単なる手順の繰り返しだけでなく、その裏にあるシステム全体の目的や背景を理解することが重要です。
目的や全体像が見えないまま作業を続けると、単調に感じやすく、モチベーションが下がる原因になります。



筆者も初めの頃は、目の前の作業だけをこなしていましたが、全体の流れやなぜその作業が必要かを理解するよう意識を変えたことで、仕事の意味が見え、やりがいを感じられるようになりました。
【改善ポイント】
作業前に「この作業の目的は何か」「完了すると何が変わるのか」を簡単にメモする習慣をつけましょう。
背景を理解することで、作業の意義や全体像が見え、モチベーション維持につながります。
特にインフラエンジニアのキャリア初期においてきついこと
インフラエンジニアとして働き始めたばかりの頃は、想像以上に多くの壁に直面するものです。
扱う技術領域が広く、すべてが初めてのことばかりで、戸惑いや不安を感じるのは当然です。
本章では、筆者自身の経験も踏まえて「キャリア初期に特につらいと感じやすいポイント」と、その乗り越え方について解説します。
最初のつまずきは誰にでもあるもの。必要以上に落ち込まず、少しずつ前に進んでいくことが大切です。
- 覚えることが多すぎて圧倒される
- エラーやトラブルの原因がわからず手が止まる
- 「わかっている前提」で話が進みがち
覚えることが多すぎて圧倒される
OS、ネットワーク、クラウド、セキュリティ……と学ぶ範囲が広く、最初は混乱する人も多いです。
基礎知識がつくまでは、業務の一つ一つが重く感じられがちです。



「こんなに覚えられるのか?」と不安になることもありましたが、毎日少しずつ積み重ねることで、少しずつ知識が繋がっていきました。
効果的だったのが、「今の業務に必要な知識」から順に絞って学ぶこと。
たとえば、Linuxサーバーの設定作業を任されていた時期は、「とにかくLinuxとコマンド操作」に集中しました。
必要なタイミングで学ぶ方が、定着も早く無理がありません。
エラーやトラブルの原因がわからず手が止まる
インフラエンジニアのキャリア初期は、構築や運用の現場でエラーやトラブルに直面することが多くあります。
経験が浅いと原因の特定が難しく、どう対応すれば良いか分からずに作業が止まってしまうことも少なくありません。



筆者も最初は同じ壁にぶつかりましたが、先輩やメンターに相談しながらトラブルシューティングの方法を学び、徐々に自己解決力を身につけることで乗り越えました。
わからないことを放置せず、積極的に調べたり質問する姿勢が大切です。
「わかっている前提」で話が進みがち
インフラの現場では、業務のスピードが求められるため、先輩や同僚が専門用語を使いながら話を進めることがよくあります。
そのため、まだ経験が浅い段階ではついていけないことも少なくありません。



新人時代に戸惑った経験がありますが、わからないことを放置せず、積極的に質問し理解を深めることで、徐々に職場の会話についていけるようになりました。
疑問点をそのままにせず、自分から声を上げる姿勢が重要です。
キャリア初期においてきついことについて述べてきましたが、結局のところ、「環境選び」で負担が大きく変わります。
夜勤や常駐先が合わない場合は、早い段階で異動・転職を検討するのも方法の一つです。
インフラエンジニアのきつい体験談~どう乗り越えたか
ここではインフラエンジニア職できつい思いをしながらも乗り越えた方々の体験談を紹介します。
- 深夜のトラブル対応がつらかった
- 知識不足で周囲に迷惑をかけた
- 人間関係がうまくいかず、相談できる人がいなかった
自分がこの仕事に向いているかどうか気になる方は、以下の記事もチェックしてみてください。
深夜のトラブル対応がつらかった(20代/男性)
私は入社して間もない頃、深夜のトラブル対応が非常に辛く感じました。
システム障害が起きると、たとえ寝ていても呼び出され、慌ただしく現場に向かわなければなりません。
睡眠不足が続き、体力的にも精神的にも限界を感じていました。
しかし、先輩や同僚の支えを受けながら、トラブルの原因を素早く切り分けるスキルを少しずつ身につけることで、対応に余裕が生まれました。
また、職場のシフト調整や上司との相談で夜勤負担を軽減する働きかけを行い、自分の生活リズムを守る工夫もできるようになりました。
今では、夜間対応の頻度も減り、深夜の呼び出しも精神的なプレッシャーが軽くなりました。
当時は本当に大変でしたが、周囲のサポートや自分のスキルアップが乗り越える大きな力になったと感じています。
知識不足で周囲に迷惑をかけた(30代/女性)
入社当初は覚えることが多く、自分の知識不足で周囲に迷惑をかけてしまうことが何度もありました。
特にトラブル対応時に、何をどうすればいいのか分からず、先輩に助けを求める場面が多く、自信をなくしたこともあります。
しかし、そこで諦めずにコツコツと基礎から学び直し、先輩のアドバイスを素直に受け入れることで、徐々に自分で問題解決できるようになりました。
オンラインの勉強会やITスクールのサポートも活用し、知識と実務経験を積み重ねることで自信を取り戻しました。
今では後輩に教える立場にもなり、迷惑をかけた当時があったからこそ、人の気持ちに寄り添った指導ができると思っています。
人間関係がうまくいかず、相談できる人がいなかった(20代/男性)
入社当初からチーム内の人間関係になじめず、質問や相談すらしづらい雰囲気が続いていました。
業務の進め方も自己流になり、ミスが増えてしまう悪循環に。
次第に職場に行くこと自体が憂うつになっていきました。
「このまま続けても成長できない」と感じて転職を決意しましたが、どんな職場なら自分に合うのか、どう探せばいいのか分からず迷っていました。
そんなときに出会ったのが転職エージェントの活学キャリアです。
担当者は私のこれまでの経験や悩みを丁寧にヒアリングし、複数の職場を提案してくれました。
その中から選んだ今の職場では、先輩や同僚に加えて、活学キャリアを通じて知り合ったエンジニア仲間とも交流できるようになり、技術面でも精神面でも大きな支えを得られています。
環境が変わるだけで、モチベーションや成長スピードが大きく変わることを実感しました。
きついインフラエンジニアに関してよくある質問
最後にインフラエンジニアの仕事についてのよくある質問にお答えします。
- どのくらいで仕事に慣れる?
- 夜勤や休日対応はどのくらいある?
- スキルアップすればきつくなくなる?
どのくらいで仕事に慣れる?
インフラエンジニアとして仕事に慣れるまでの期間は個人差がありますが、一般的には6か月から1年程度が目安とされています。
基礎知識の習得や日常業務の流れを理解し、トラブル対応の経験を積むことで徐々に自信がついてきます。



筆者の経験では、最初の数か月はわからないことが多く戸惑うことも多いですが、周囲のサポートや継続的な学習を通じて、1年ほどで自立して動けるようになりました。
焦らず、一歩ずつ着実にスキルを積み重ねることが大切です。
夜勤や休日対応はどのくらいある?
夜勤や休日対応の頻度は、配属されるプロジェクトや業種によって大きく異なります。
24時間365日稼働するシステムを扱う現場では、シフト勤務や夜間の障害対応が発生することが多く、深夜や休日に呼び出されるケースもあります。
特に運用保守のフェーズではこうした対応が避けられません。
一方で、クラウド中心の環境や設計・構築フェーズに進むと、日勤のみで働ける職場も増えています。
最近では、夜勤なしやリモート勤務可能な求人も増加傾向にあるため、自分の働き方に合った職場を選ぶことが重要です。
未経験者が自分の希望に合った職場を見つけるのは簡単ではありませんが、転職エージェント「活学キャリア」なら、あなたのライフスタイルや希望条件を丁寧にヒアリング。
シフトや勤務時間、働き方の柔軟性まで詳しく把握した求人情報をもとに、無理なく長く続けられる職場を紹介してくれます。
また、現場のリアルな状況を熟知したスタッフがフォローしてくれるため、入社後のミスマッチも防げます。
夜勤の有無や休日対応の頻度が気になる方は、ぜひ「活学キャリア」の無料カウンセリングを利用して、自分に合った働き方をしっかり相談してみてください。
スキルアップすればきつくなくなる?
スキルが上がることで、仕事の「つらさの質」は変わることが多いです。
例えば、キャリア初期は手順通りにしか対応できなかったトラブルも、経験と知識が増えると原因特定や根本的な改善提案ができるようになります。
これにより、単なる問題解決から一歩進んだ仕事の楽しさや達成感を感じられるようになるでしょう。
また、設計や自動化、プロジェクト管理などの上流工程に携わる機会が増えれば、物理的な拘束時間や夜勤などの負担が減ることも多いです。
ただし、スキルアップに伴い別の責任やプレッシャーが増える面もあるため、仕事の難しさがなくなるわけではありません。
それでも、より専門性の高い仕事に携われる喜びや、自分の成長を実感できる点で「きつさ」を乗り越えやすくなるのは確かです。
まとめ:インフラエンジニアはきつさはあるが、それ以上に得られる価値がある仕事
インフラエンジニアの仕事は確かに「きつい」と感じる場面もあります。
夜勤やトラブル対応、学び続ける必要性など、負担に感じる要素は少なくありません。
しかし一方で、社会の基盤を支えるやりがいや、技術力を活かしてキャリアアップできる可能性、そして安定した需要という大きな魅力も持っています。
向き不向きや働き方の選択によって、きつさを軽減しながら長く活躍することも十分に可能です。
自分に合った職場環境やキャリアプランを意識し、適切なサポートを得ることが、成功の鍵となります。
もし今の職場環境で負担が大きい場合は、異動や働き方の変更も含めて改善策を検討しましょう。
「活学キャリア」では、個々に合った改善策も提案しています。
まずはお気軽にご相談ください。

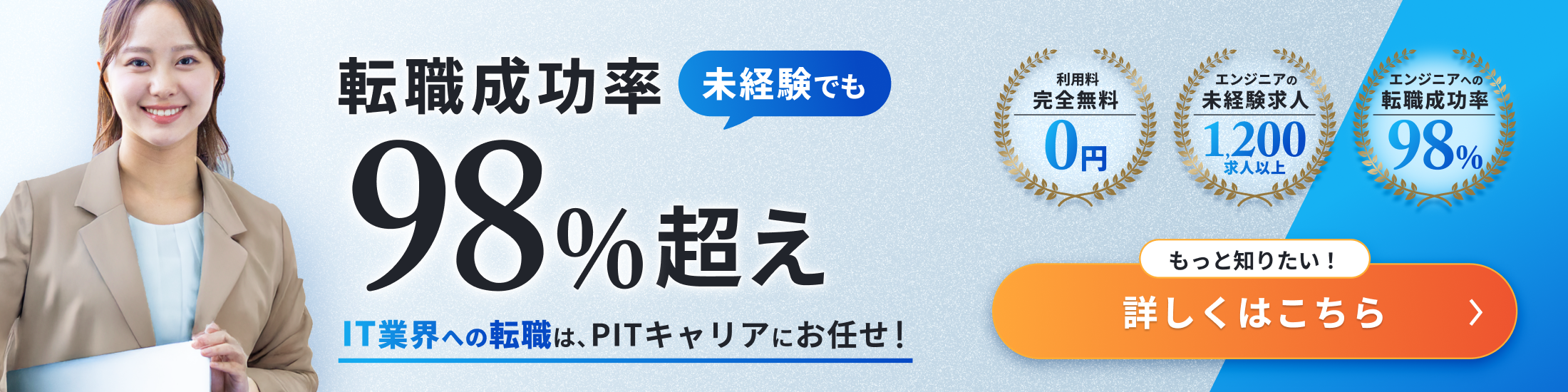
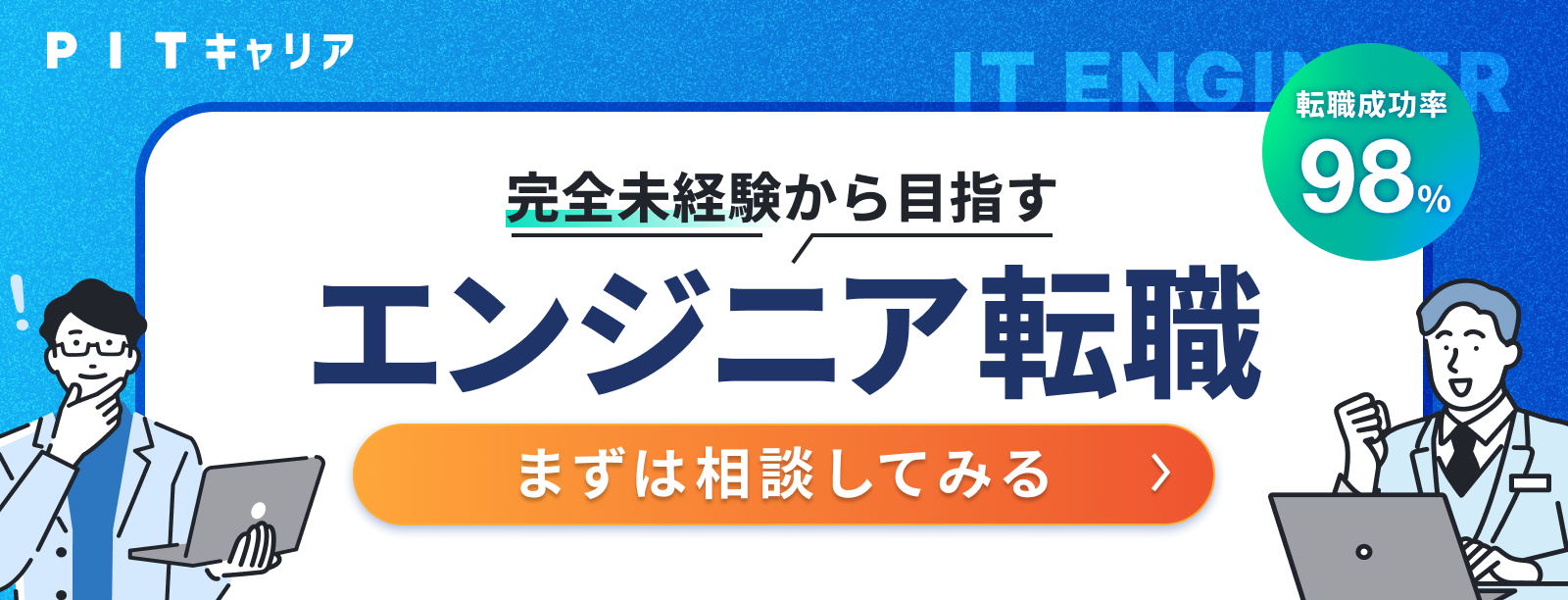
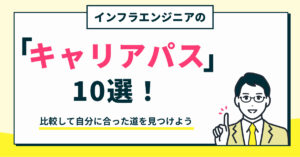
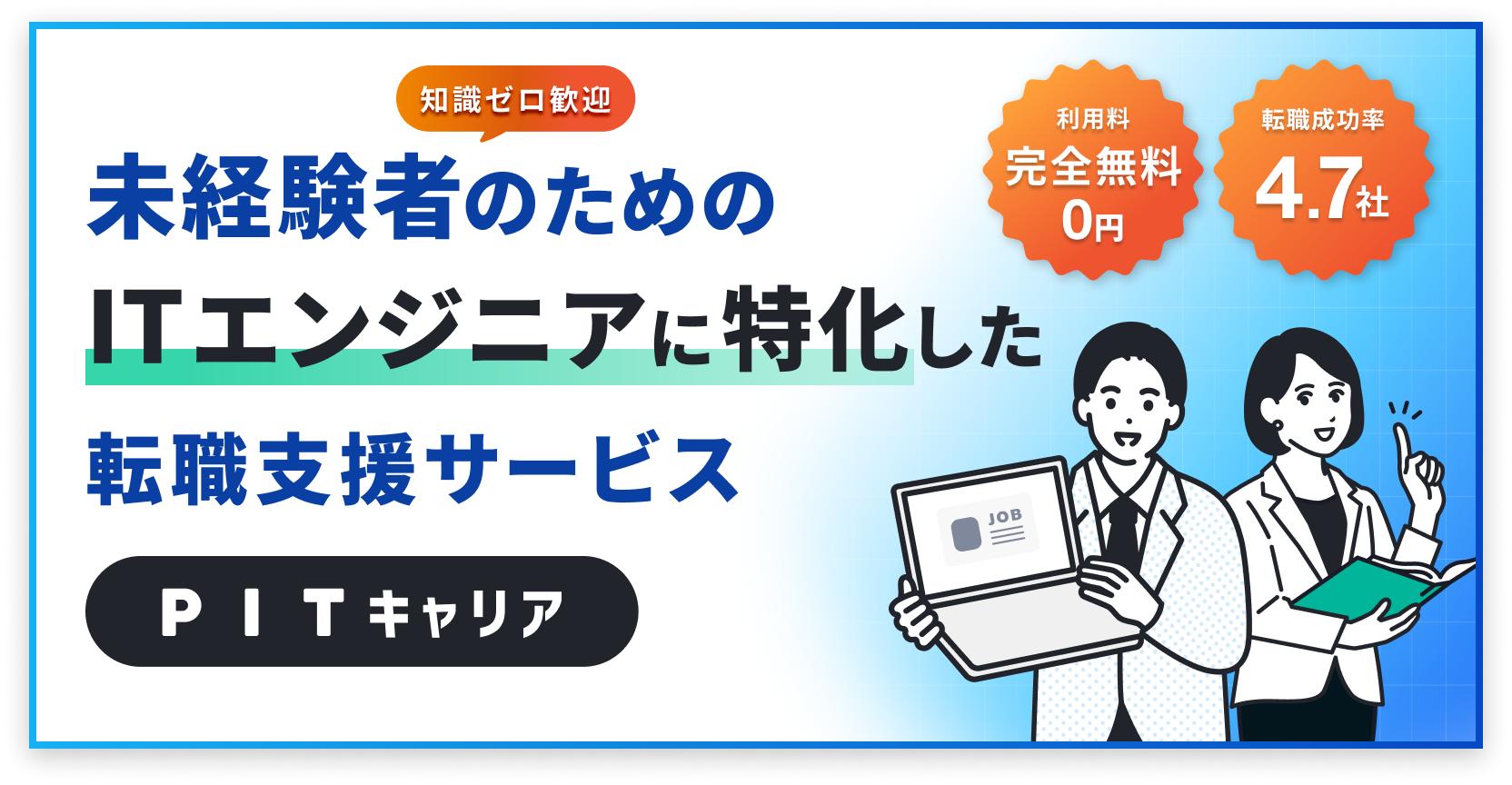
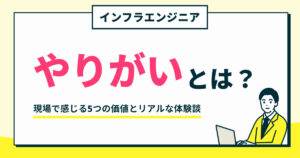
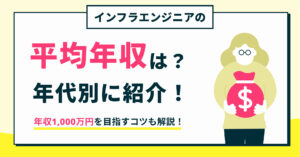
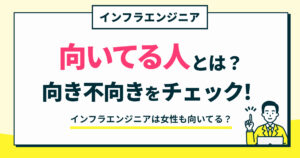
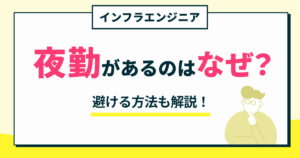
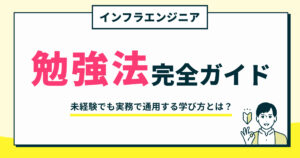





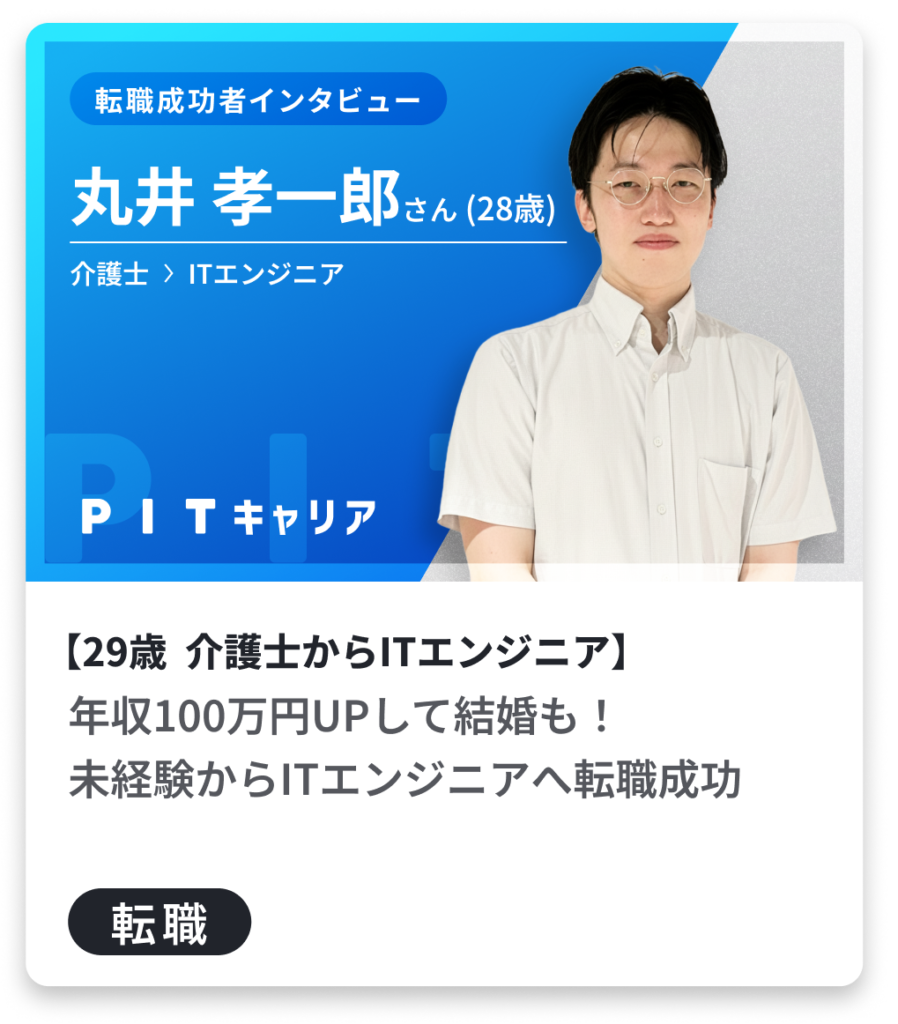
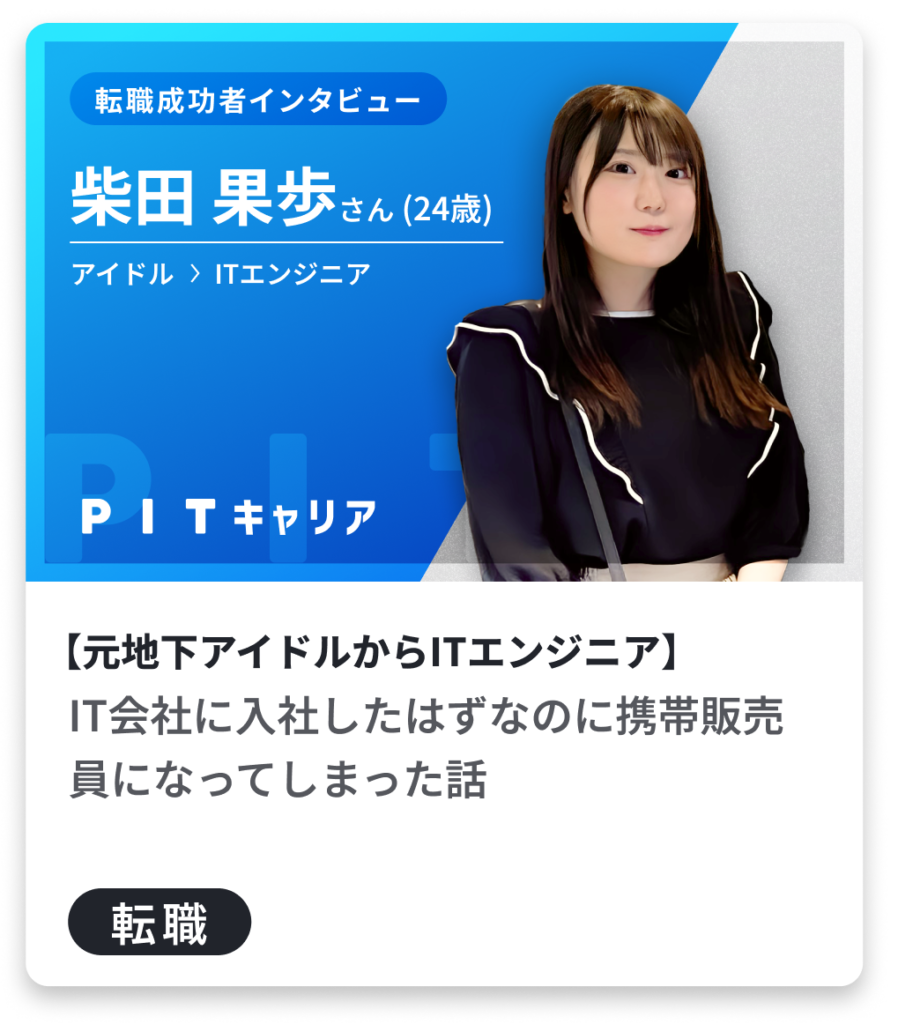
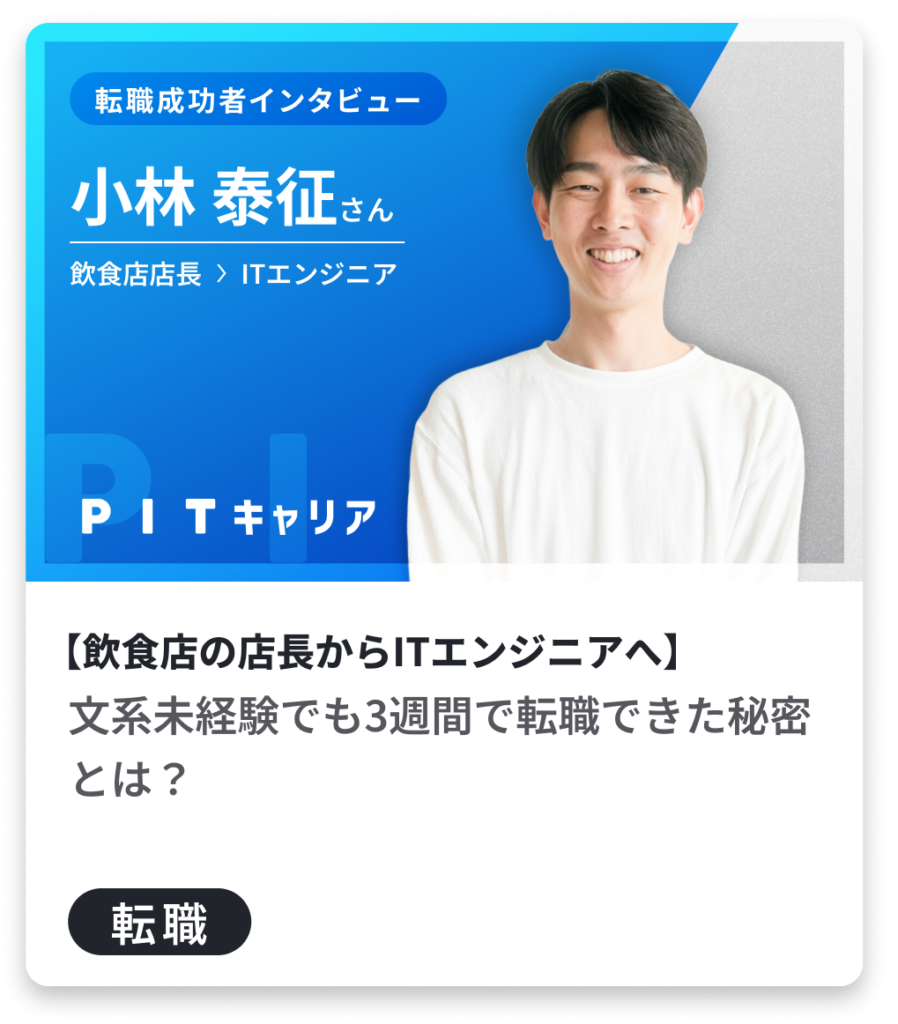

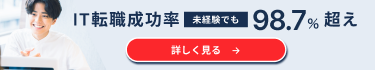
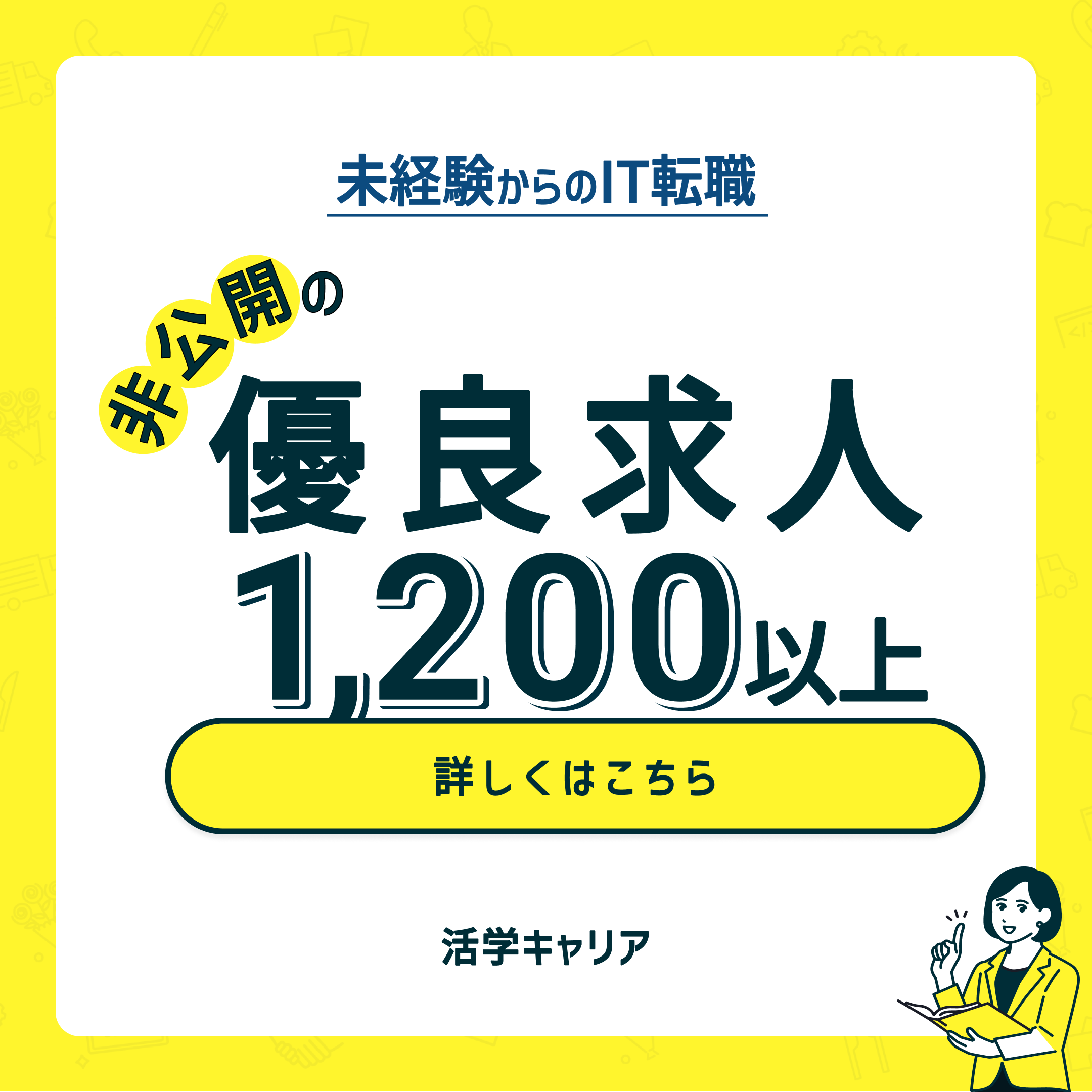

 お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
